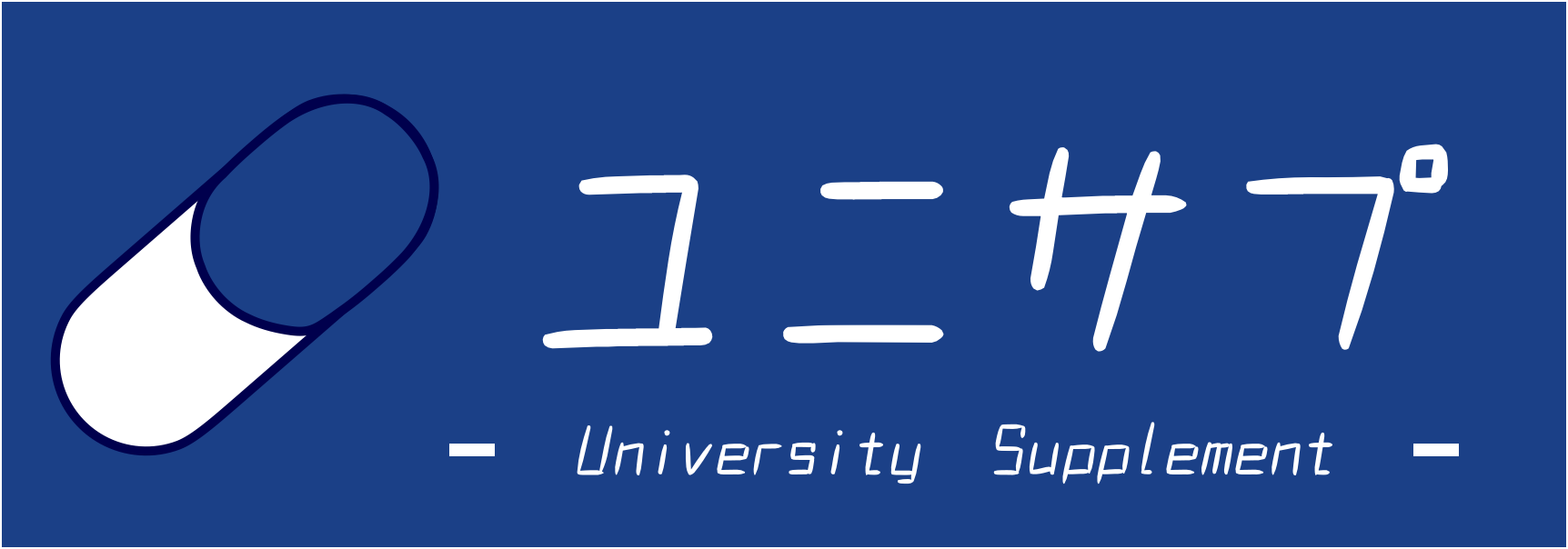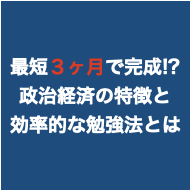こんにちは、ぼうです。
今回の記事は大学受験の社会科目である政治経済について科目の特徴から勉強の仕方等までを徹底的に解説する内容になります。
今まで政治経済の学習をしたことがない人や理系であってもこの記事を読めば、政治経済の全体感が理解できた上で、何から手をつければ良いのかわかるようになります。
また、政治経済という科目の性質上、長い期間をかけて勉強する方は少ない傾向にあるため、できるだけ短期間で成果が出る勉強の仕方がわかるよう解説しますね!
社会科目に悩んでいる人や、日本史世界史で行き詰まっていると感じている人などはぜひ参考にしてみてくださいね。
政治経済ってどんな科目?特徴は?
日本史や世界史などは人類の歴史について勉強するというイメージがつきやすいと思いますが、政治経済は少々イメージしにくい方もいるのではないでしょうか。
政治経済とは、大体18世紀以降に起きた歴史的な出来事に付随して起きた経済や文化の変化に伴い、人類がより良い国の統治の仕方について模索してきた流れを学ぶ科目と言えます。
紀元前の内容を学ぶ必要はありませんので学ぶ年代としても遡って400年程度と非常に短く、暗記の量は歴史系科目に比べると圧倒的に少ないという特徴があります。
しかし一方で、各国がさまざまな角度から経済的な出来事に向き合うために、同じ物事を様々な角度から分析・理解する必要がある科目とも言えます。
良い面も悪い面も様々な歴史に対してとってきた対策としての政治を学ぶことになるため、非論理的な羅列を覚える必要はなく、基本的には論理的な暗記をしていくことが大切な科目であるという特徴を持っています。
暗記と理解のバランスが大切な科目でもあるので、暗記が苦手な受験生であっても好きになれる可能性があります。
Stage1:政治経済の概要を理解する
政治経済の勉強の第一歩目はその他の社会科目と同様に基礎知識の詰め込みになります。
上記で紹介している、『畠山のスパッとわかる政治・経済爽快講義』は、政治経済という科目の全体感を掴むためには非常に有用な教材になります。
単元ごとに分かれて書かれている構成となっており、左側にその範囲のイメージ図やまとめが掲載されており、 右側にはイメージ図を捕捉する講義調の解説が掲載されています。
「〇〇は〜だね」のようにに語りかけてくれるタイプの教材なので、実際に授業を受けているかのような印象を受け、教科書ではすっと入ってこないという受験生でも使いやすのが特徴です。
また、基本的には毎年新しい改訂版が出ているのでその点に関してもおすすめできます。
政治経済の教材に関しては時事的な内容にも触れられているかどうかは大切なポイントになります。
日本史や世界史等の科目と異なり、政治経済では直近で起こった社会的な問題等もテーマとなることがあります。
2022年現在では新型コロナウイルスに関連する健康や保健の問題や、ロシアとウクライナの間の戦争に伴い国防や領土などに関する内容も出題される可能性があると考えて良いでしょう。
『畠山のスパッとわかる政治・経済爽快講義』勉強の仕方はシンプルで、①左側に書かれている政治経済のテーマに関する図を読み簡単にイメージ、②右側の講義を読みイメージを言葉で理解、③もう一度左側の板書などで知識を整理するという形になります。
日本史や世界史等の歴史科目はあくまで歴史上起きたことになるので、有機的な繋がりがない場合もあります。
一方で、政治経済は経済的な出来事に対する政治という構図があるため、基本的に論理的な繋がりがあるものがほとんどになります。
よって、わからないものをわからないまま暗記したところで使い物にならない恐れもあるため、勉強はできるだけ仕組みとして理解することが良いかと思います。
結局、日本史や世界史のように歴史を学ぶのではなく、政治と経済というシステムを勉強することになるので、システム(構造)を理解することで絶対的な暗記量を少なくすることができます。
例えばアメリカの政治制度とイギリスの政治制度をバラバラに覚えると暗記量が2倍になってしまいますが、根本の部分を理解すると両者の差異のみを覚えれば良いため暗記量が減り楽になります。
アメリカもイギリスも三権分立(立法・行政・司法の三者が互いに作用しながら存在している形)の仕組みを持っていることや、何かしらのチェックアンドバランス(互いが牽制しあって暴走を防ぐ仕組み)が作用しているというフレームを覚えてしまってから、各単語を理解するイメージですね。
アメリカは大統領制のため、国民は立法府の議員を選び、行政府の大統領も選ぶという仕組みになっており、国民から直接選ばれる大統領は強大な権力を持っています。
一方でイギリスは議院内閣制のため、国民は立法府の議員を選びますが、行政府のリーダーは立法の与党の代表がなる仕組みとなっています。
大きな仕組みは同じですが、それぞれの選ばれ方に差があるため、そのような差を意識しながら暗記の負担を減らすことができるように努めましょう。
Stage2:知識を入れる
政治経済の勉強の二段階目は知識の掘り下げを行うことです。
第一段階で『畠山のスパッとわかる政治・経済爽快講義』を用いて政治経済の基礎的な内容を理解することを目標としましたが、社会科目の基礎体力はあくまで暗記量のため、理解だけ頑張ったとしても点数には結びつきません。
『畠山のスパッとわかる政治・経済爽快講義』で理解した内容をしっかり掘り下げ暗記量を増やすことが第二段階目の目標であり、この内容には『一問一答』を用います。
政治経済の一問一答は代表的なものが山川出版と東進ハイスクールの2冊になりますが、この二冊に限ってしまえばほぼ好みによって選んでしまってもよいです。
個人的には教科書のブランドである山川出版の方が定義づけがわかりやすくシンプルな印象はありますが、飾りがなく悪い意味で無機質な教材なので、シンプルすぎるのが苦手な人は東進ハイスクールのものも参考にしてくださいね。
社会科科目に限らず、暗記のコツはとりあえず回数をこなすことです。
脳は一度覚えた内容をすぐに忘れてしまうという特徴を持っており、基本的には新しい記憶は3日と持たせることができないようです(詳しくは忘却曲線を調べてみてください)。
新しい記憶を定着させるためには脳に必要な情報であると思わせることが必要で、何度も記憶する内容ということは大切な内容なのだと脳にイメージさせ、そのために回数をこなすことが必要になるということです(少し難しいですね)。
例えば、山川出版の政治経済一問一答であればページ総数は概ね140Pです。
受験生であれば10周程度はミニマムで必要かと思いますので、根性で周回しましょう。
最初の1周目が一番厳しく、徐々に楽になっていくので最初が正念場になります。
しかし悲しいことに10周しても記憶は端から溢れてしまうため、忘れては打ち忘れては打ちの連続になります。
Stage3:問題を解いて練習する
政治経済の勉強の三段階目は教材を使って行う問題演習になります。
政治経済の勉強を頑張っているのにも関わらず成績が上がらない多くの受験生は、この問題演習の段階を手を抜きがちな印象があります。
社会の勉強とは知識を増やすものだという固定観念に縛られて、ずっと講義調の教材を読んでいたり、一問一答とにらめっこしていたりというイメージです。
こういった受験生は多くの場合、ある程度まで学力を伸ばすことはできますが、高レベルの段階までは到達できないことがあります。
勉強の基本はインプット(入れる勉強=暗記)だけではなくアウトプット(出す勉強=問題演習)も非常に大切になりますが、勉強が苦手な人ほどインプットに傾倒する習性があります。
勉強はインプットだけでなくアウトプットが大切である理由としては、人間はインプットの最中ではインプットの漏れに気づくことができないからです。
インプットを行った後にアウトプットすることで「さっき覚えたはずなのに、ここ覚えていなかった!」と気づくことができます。
そして、アウトプットを行う中で確認できたインプットの漏れを塞いでいくことが大切になるということですね。
積極的に問題演習することで自分の苦手な部分を発見し、概要理解とインプットに戻る、そしてまた問題演習をするという流れを大切しましょう。
余談ですが、受験生の中には単語カードやスマートフォンを用いた苦手メモのような自分で作るタイプの暗記ツールを利用している方も多くいるかと思います。
こういった暗記ツールは非常に便利ではありますが、勉強を始めた段階でこういった暗記ツールを利用することはあまりおすすめできません。
理由としては知識のインプットが甘いまま暗記ツールを自作すると、暗記ツールを作成する時間が膨大にかかり、実質自作の単語帳レベルで暗記ツールを作成しないとならない場合も多々あります。
これでは単語帳を複製しているだけの作業となり、作業自体は大変にも関わらず学力に一切反映されないという時間の浪費になります。
こういった暗記ツールは先程のインプットの漏れをアウトプットによって気づいたのちに、自分自身が間違いやすい内容を特定し、その範囲のみを暗記ツールとして残すことが効率的です。
Stage4:大学ごとに過去問演習をする
政治経済の勉強の最終段階は大学ごとの過去問対策になります。
政治経済に限らず大学の入試問題は学部ごとにも傾向があり、必要な対策が異なってきます。
法学部では憲法や法律などの法学系の内容、経済学部では経済史や経済理論などの経済学系の内容が聞かれることが多くなります。
こういった内容は単年の傾向ではなく、複数年に跨った傾向であることが多く、その大学がどのような知識を持った学生に入学して欲しいのか暗に示しているものでもあります。
例えば憲法に関する内容が毎年出題されているのであれば、憲法の条文からそれぞれの条項とその内容、またその憲法に関わる判例などを頭に入れることで正答率を高めることにつながるでしょう。
経済範囲であれば、文系であったとしても計算問題が出題されることもあり、こういった問題は多くの受験生が苦手で不慣れであるため、しっかりと対策を積めば他の受験生を引き離すチャンスになるとも言えます。
また、政治経済を選択科目にする場合、大学や学部に関係なく時事問題も積極的に取り組みましょう。
前述しましたが、昨今は新型コロナウイルスのことがあるため公衆衛生に関する内容や、それに伴う生存権や、国際関係などの知識も大切になるかもしれません。
また、アメリカ大統領選がありますので、アメリカの政治制度や選挙に関する内容も出題の可能性がありますね。
当然ですが、ロシアとウクライナの領土問題に関しても出題される可能性は非常に高くなるため、積極的に新聞やニュースなどに触れることでこれらの内容に鋭敏になるように努めましょう。
また、ロシアとウクライナの問題が現在話題になっていますが、ロシアウクライナ自体の問題だけでなく、国民主権領土の国家を構成する3要素の知識などそれに付随する内容が出題されることも多々あるため、関連知識の整理も大切です。
大学入試の過去問を早い段階から着手することで、志望する大学の入試傾向を知ることができ、その入試問題が求める知識と自身との差異を埋めることにつなげましょう。
最後に
政治経済の勉強の大きな流れは解説しましたが、理解できたでしょうか?
政治経済は暗記量に比べ、理解することが非常に多い科目でもあるため、一度仕組みを理解できれば最速で学力をつけることも可能な科目になります。
歴史系科目は少なくとも1年間の勉強が必要と言われますが、政治経済であれば最短3ヶ月程度でも十分戦える科目にできます。
英語や国語といったヘビーな科目に時間を割きつつ、最短ルートで偏差値をガンガンあげちゃいましょう!
それではまた、次回の記事でお会いしましょう!