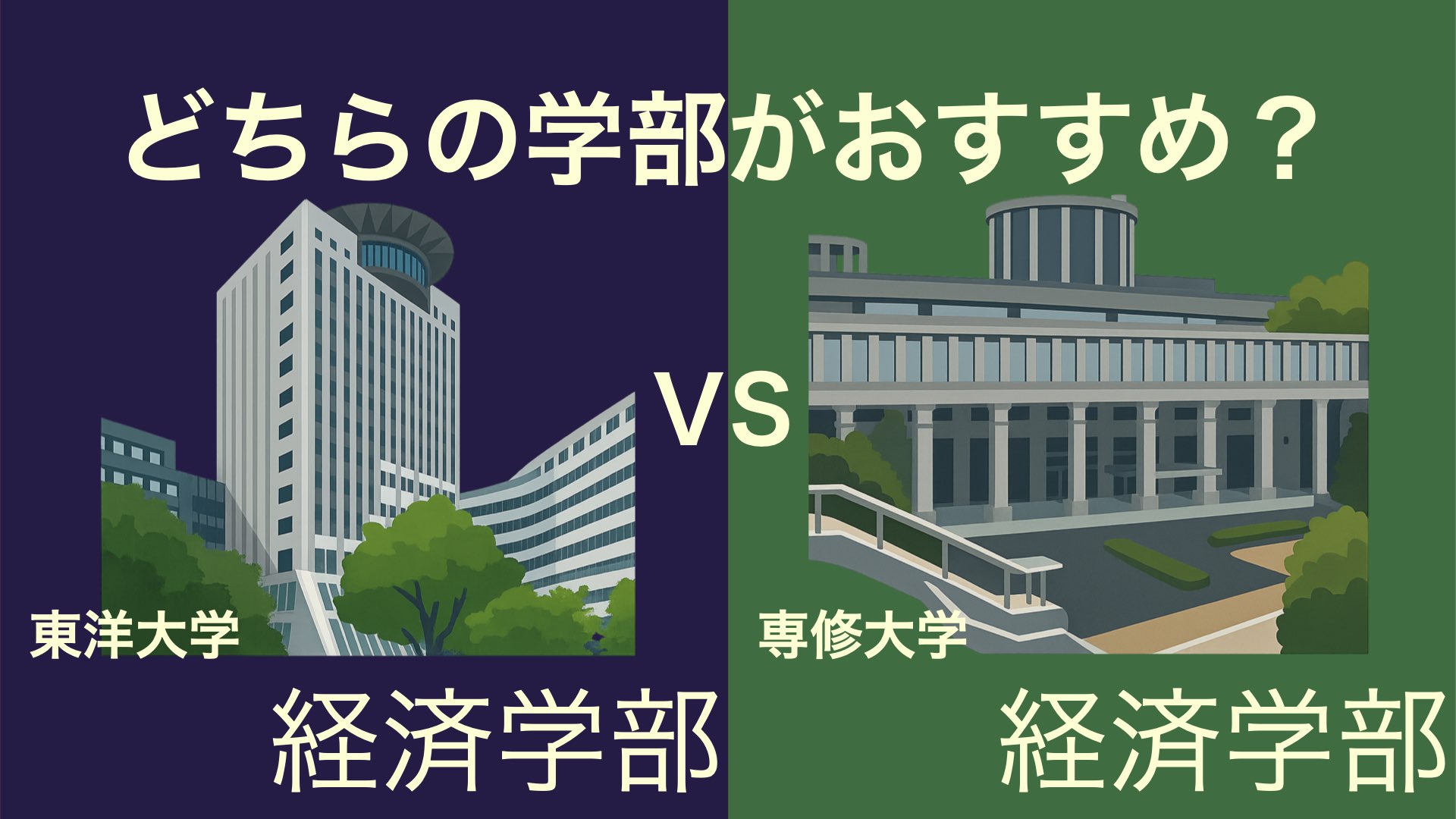東洋大学経済学部と専修大学経済学部はどんな大学?

基本情報
| 項目 | 東洋大学経済学部 | 専修大学経済学部 |
|---|---|---|
| 学部設立 | 1950年 | 1949年 |
| 所在地 | 東京都文京区白山5-28-20(白山駅) | 神奈川県川崎市多摩区東三田2-1-1(生田駅) |
| 学部理念 | 経済学部は、豊かな人間性に基づき、経済理論を基礎に、国際的視野を持って、日本の経済社会を学際的に考える、幅広い知識と的確な判断力を備えた、自立性のある人材を養成する。 | 経済的、社会的及び歴史的な諸事象を考察の対象とする専門的諸科学の研究成果を体系的に教授することにより、深い洞察力と高い批判力を備えた専門的教養を有する社会人及び職業人を養成する |
東洋大学経済学部は、1950年に設立された東洋大学の伝統ある学部の一つであり、近代日本の高等教育発展とともに成長してきました。キャンパスは東京都文京区の白山キャンパスに置かれ、都営三田線「白山駅」や東京メトロ南北線「本駒込駅」から至近という利便性の高い立地が特徴です。経済学の基礎理論から応用分野まで幅広く学べるカリキュラムが整備されており、金融・公共政策・国際経済など多彩な分野をカバーしています。学部設置当初から社会の要請に応える人材育成を目標とし、実学志向を強く打ち出してきたことが特色です。また、首都圏に位置するメリットを活かし、多数の企業や行政機関との連携を通じた実習・講座が展開されており、都市型総合大学としての強みが学びの環境に反映されています。
専修大学経済学部は、1949年に設立された専修大学の歴史を背負う看板学部の一つで、戦前から日本の経済教育に大きな役割を果たしてきました。所在地は東京都千代田区神田神保町の神田キャンパスと、神奈川県川崎市の生田キャンパスを拠点としており、学年によって異なるキャンパスで学ぶことになります。特に神田キャンパスは「学生街」として知られる神保町エリアに位置し、古書店や出版社に囲まれた学術的な雰囲気が特徴です。カリキュラムはミクロ・マクロ経済学を基盤に、金融経済、国際経済、環境経済など現代的な課題を扱う科目群も充実しています。実証的な研究手法やフィールドワークも取り入れており、社会との接点を意識した学びが展開されているのが特色です。長い伝統と都市型の立地を活かし、学術的にも実務的にも応用範囲の広い人材育成を目指す姿勢が際立っています。
大学の規模
東洋大学経済学部の規模は、学生数 616 名と大きく、私立大学の中でも比較的多くの学生を受け入れている点が特徴です。規模の大きさは、講義の選択肢やゼミの多様性に直結しており、経済学の幅広い分野を学びたい学生にとってメリットとなります。学生数が多いことで、同級生や先輩後輩との交流の機会も広がり、人脈形成にもつながりやすい環境が整っています。また、キャンパス内のクラブ活動やサークルも活発で、多様な学生が集うことで学問以外の活動も充実させることが可能です。大規模学部ならではのリソースの豊富さが、学習と生活の双方を支えています。
専修大学経済学部の学生数は 751 名で、こちらも比較的規模の大きな学部です。特に神田キャンパスを中心とした都市型の学習環境に、多数の学生が集まる点が専修大学の特色といえます。規模の大きさはゼミや専門科目の多様性を可能にし、学生の関心や将来の進路に応じて柔軟な履修計画を立てやすくなっています。また、同じ分野を学ぶ多くの仲間との切磋琢磨が、学びの質を高める効果を持っています。人数が多い分、同窓ネットワークも厚く、卒業後のキャリア支援や業界でのつながりにおいても大きな強みとなるのが、専修大学経済学部の規模の特徴です。
男女の比率
東洋大学経済学部と専修大学経済学部の男女比を比較すると、まず全体傾向として東洋大学経済学部は男子学生の比率がやや高めで、依然として「男子中心の学部」という印象を残しています。一方で専修大学経済学部は、男子学生が多数を占めつつも女子学生の割合が近年上昇傾向にあり、経済学分野における女性進出を反映したバランスの改善が見られます。特に私大経済学部では、青山学院大学や立教大学などで女子学生の比率が高く、専修大学経済学部の数値はそれらに比べるとまだ男性優位の構成ですが、東洋大学と比べた場合には「やや男女差が小さい」という特徴を持ちます。
また、首都圏の経済学系学部を広く見渡すと、多くの大学の経済学部も男子学生比率が6割を超えており、東洋・専修も同様の傾向に含まれます。ただし専修大学は他の伝統的な経済学部よりも女子比率が上昇している点で一歩先行しているといえ、これは教育方針としてキャリア支援や資格取得支援が女子学生にも広がっている影響と考えられます。一方の東洋大学経済学部は、依然として男子学生の割合が比較的高い構成のままであり、学内文化や部活動、サークル活動においても男子比率が強く反映されています。このため両大学を比較すると、専修大学経済学部の方が男女比のバランスにおいてやや多様性を反映しており、東洋大学は伝統的な男子中心の経済学部像を色濃く残しているといえるでしょう。
初年度納入金
東洋大学経済学部と専修大学経済学部の初年度納入金を比較すると、まず学費水準そのものは両大学ともに首都圏私立大学の経済学部として標準的な水準に位置しています。ショートコードで示される初年度納入金(tuition_first)によれば、両大学は授業料に加えて施設費や諸会費を含んだ総額で100万円を超える水準に設定されており、国公立大学と比較すると大きな差が見られるものの、他の私大経済学部と並べて見れば大きな乖離はありません。
具体的に見れば、東洋大学経済学部の初年度納入金は専修大学経済学部よりやや高めに設定されており、これは授業料に加えて施設設備費の比重が相対的に大きいことが背景にあります。一方、専修大学経済学部は比較的抑えられた水準であり、特に授業料部分の安定性に加えて奨学金制度が多様に整備されている点で、学生や家庭の負担軽減を意識した設計となっています。こうした違いは「年間の家計負担」という観点で比較すると明確に表れ、専修大学は学費の安さという点で優位性を持ち、東洋大学はやや高額ながらもキャンパス設備の充実度や学習環境に対する投資が反映されているといえます。
SNSでの評価
SNSでの評価について見ると、東洋大学経済学部と専修大学経済学部はいずれも首都圏の中堅私立大学として、大学選びの際に受験生や在学生が積極的に情報発信している点が共通しています。ただし、その評価のニュアンスには違いが見られます。
まず東洋大学経済学部については、SNS上で「規模の大きさ」や「学びの幅広さ」に言及する声が多く、特に大規模大学としての人的ネットワークやサークル活動の豊富さに肯定的な評価が寄せられています。一方で「学生数が多すぎて個別対応が弱い」といった批判的な意見も散見され、学習面よりもキャンパスライフや人間関係に関する言及が多い傾向があります。
専修大学経済学部に関しては、「実学的なカリキュラム」や「資格試験への対応力」に対する評価が一定数あり、キャリア志向の学生からの支持が目立ちます。また「規模が東洋よりもコンパクトで教員との距離が近い」とのポジティブな声がある一方で、「ネームバリューの点ではMARCHや日東駒専の他校に劣る」といった相対的評価が付されることも少なくありません。
他大学との比較に目を向けると、明治大学や青山学院大学などMARCHに所属する大学の経済学部は「ブランド力の高さ」がSNS上でしばしば強調される一方、東洋や専修は「コストパフォーマンス」「学習環境の身近さ」で評価される構図が見えます。つまり、SNSでは「大規模さとブランドの東洋」「実学志向で親しみやすい専修」というイメージが共有されており、いずれも受験生にとって大学選びの重要な判断材料となっているといえるでしょう。
合格難易度(偏差値・倍率)

偏差値(マナビジョン)
東洋大学経済学部と専修大学経済学部の偏差値を比較すると、両者ともに私立中堅大学群の中で重要なポジションを占めています。61 と 57 の数値は、いずれもMARCHや早慶上智といった上位私大には届かないものの、日東駒専クラスの中では安定した人気を維持していることが分かります。例えば同じ「日東駒専」グループに含まれる駒澤大学経済学部や大東文化大学経済学部などの数値と比べると、東洋・専修はいずれも上位に位置しており、実際の入試難易度でも「やや難関」に属します。
一方で、MARCH下位に含まれる明治大学や立教大学経済学部の偏差値と比べると差が大きく、入試戦略上では「併願先」「すべり止め」としての位置づけになることも多いです。つまり、日東駒専内では上位校として選ばれやすいが、MARCH以上を目指す受験生にとっては安全校的な役割を担う傾向が見られます。特に東洋大学は都心キャンパス移転の影響で志願者数が伸び、相対的に偏差値が専修大学をやや上回る傾向があります。一方、専修大学は法学部や商学部の評価が安定しており、経済学部も堅実な難易度を維持しています。
総じて、東洋・専修両大学は「日東駒専」中でも比較的高い難易度を示す学部であり、都市部での立地や知名度を背景に、地方私大の経済学部より明らかに入試難易度が高い位置にあります。そのため、進学を検討する際は、MARCH以上を狙う場合のセーフティライン、あるいは日東駒専の中で確実に学びたい学生に適した選択肢といえるでしょう。
倍率
東洋大学経済学部と専修大学経済学部の倍率・競争率を比較すると、両者ともに安定的に志願者を集める傾向があります。3.7 と 2.6 のデータをみると、いずれも日東駒専クラスの中では標準的な水準に位置しています。首都圏に拠点を置く大学として広く知られているため、地方私大の経済学部と比べれば競争率は高く、入学希望者の分母の大きさが際立っています。
また他大学との比較を行うと、例えば駒澤大学経済学部や大東文化大学経済学部ではやや倍率が下がる傾向が見られるのに対し、東洋・専修は依然として「志願者が多く集まりやすい学部」として位置付けられます。特に東洋大学はキャンパスの都心移転効果もあり、受験生人気の高まりによって近年倍率が上昇する場面もあります。一方、専修大学は堅実な学風からリピーター受験層が厚く、安定的に一定の志願者数を確保している点が特徴的です。
このように倍率の面から見ると、東洋と専修はどちらも「日東駒専」中で相対的に高い競争率を維持しており、MARCH下位校の滑り止めとして機能する一方で、内部的には日東駒専内で志願者が集中しやすいポジションにあるといえます。したがって、両大学経済学部はいずれも「入学のしやすさ」というより「受験生の人気が安定的に高い」という特性を持っており、学部選びの際にはこの競争率の高さも意識する必要があるでしょう。
卒業後の進路

有名企業の就職率
東洋大学経済学部の進学率は 4.6% です。進学者は、計量経済・公共政策・金融工学など理論とデータ分析を重ねる領域や、国際経済・地域政策の研究系ゼミ出身者に多い傾向があります。就職志向が強い学部であっても、研究テーマを深掘りしたい学生は学内外の大学院へ進み、研究職・政策系・シンクタンク志望へとつなげています。相対的位置づけとしては、日東駒専の分布の枠内に収まる標準域で、年度差や方式差(一般選抜・総合型など)により上下が生じるレンジです。大学群を横断してみると、GMARCHでは研究志向が強い学科構成の影響で進学率が高めに現れる学部も見られるため、群全体のレンジと照合した場合に中程度のポジションに置かれるケースが多いと言えます。進学希望者向けには、研究計画立案支援や外部大学院説明会へのアクセス、教員ネットワークの紹介などが整備されており、学部段階での実証演習や卒業研究の濃度がそのまま進学準備の質に直結する環境です。
専修大学経済学部の進学率は 2.2% です。経済理論・統計・ファイナンス系で専門性を高めたい学生が学内外の大学院に進む一方、就職を選ぶ学生が多数派という点は経済系学部の一般的傾向と一致します。相対的には、日東駒専のレンジに沿う水準で推移し、年度要因や募集区分の違いにより東洋大学との相対差が前後する範囲にあります。大学群比較では、GMARCHには研究主導のカリキュラムを持つ学部が含まれるため、群全体と並べると中程度〜控えめに位置づけられる局面が多く、専修では少人数ゼミの研究指導や教員の推薦ネットワークを活用して、選抜要件(研究計画書・口頭試問・英語外部試験など)への対策密度を高めていく形が主流です。就職志向の厚さを背景に、大学院進学組は少数精鋭で計画的に準備を進めるスタイルが根付いているのが特徴です。rr
主な就職先
アクセンチュア(名)
JTB(名)
川崎市役所(5名)
富士ソフト(4名)
東洋大学経済学部では上記の他に、金融業界や地方銀行への就職が目立つほか、大手損害保険会社や証券会社など幅広い金融関連企業に進む学生が多く見られます。また、製造業や流通業といった伝統的な大企業にも一定数の就職実績があり、特に食品、機械、住宅関連など生活基盤に直結する分野での採用が堅調です。さらに、商社や情報通信業界など、経済学の学びを応用できる分野への関心も高く、多様な進路が確保されています。
専修大学経済学部では上記の他に、金融機関の中でも地方銀行や信用金庫、証券会社など安定したキャリアを選ぶ学生が一定数います。また、大手小売業や物流企業への就職が多く、経済学で培ったマクロ・ミクロ両面の知識を活かして事業戦略や流通システムに関わるケースが見られます。さらに、IT関連企業やサービス業にも進出しており、時代の変化に応じて幅広い業種への対応力があることが特徴です。
進学率
東洋大学経済学部の進学率は 4.6% です。経済学の基礎を固めたうえで大学院に進む学生も一定数おり、研究テーマとしては金融政策や国際経済、地域経済分析などの分野が多く見られます。ただし全体的には学部卒業後すぐに就職を選ぶ学生の方が大多数を占め、進学率は日東駒専グループ全体の平均とほぼ同程度にとどまります。進学を選ぶ学生は、専門性を高めて研究職・教育職を志すか、あるいは資格取得や将来的なキャリア形成を視野に入れて大学院をステップとして活用する傾向があります。GMARCHグループと比較すると大学院進学率は相対的に低い位置にあり、研究大学としての色彩は薄めですが、逆に実務志向の強さが表れているとも言えます。
専修大学経済学部の進学率は 2.2% です。こちらも学部卒業後に直ちに企業就職を目指す学生が大半であり、進学者は全体の中では少数派にとどまります。大学院に進学するケースとしては、経済理論の深化や統計学・データ分析といった実証研究を軸にしたものが中心で、将来的に公的研究機関や教育関連職を志す学生に多く見られます。専修の進学率は日東駒専グループの標準的な水準であり、他大学と大きな差は認められません。GMARCHクラスの大学と比べれば数値的には低めですが、その分、学部教育の段階で職業的スキルや就業適性を強調するカリキュラムが充実しており、大学院に進まずとも社会で活躍できる基盤づくりが重視されています。
留学生

受け入れ状況
東洋大学経済学部の留学生数は 203名 です。日東駒専グループの中では比較的多い方に位置しており、特にアジア圏からの学生受け入れが目立ちます。東洋大学は「国際化」を大学全体の方針の一つとして掲げており、学部レベルでも留学生向けの日本語教育科目や、国際交流イベントを通じた学生同士の交流が積極的に行われています。他大学と比べると、同規模の日東駒専の中では上位水準で、グローバル人材育成に力を入れる姿勢が表れています。一方でGMARCHと比較すると数値的にはやや劣る傾向があり、特に英語による専門教育プログラムの量的充実度では差が見られます。
専修大学経済学部の留学生数は 385名 です。こちらもアジア圏を中心とした留学生が多く、キャンパス内での文化交流が一定程度活発に行われています。ただし全体の規模感としては東洋大学に比べて控えめであり、日東駒専内では平均的な位置にあります。授業面では外国人留学生向けの基礎日本語教育科目を備えるなどサポート体制は整っていますが、国際プログラムの数や規模ではGMARCHクラスに後れを取る印象があります。総じて、専修大学の国際色は地域的な偏りが少なく安定しているものの、全体的なボリューム感では東洋大学に一歩譲る傾向が見られます。
海外提携校数
東洋大学経済学部の海外提携校数は 259 校 です。日東駒専グループの中では比較的積極的に国際提携を進めている大学に位置し、アジアや欧米を中心とした交換留学プログラムを提供しています。これにより、学生が長期・短期で海外に渡航しやすい環境が整っており、国際経験を積む機会は日東駒専内でも豊富な部類といえます。ただし、GMARCHクラスの大学群と比較すると提携校の数や多様性においてやや劣り、特に欧州の名門大学とのネットワーク形成では差が見られます。とはいえ、実務的な英語力や異文化理解を身につけたい学生にとっては十分な機会が用意されている点が特徴です。
専修大学経済学部の海外提携校数は 36 校 です。提携校の数は東洋大学と比較するとやや控えめで、日東駒専内では平均的な位置にあります。交流先はアジアを中心としつつ、北米や欧州にも一定のネットワークを持ち、交換留学や短期語学研修などを通じた実践的な国際交流の機会を提供しています。ただし、全体的な規模感としてはやや限定的であり、より多彩な選択肢を望む学生には物足りなさを感じる可能性があります。他方で、提携校との関係は比較的密接で、少人数でのきめ細かい交流が実現している点は評価できます。総じて、専修大学は「広さ」よりも「深さ」を意識した国際連携が特徴といえるでしょう。
結局東洋大学経済学部と専修大学経済学部のどちらが良いか

東洋大学経済学部と専修大学経済学部を比較すると、両者ともに首都圏の有力な私立大学として歴史と伝統を有し、経済学教育に強みを持っています。東洋大学は学生数が多く、幅広い分野をカバーするカリキュラムを提供しており、学問的な探究心を育むとともに実社会に即した応用力を高めることを目指しています。立地も東京都文京区白山にキャンパスを構え、都心のアクセスの良さを活かしながら企業や官公庁との接点を持ちやすい点が特徴です。一方、専修大学経済学部は、明治期の経済教育の先駆けとして創設された伝統を背景に、経済学の専門性に特化した教育を展開しています。神田キャンパスをはじめとした都心部での学びの機会も多く、経済研究や実務教育の両面で強みを発揮しています。
就職の面で見ると、東洋大学は学生規模の大きさを活かし幅広い企業や業界への就職実績を持ち、有名企業への就職率においても安定した評価を得ています。特に金融業やメーカー、大手流通などに強く、卒業生のネットワークの広さも大きな魅力となっています。専修大学は歴史的に経済学や商学に力を入れてきたことから、金融・証券・保険といった分野への就職に厚みを持ち、伝統校ならではの卒業生ネットワークが活かされやすい環境があります。また、就職サポート体制の充実度でも高い評価を受けています。
結論として、幅広い分野に対応した経済学教育や多様な進路を志向するなら東洋大学経済学部が適しており、より専門的で伝統的な経済学教育を受けたい場合や金融関連の進路に強みを求めるなら専修大学経済学部が良い選択となります。どちらを選ぶかは、自身が将来どのような進路を描きたいかによって判断するのが望ましいでしょう。