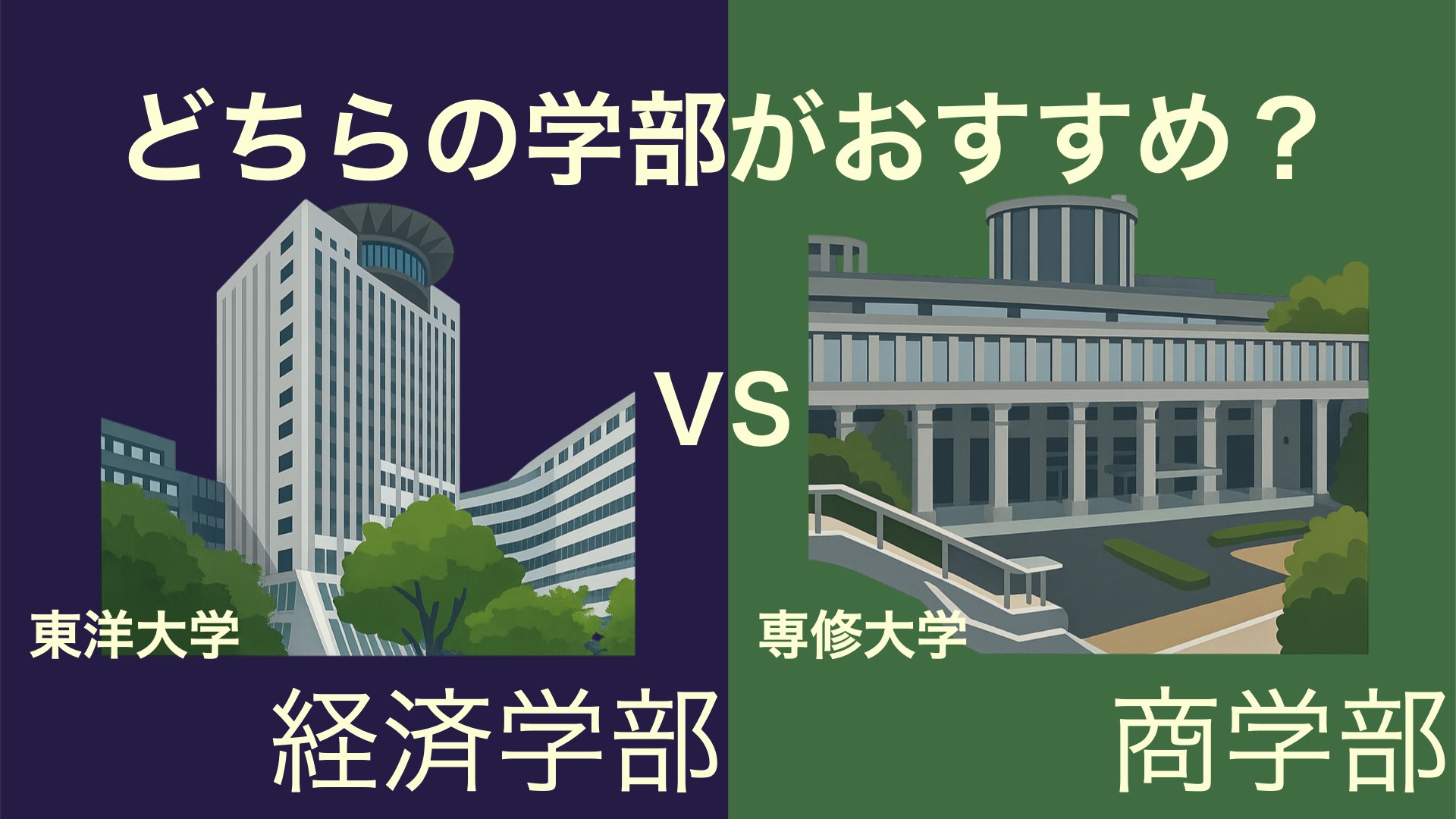東洋大学経済学部と専修大学商学部はどんな大学?

基本情報
| 項目 | 東洋大学経済学部 | 専修大学商学部 |
|---|---|---|
| 学部設立 | 1950年 | 1965年 |
| 所在地 | 東京都文京区白山5-28-20(白山駅) | 東京都千代田区神田神保町3-8-5(神保町駅) |
| 学部理念 | 経済学部は、豊かな人間性に基づき、経済理論を基礎に、国際的視野を持って、日本の経済社会を学際的に考える、幅広い知識と的確な判断力を備えた、自立性のある人材を養成する。 | 専修大学商学部はビジネスに関わる「 ヒト」「モノ」「カネ」、そして「 情報 」の「 仕組み」を明らかにして、ビジネスに必要とされる実践的な知識や技術、倫理観および国際的視点について基礎から学習することを教育理念 としています。 |
東洋大学経済学部は1950年に設立され、首都圏の私立大学群の中でも比較的規模の大きな学部として発展してきました。経済学の教育研究に重点を置き、伝統的に実学と理論をバランスよく学べる環境を提供している点が特徴です。キャンパスは東京都内に位置し、都心部や副都心からのアクセスも良好で、学生にとって通いやすい立地となっています。学部の歴史的背景としては、大衆教育の普及や高度経済成長期に伴う経済学教育需要の拡大を背景に発展を遂げており、地域社会や企業との連携を通じて実践的な学びを重視してきました。都市型キャンパスならではの利便性を活かし、ゼミや研究活動も活発で、幅広い学びの選択肢を持つ学部といえます。
専修大学商学部は1965年に設立され、戦後の日本社会における商学教育の拡大期に大きな役割を果たしてきました。商学部は経営・会計・マーケティングなど幅広い分野を体系的に学べることを特色とし、社会や産業界との結びつきが強い点が伝統的な強みです。キャンパスは都心からやや離れたエリアにありながらも交通網の発達によりアクセスが容易で、落ち着いた学習環境と首都圏ならではの企業活動への接点の両方を得られる立地条件となっています。歴史的にみると、商業実務に直結した教育を礎としながら、学術研究との融合を進めることで、学部としての地位を高めてきました。学生は理論と実務の双方を意識した教育環境の中で、社会で即戦力となるための学びを展開できるのが特徴です。
大学の規模
東洋大学経済学部の学生数は616名で、学部としても比較的大規模な構成を誇っています。この規模の大きさは、学科や専攻の多様性に直結しており、経済学の基礎から応用、さらに社会問題や国際経済といった幅広いテーマに対応できる教育体制を実現しています。また、学生数が多いことでゼミやサークル、課外活動も活発で、異なる価値観を持つ仲間との交流機会が豊富に得られる点も大きな魅力です。一方で規模が大きいがゆえに、講義の一部は大人数形式となり、主体的に学びを深めるためには積極的な行動が求められる側面もあります。総じて、規模の大きさが学びと交流の幅を広げる原動力になっている学部といえるでしょう。
専修大学商学部の学生数は648名で、東洋大学と比較するとやや小規模な構成となっています。この規模は、授業やゼミにおける教員との距離感を近くし、アットホームな教育環境を形成しています。学生数が抑えられていることにより、少人数制のゼミや演習で手厚い指導を受けられる傾向があり、実践的な学びを重視する商学部の教育方針に合致しています。特に、会計やマーケティングなど専門性の高い分野では、教員から直接指導を受けられる環境が学生にとって大きなメリットです。一方で、規模がやや小さいため、交流の幅や課外活動の多様性は経済学部のような大規模学部に比べると制約がある面も否めません。しかしながら、その分一人ひとりに目が届く教育環境が整っている点は大きな強みとなっています。
男女の比率
東洋大学経済学部の男女比は72.4 : 27.6で、全国的にみても標準的な傾向を示しています。経済学という分野は男女問わず幅広い層に人気があるため、極端な偏りはなく、授業やゼミ活動でも多様な意見が飛び交いやすい環境が形成されています。大規模学部であることも相まって、男女それぞれの割合が均衡しやすく、学生生活における人間関係の幅広さにもつながっています。男女の比率が大きく偏らない点は、将来の社会に出たときの人間関係の構築にも直結する要素であり、バランスのとれた環境で学べることは大きな利点といえるでしょう。
専修大学商学部の男女比は56.5 : 43.5で、こちらも大きな偏りは見られず、他大学の商学部と比較しても平均的な水準に収まっています。商学部の性質上、会計や経営、マーケティングといった領域には男女双方から関心が集まりやすく、ゼミや授業においても自然に多様な視点を取り入れることが可能です。特に少人数での演習が重視される環境においては、男女のバランスが保たれることで議論の多様性が増し、実社会さながらの意見交換の場が形成されやすくなります。結果として、学生同士が互いに補い合いながら成長できる学びの場となっている点が特徴です。
初年度納入金
東洋大学経済学部の初年度納入金は126.5で、私立大学経済系学部としては標準的な水準に位置しています。授業料や施設費などが含まれるこの金額は、首都圏に所在する同規模の大学と比較すると突出して高額ではなく、家庭の経済的負担をある程度抑えながら、充実した教育設備を享受できる点が特徴です。さらに、大学全体として奨学金制度や給付金の種類も多く、学費面での支援を受けやすい体制が整っているため、学生の学習意欲を長期的に支える仕組みが構築されています。
専修大学商学部の初年度納入金は122.6で、こちらも私立商学系学部の中では平均的な負担感に収まります。他大学の商学部と比較しても大きな差はなく、経営学やマーケティング分野を学ぶ環境として十分なコストパフォーマンスを備えています。加えて、専修大学は比較的実務に直結する教育を重視しており、資格取得支援やキャリア教育に力を入れていることから、学費に見合った投資効果が得られやすい点が評価されています。家庭にとって大きな負担となりやすい私立大学の学費ですが、専修大学の場合は教育内容と費用のバランスを考慮すれば納得感を得やすい水準といえるでしょう。
SNSでの評価
SNSでの評価に目を向けると、東洋大学経済学部は「大学全体の規模感が大きく、幅広い学生層と交流できる点が魅力」とする声が多く見られます。特に首都圏の学生にとってアクセスの良さや知名度が高く、SNS上では「就職活動での知名度の安心感」や「資格取得や公務員試験のサポート体制が整っている」といったポジティブな意見が散見されます。一方で、「大規模大学ゆえに個別のサポートがやや手薄になる」との声もあり、学生自身が積極的に動く姿勢が求められるという評価も見受けられます。
専修大学商学部については、「実学志向の授業が多く、ビジネスに直結する学びが得られる」との評価が多く、SNS上でも「資格講座やキャリア支援が充実している」という意見が目立ちます。特に商学部としての実務連携の強さやOB・OGネットワークを評価する声が多く、「就職活動で役立った」という投稿が多いことが特徴的です。ただし、「キャンパスの立地によって通学がやや不便」とする意見や、「学内のブランド力は他の有名私大に比べて劣る」との声も一定数見られ、評価は一様ではありません。
全体として、東洋大学は規模と知名度、専修大学は実学重視と支援体制の充実という特徴がSNSでの評価に反映されており、どちらを選ぶかは学生が求める学びのスタイルやサポート環境への期待によって評価が分かれているといえます。
合格難易度(偏差値・倍率)

偏差値(マナビジョン)
偏差値・入試難易度について見ると、東洋大学経済学部は 61 程度、専修大学商学部は 59 程度となっています。いずれも中堅から上位私立大学の水準に位置づけられ、首都圏の受験生にとって現実的かつ競争的な選択肢といえます。東洋大学は学部の規模が大きく、全国的に知名度もあるため志願者数が安定して多く、専修大学は商学に特化した学びを求める層に人気があり、毎年一定の競争が見られます。
他大学グループと比較すると、例えばGMARCHと比べるとやや低めの水準に位置するものの、日東駒専の枠内では偏差値は上位に属しており、選抜の厳しさは同グループ内でも目立ちます。特に、近年は志願者の多様化によって、学部ごとの人気に波があるものの、経済・商といった社会科学系の学部は安定的に需要が高く、受験生にとっては確実に合格を勝ち取るための十分な準備が必要とされます。
また、入試形式も多様化しており、一般選抜に加えて共通テスト利用方式や推薦入試など幅広い選択肢が設けられています。これにより、学力一本ではなく多様な評価方法によって入学のチャンスが与えられていますが、その分、競争は質的に厳しさを増しているともいえます。こうした点からも、両大学は日東駒専の中で比較的高い入試難易度を維持しており、受験生にとっては十分な対策が求められる環境といえるでしょう。
倍率
倍率・競争率について見ると、東洋大学経済学部は 3.7、専修大学商学部は 3.2 という数値が示されています。いずれも中堅私立大学としては標準的ながら、学部の規模や知名度の違いにより、志願者数や競争の様相には差が見られます。東洋大学は首都圏に広く認知される総合大学であるため、毎年安定的に受験生を集め、結果として倍率も安定傾向にあります。一方、専修大学は商学分野に特化した学びを提供しており、受験生の志望動機が明確であるため、少数精鋭の競争が形成されやすい特徴があります。
他大学グループとの比較を行うと、GMARCHに比べれば倍率はやや抑えられているものの、日東駒専の水準としては十分に競争的であり、合格を得るには相応の準備が不可欠です。特に近年では、併願先として上位校を志望する受験生も受験することから、合格ラインは安易に下がることなく、一定の難易度を維持しています。このため、両大学の倍率は日東駒専の平均的な水準よりもやや高めに位置しており、受験生にとっては油断できない環境となっています。
さらに、一般選抜のみならず共通テスト利用方式や推薦入試の導入が広がっていることで、表面的な倍率だけでは測れない複雑さもあります。実際には方式ごとの難易度や競争率に差があり、受験生は戦略的に出願方法を選択する必要があります。こうした背景から、東洋大学経済学部と専修大学商学部の倍率は日東駒専全体の傾向を示すとともに、両校のブランド力や学部特性を反映した競争の厳しさを表しているといえるでしょう。
卒業後の進路

有名企業の就職率
有名企業就職率について見ると、東洋大学経済学部は 9.6、専修大学商学部は 7.5 という結果が出ています。どちらも日東駒専グループに属する学部としては比較的堅調な水準を示しており、学部で培った知識や資格取得支援の体制が就職実績を支えています。東洋大学は大規模総合大学であるため、多様な業界への就職実績が豊富であり、学生の進路選択に幅があることが特徴です。一方、専修大学は商学分野に重点を置いているため、金融や流通、商社系を中心に安定した実績を持ち、専門性を生かしたキャリア形成に強みがあります。
他大学グループとの比較において、GMARCHと比べればやや数値は控えめであるものの、日東駒専の平均的な水準と比較すると両学部とも上位に位置づけられます。これは首都圏での知名度や企業とのつながり、OB・OGネットワークの活用が就職活動において効果的に働いているためです。加えて、資格取得講座やインターンシップ支援など大学独自のキャリア形成支援も実績を後押ししています。
総じて、両大学の就職率は日東駒専グループの中では安定的かつ比較的高い水準にあるといえます。学生にとっては、自身の適性や将来のキャリアビジョンに応じて「幅広い進路の選択肢」を重視するなら東洋大学経済学部、「商学の専門性や実務直結型のキャリア」を志向するなら専修大学商学部が適していると考えられます。
主な就職先
アクセンチュア(名)
JTB(名)
東京都特別区Ⅰ類(4名)
エン・ジャパン(4名)
東洋大学経済学部では上記の他に、幅広い業種への就職実績が見られます。金融業界では銀行・証券・保険といった分野に人材を輩出しており、特に営業職や総合職としての採用が多い点が特徴です。また、製造業やメーカー関連への就職も堅調で、自動車・電機・食品といった分野での採用実績が確認されています。さらに、流通業や小売業、商社などでも活躍が見られ、全国的に展開する大手チェーンや専門商社で働く卒業生も少なくありません。情報通信分野ではITサービスやシステム開発会社に進む学生も増えており、経済学部で培った数理的分析力や経済理解を応用できる分野として人気が高まっています。加えて、公務員志望者も一定数おり、国家公務員や地方自治体職員として地域社会に貢献する進路も安定して確保されています。こうした多様な業種への就職実績は、東洋大学が持つ総合大学としてのネットワークの広さや、OB・OGの人的つながりの強さに支えられており、特定業界に偏らないバランスの良さが際立ちます。
専修大学商学部では上記の他に、特にビジネス系学部の強みを活かした進路選択が多く見られます。金融業界への就職は伝統的に強く、銀行・証券・保険といった大手企業に安定した採用実績を持っています。また、商学部の性格上、流通業や小売業、さらにはサービス業への進出が目立ち、経営管理やマーケティング、販売戦略などを学んだ学生が現場で即戦力として評価されています。さらに、製造業や商社に進む卒業生も一定数存在し、経済活動の中心である企業間取引や営業の分野で活躍しています。近年ではIT関連企業やベンチャー企業に挑戦する学生も増えており、情報化社会に対応する柔軟なキャリア形成が広がっています。加えて、公務員や教育関連機関に進む学生も安定的に見られ、社会的信頼を得たキャリア形成も実現されています。専修大学は商学分野に特化した教育を展開しているため、企業経営に関する理論と実務を兼ね備えた人材を多方面に送り出しており、就職市場においても存在感を示しています。
進学率
進学率について見ると、東洋大学経済学部は 4.6、専修大学商学部は 2.2 という結果が確認できます。両学部ともに、伝統的に就職志向が強い傾向があるため、進学率は突出して高い水準ではありませんが、一定数の学生が大学院や専門職大学院へと進む姿勢を見せています。特に経済学部では、公共政策や経済理論の高度な研究を志望して進学する学生が一定数存在し、商学部では会計・経営研究科やMBAなど、実務的な専門知識を深める進学先が選択肢となります。
他大学グループとの比較では、GMARCHの進学率が研究志向の強さからやや高めの数値を示す一方、日東駒専グループの中では東洋大学・専修大学ともに標準的か、やや上位の位置づけにあるといえます。特に首都圏での認知度の高さや学部の専門性が、進学を選ぶ学生にとって安心感を与えており、将来の学術的キャリアを考える場合にも一定の評価を受けています。
総合的に見ると、就職を前提とする学生が多数派である一方で、進学を志す学生には大学院レベルでの研究環境やカリキュラムが整備されているため、専門分野に踏み込んだ学習を継続することが可能です。したがって、研究や専門職に関心がある学生にとっては進学の道も十分に用意されている学部だといえるでしょう。
留学生

受け入れ状況
東洋大学経済学部における留学生数(203名)は、国内でも比較的多様な国・地域から学生を受け入れており、アジア圏を中心に欧米からの留学生も在籍しています。経済学という分野はグローバル経済との関連性が高いため、授業やゼミにおいて国際的な視点を持ち込む留学生の存在は学修環境を豊かにしています。また、大学としても国際交流科目や英語開講科目を拡充させており、日本人学生と留学生が合同で議論する場を数多く提供している点が特徴です。こうした交流は経済学の知識をグローバルな社会で活かす力を養う機会となっており、国際感覚の育成に直結しています。
専修大学商学部の留学生数(385名)は、学部としては中規模ながらも着実に増加傾向にあります。特にアジアのビジネス関連学部からの交換留学生が多く、商学の実務教育とリンクする形で、マーケティングや経営戦略の議論に国際的な視点が加わるのが特徴です。また、商学部は実践教育に力を入れており、留学生と共に行うグループワークやプレゼンテーションを通じて、国境を越えた協働力を磨ける環境が整っています。専修大学自体が国際交流協定を多く結んでいるため、留学生を受け入れるだけでなく、自学部生の海外派遣とも連動し、双方向の国際交流が活発です。結果として、商学部で学ぶ学生にとっては留学生と日常的に関わることが、将来のビジネスフィールドで不可欠な異文化理解力や国際対応力の養成に直結しています。
海外提携校数
東洋大学経済学部が提携する海外大学の数は 259 校となっており、アジアや欧米の大学を中心に幅広いネットワークを形成しています。これにより、交換留学制度やダブルディグリー制度、短期語学研修など多彩なプログラムを提供しており、学生は在学中に海外での学修や生活を体験する機会を得られます。特に経済学の分野では国際的な研究や事例分析が不可欠であり、こうした提携先での学びは国際経済やグローバルビジネスへの理解を深める上で大きな強みとなります。また、大学としては英語だけでなく多言語での交流を奨励しており、留学先で得られる人脈や異文化理解は卒業後のキャリア形成にも直結しています。
専修大学商学部の海外提携校数は 36 校で、こちらもアジア・欧米に広がる多様な大学と協定を結んでいます。特に商学分野における実務的な教育と連動した留学制度が特徴であり、現地でのビジネスインターンシップやケーススタディを通じて、実践的に異文化ビジネス環境を体験することができます。さらに、海外からの派遣留学生と国内の学生が合同で学ぶプログラムも展開しており、専修大学の商学部で学ぶ学生は学内外を問わず国際的なビジネス感覚を養うことができます。提携校数は東洋大学と比べて大きな差はないものの、商学的な応用を重視した連携内容に特色があるといえます。
結局東洋大学経済学部と専修大学商学部のどちらが良いか

東洋大学経済学部と専修大学商学部を比較すると、それぞれに明確な特色が見られます。東洋大学は経済学に基盤を置きつつ、国際経済やグローバルな課題への学術的アプローチを重視しており、理論と分析力の養成に強みがあります。一方で専修大学は商学の応用力を重視し、ビジネス実務や経営現場を意識した教育体系を築いているのが特徴です。どちらも有名企業への就職実績や進学率において安定した水準を維持しており、他大学グループと比較しても一定の競争力を発揮しています。
進学率や国際性の観点では、両大学とも留学制度や海外大学との提携を通じて学生の可能性を広げていますが、東洋大学は経済学的な分析視点から、専修大学は実務的・応用的な商学教育を通じて、それぞれ異なる国際経験を提供しているといえます。どちらが上かは志望者の将来像に左右されやすく、理論重視で研究や公共政策などを目指すなら東洋大学経済学部が、ビジネス現場や企業活動に直結する力を培いたいなら専修大学商学部がオススメといえるでしょう。