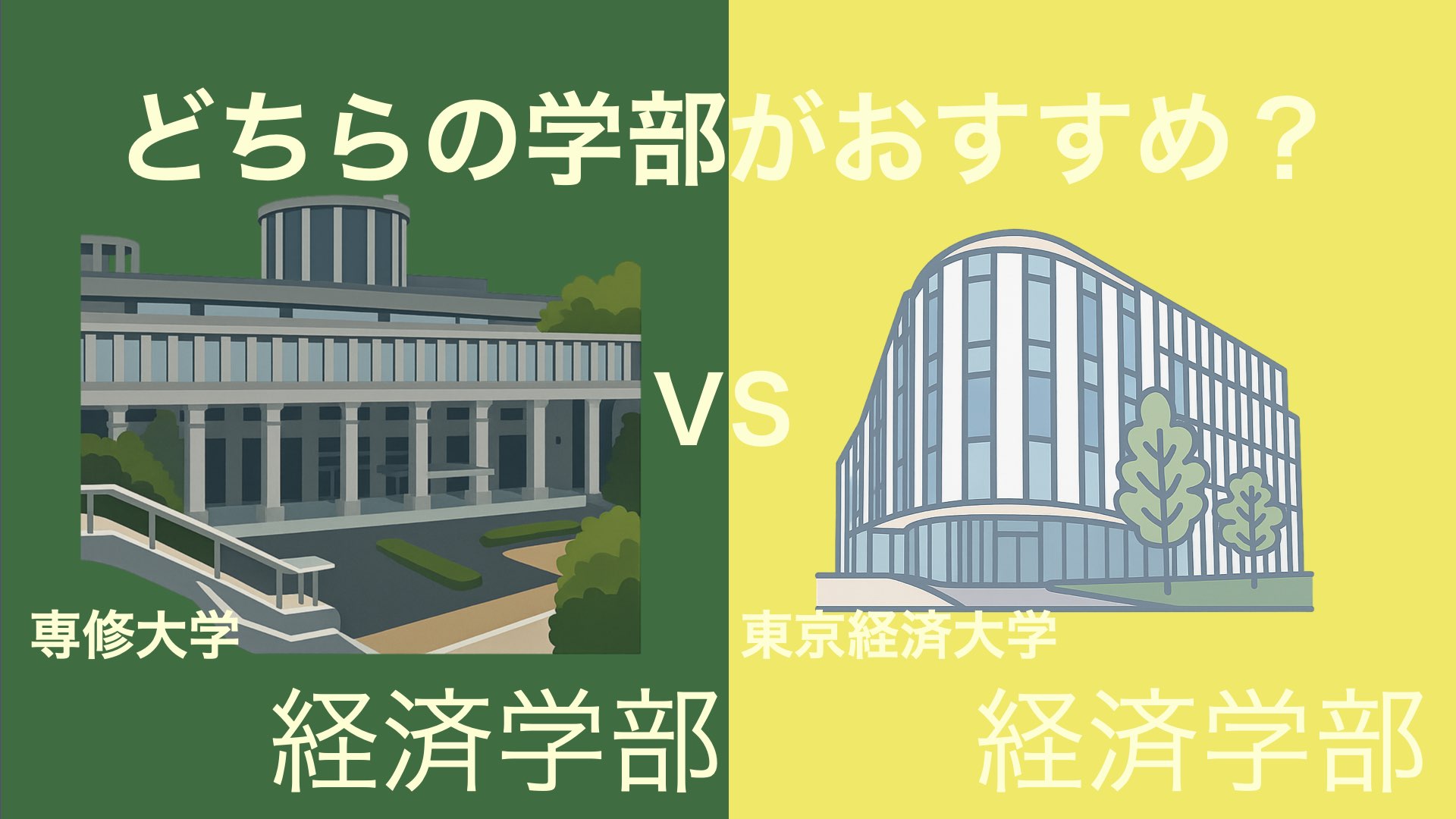専修大学経済学部と東京経済大学経済学部はどんな大学?

基本情報
| 項目 | 専修大学経済学部 | 東京経済大学経済学部 |
|---|---|---|
| 学部設立 | 1949年 | 1949年 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区東三田2-1-1(生田駅) | 東京都国分寺市南町1-7-34(国分寺駅) |
| 学部理念 | 経済的、社会的及び歴史的な諸事象を考察の対象とする専門的諸科学の研究成果を体系的に教授することにより、深い洞察力と高い批判力を備えた専門的教養を有する社会人及び職業人を養成する | 経済学部は、グローバル化の進展する経済社会における多様な諸問題を分析し、その解決に努め、以って国内外の様々な要請に応えて活躍できる、高度な専門的経済知識と倫理観を備えた良き市民、良き経済人を養成し、その基盤となる教育研究を推進する。 |
専修大学経済学部は、1949年に設立され、社会科学系学問の中でも特に経済学の教育・研究を重視して発展してきました。キャンパスは生田駅からアクセスでき、都市型の利便性を享受できる環境にあります。カリキュラムは経済理論を基盤としながら、統計・計量経済学や実証的研究に力を入れており、政策立案や企業活動の分析に役立つ実践力を養うことができます。さらにゼミ活動を通じて少人数教育が行われることで、理論と現実を結びつける力を培えるのが特徴です。専修大学の伝統的な経済教育は、多くの卒業生が金融業界や公務員分野で活躍する基盤を築いています。
東京経済大学経済学部は、1949年に設立され、経済学を中心とした社会科学教育を専門に据えて発展してきました。立地は国分寺駅から通学可能で、都市圏にありながら落ち着いた学習環境を持つ点が魅力です。カリキュラムはミクロ・マクロ経済学といった基礎理論に加え、現代社会に直結するフィールドワークや地域経済研究も取り入れており、実証的な教育姿勢が特徴です。少人数教育と学生主体の演習により、自ら考え議論する力を養うことに重点を置いています。さらに、企業や自治体との連携による課題解決型の学びも充実しており、社会と直結した実践的な学修を重視する傾向が強く見られます。
他の大学群と比べると、専修大学経済学部は日東駒専に属し、伝統ある大規模経済学部として知名度が高く、学修環境や卒業生ネットワークの厚みで安定感があります。一方、東京経済大学経済学部は規模としてはやや小規模ながらも、地域社会と連携した実践的教育やアットホームな環境を特徴とし、個別対応の手厚さが強みです。GMARCHと比較すると、偏差値やブランド力では劣る部分がありますが、費用対効果や教育内容の特色を重視すれば十分に魅力的な選択肢となります。どちらを選ぶかは、安定感を求めるか実践的な学びを重視するかによって異なるといえるでしょう。
大学の規模
専修大学経済学部の学生数は751名で、大学全体の中でも大きな規模を誇っています。人数が多いことは、多様なバックグラウンドを持つ学生が集まり、幅広い人脈を築ける点で強みとなります。また、規模の大きさはゼミや授業の選択肢の多さにも直結しており、経済学の専門分野を深める際に柔軟な進路選択が可能です。ただし、その分授業や課外活動において競争が激しくなる傾向があるため、学生自身の積極性が重要になるという側面も見られます。
東京経済大学経済学部の学生数は530名と、専修大学と比べると小規模です。規模が小さいことは、学生と教員の距離が近く、一人ひとりに対してきめ細やかな教育を受けやすいという利点につながります。講義やゼミでの発言機会も比較的多く、学習意欲が高い学生にとっては学びを深めやすい環境といえます。反面、学部全体でのネットワーク形成や多様な分野を横断的に学ぶ機会はやや限られる傾向があります。
他大学群と比べると、日東駒専に属する専修大学は学生数の多さが際立ち、教育リソースや学生活動の幅広さに強みがあります。東京経済大学は学生数が少ない分、密度の高い教育を特徴としており、これは小規模大学の利点といえます。GMARCHと比較すると、学生数や規模で劣るものの、両大学ともにアットホームな教育環境を武器として、学生に寄り添った学びを提供している点に特色があります。結果として、規模の大きな専修大学と、小規模ながら濃密な教育環境を持つ東京経済大学という対照的な魅力を備えています。
男女の比率
専修大学経済学部の男女比は75.4 : 24.6で、男子学生の割合がやや高めとなっています。経済学部は統計学や金融、公共政策など幅広い専門分野を扱うため、性別に関わらず進学者は多様ですが、依然として男子が中心となる傾向が強い学部です。男子比率の高さはゼミや学生活動における議論のスタイルや雰囲気に影響を与える場合があり、積極的で実務志向の学生が集まりやすいのが特徴です。
東京経済大学経済学部の男女比は81 : 19で、専修大学と比較すると男女のバランスが比較的均衡している点が特徴です。経済学部の中でも、社会経済や地域経済といった分野に関心を持つ女子学生が多く、学部全体として柔らかい雰囲気を持つのが利点です。また、男女比が均衡していることで、グループワークやゼミ活動で多様な視点が自然に反映され、議論が活発になりやすい点も教育環境の強みとなっています。
他大学群と比べると、日東駒専に位置づけられる専修大学は男子学生が多い傾向が強く、これは理論や実務を志向する進学者が多いことと関連しています。一方、小規模である東京経済大学は男女比のバランスが良く、地域社会や教育に密着した研究に女子学生が積極的に参加している点で特色があります。GMARCHクラスと比べると両大学とも規模で劣る部分はありますが、学生生活の中での性別構成の違いが教育や交流に独自の個性を与えているといえるでしょう。
初年度納入金
専修大学経済学部の初年度納入金は122.4万円であり、私立大学の経済系学部としては標準的な水準に位置しています。経済学部は講義中心の学修が多く、実験や特殊な設備を必要としないため、医学部や理工系学部に比べて学費は抑えられる傾向にあります。また、専修大学は奨学金制度や学費分納制度も充実させており、経済的な理由で進学をためらう学生にとっても学修を継続しやすい環境を整えています。
東京経済大学経済学部の初年度納入金は129.3万円で、専修大学よりやや低めの設定となっているのが特徴です。小規模な大学であるため管理費用を抑えていることが学費の低さに反映されています。さらに、地域社会に根差した教育方針を掲げており、通学圏内からの学生が多いこともあって生活コストを抑えながら学ぶことが可能です。その結果、経済的負担を軽減しつつ専門教育を受けられる点で魅力があります。
他大学群と比べると、日東駒専の経済系学部では初年度納入金が100万円台前半から中盤に集中しており、専修大学と東京経済大学はいずれもこのレンジに収まります。一方、GMARCHクラスの経済系学部ではやや高額になる傾向があり、授業料に加えてブランド力を背景にした学費設定が目立ちます。そうした観点から見ると、両大学は経済的負担を抑えたい層にとって現実的な選択肢であり、特に東京経済大学のコストパフォーマンスは相対的に優れていると評価できます。
SNSでの評価
専修大学経済学部のSNSでの評価は、比較的堅実で真面目な学風が支持されている一方、派手さやブランド力という点ではやや控えめであるという声が見られます。授業やゼミ活動に関しては、経済学の基礎から応用まで幅広く学べる点が評価され、特に資格取得や就職支援の取り組みはSNS上でもポジティブな反応を得ています。ただし、キャンパスの立地や交通アクセスについては賛否が分かれる傾向にあり、都心部に比べると利便性の面で劣るとの意見もあります。
東京経済大学経済学部のSNSでの評価は、アットホームで面倒見が良いという意見が多く、少人数教育や学生と教員の距離感が近い点が強調されています。経済学の基礎力養成に加えて実践的な授業が多いこともあり、地域社会や実務との結びつきを感じられるというコメントも目立ちます。その一方で、知名度や全国的なブランド力に関しては専修大学と比べても弱いという声があり、学生生活の満足度は高いが対外的な評価は課題として挙げられる傾向があります。
他大学群と比べると、日東駒専は全体的にブランド力の浸透度に差があり、SNSでの話題性も大学ごとに開きがあります。専修大学は日東駒専の中では比較的発信力があり、資格や就職に強いと評価されやすいのに対し、東京経済大学は小規模さを活かしたサポート力や学生生活の充実度で高評価を得ています。GMARCHと比較すると発信力や注目度では劣りますが、学びや環境面に関しては独自の強みがあると認識されている点が特徴です。
合格難易度(偏差値・倍率)

偏差値(マナビジョン)
専修大学経済学部の偏差値は57となっており、日東駒専グループの中でも標準的な位置にあります。経済学部は幅広い受験方式を設けており、学力試験に加えて総合型や推薦型選抜などで入学する学生も多いため、入学者の学力層は比較的多様です。専修大学全体の伝統や規模感もあり、受験生の層は安定しており、継続的に一定数の志願者を集めています。経済学の王道的なカリキュラムを展開していることもあり、進学先として安心感を持って選ばれるケースが多いのが特徴です。
東京経済大学経済学部の偏差値は58であり、専修大学と比較するとやや控えめな数値となっています。東京経済大学は少人数教育や面倒見の良さが評価される一方で、全国的な知名度やブランド力においては専修大学に比べて弱い面があります。そのため偏差値の面でも、難易度が比較的落ち着いており、受験生にとってはチャレンジしやすい学部といえるでしょう。地域性や大学の特色に惹かれる受験生を中心に志願される傾向が見られます。
他大学群と比べると、日東駒専の偏差値は全体的に55前後で安定しており、専修大学はグループ内でもやや高めの評価を得ています。一方、東京経済大学は日東駒専より下のカテゴリーとされることが多く、偏差値面では一歩譲る傾向があります。GMARCHと比較すると専修大学であっても差は大きく、難易度の観点からは日東駒専上位と下位私大の中間的な立ち位置にあるといえるでしょう。東京経済大学は偏差値面でさらに控えめですが、その分受験生が入りやすく、特色教育に注力している点で独自の価値を持っています。
倍率
専修大学経済学部の倍率は2.6倍となっており、日東駒専グループの中では標準的な水準に位置しています。専修大学は安定した志願者数を誇るため、極端に高い競争率になることは少ないですが、確実に合格するには偏差値だけでなく入試傾向を押さえた対策が必要です。経済学部は幅広い受験方式を持ち、一般選抜だけでなく推薦や総合型でも一定数を受け入れるため、多様なバックグラウンドの学生が集まりやすいのが特徴です。
東京経済大学経済学部の倍率は2.9倍で、専修大学と比較するとやや落ち着いた水準となっています。大学全体の規模や知名度の違いもあり、志願者が集中することは少なく、倍率としても安定的に推移しています。そのため、受験生にとっては過度な競争を避けて受験できるメリットがあり、地域性や少人数教育など大学の強みを求める受験層に適しています。
他大学群と比べると、日東駒専の入試倍率は概ね3倍前後で推移しており、専修大学はこの標準的な数値を反映しています。一方、東京経済大学は日東駒専より下に位置付けられることが多いため、倍率は全体的に低めに落ち着いています。GMARCHになると難易度の高さから倍率もやや上昇傾向を見せますが、専修大学は日東駒専上位として堅実に志願者を集めており、東京経済大学との差は「ブランド力」と「志願者層の厚み」に起因するといえます。
卒業後の進路

有名企業の就職率
専修大学経済学部の有名企業就職率は7.5%で、日東駒専の中でも平均的な数値を示しています。特に金融・保険業や公共系企業への就職が比較的安定しており、長年の卒業生ネットワークを活かした就職支援体制も整っています。経済学部の学生は幅広い分野に進むことが可能であり、資格取得やインターンシップ制度の利用によって大手企業への道を切り開く環境が整っている点が特徴です。
東京経済大学経済学部の有名企業就職率は6.8%となっており、専修大学と比較するとやや低めの傾向にあります。中堅企業や地域密着型の企業への就職が目立ち、大手企業への進出は限定的です。ただし、少人数教育の強みを活かして学生一人ひとりに対する就職支援が丁寧に行われているため、個々の希望に沿った進路を実現できる点に特徴があります。
他大学群と比べると、日東駒専の有名企業就職率は概ね10%前後で推移しており、専修大学はその中でやや高めの位置にあります。GMARCHの大学群になると20%前後まで上昇するため、専修大学との差は歴然ですが、日東駒専の中では比較的安定した就職実績を誇ります。東京経済大学はこの平均よりやや低い水準であり、ブランド力や企業認知度の面で差が出やすいといえます。
主な就職先
川崎市役所(5名)
富士ソフト(4名)
ニトリホールディングス(2名)
EY新日本有限責任監査法人(1名)
専修大学経済学部では上記の他に、地方銀行や証券会社などの金融業界、さらに流通やサービス業への就職者も多く見られます。公務員志望者も一定数おり、国家公務員や地方自治体への合格実績もあります。学部として幅広い進路支援を行っているため、学生は経済学の専門性を生かしつつ多様な分野でキャリアを築くことが可能です。
東京経済大学経済学部では上記の他に、中小企業や地域経済を支える企業への就職が多い傾向にあります。特に営業職や事務職など、安定的な職種に就く学生が目立ちます。また、教育関連企業や情報通信業界に進む学生も一定数存在しており、少人数教育を生かした個別支援により、学生の希望に沿った進路が開かれるのが特徴です。
他大学群と比べると、日東駒専の学生は大手企業に加えて地方銀行や中堅企業への就職が多く、専修大学はその中でも比較的安定した大手金融系への就職が見られます。一方、東京経済大学はやや地域密着型の傾向が強く、全国的な知名度を持つ大企業への進出は限定的です。GMARCHの学生は大手総合商社や外資系企業への就職例も多く、ここに大きな差があるといえます。
進学率
専修大学経済学部の進学率(2.2%)は、日東駒専の中では平均的な水準に位置しています。大学院進学者は少数派ではありますが、経済理論や公共政策、ファイナンス研究を志す学生が一定数存在し、国内外の大学院へ進むケースもあります。進学率自体はそれほど高くはありませんが、研究志向の学生には専修大学の指導環境が一定の評価を受けています。
東京経済大学経済学部の進学率(3.4%)は、全体的にやや低めです。大学院進学を選択する学生は限られており、卒業後は直ちに就職に向かう傾向が強いのが特徴です。ただし、研究志向を持つ学生については、経済学研究科を中心とした大学院進学支援が行われており、少数精鋭で学びを深める環境は整っています。
他大学群と比べると、日東駒専や東京経済大の学生は進学よりも就職を選ぶ傾向が顕著で、大学院進学率は一桁台にとどまることが多いです。一方で、GMARCHクラスの大学では大学院進学率がやや高く、特に経済学部では専門研究や学術キャリアを目指す学生が一定数存在します。この違いが教育環境の充実度や進路選択の幅の広さに直結しているといえます。
留学生

受け入れ状況
専修大学経済学部の留学生数(385名)は、全学的な取り組みの一環として一定の数を維持しています。学部としても国際交流を重視しており、短期交換留学や英語開講科目を通じて留学生と日本人学生が共に学ぶ機会を設けています。こうした環境は、国際経済や貿易、金融といった分野を学ぶ際にグローバルな視点を養う土壌となっています。
東京経済大学経済学部の留学生数(100名)は比較的少数ですが、授業やゼミに積極的に参加することが多く、学部全体に国際的な雰囲気をもたらしています。特にアジア圏からの留学生が多く、地域経済や国際ビジネスに関するディスカッションを通じて、学生同士が異なる視点を交換する機会が増えています。大学としても海外協定校との提携を活用し、双方の学生が交流できる仕組みを整備しています。
他大学群と比べると、日東駒専や東京経済大クラスでは留学生数は限定的ですが、少人数である分、交流の機会は密接で深い学びにつながる傾向があります。一方、GMARCHクラスでは留学生数が多く、より多様な国籍の学生が集まるため、広範な国際交流の場が整っている点で差が見られます。この違いは、学びの環境における国際色の濃さや学生の異文化理解力に影響を与えています。
海外提携校数
専修大学経済学部の海外提携校数(36校)は、比較的多様な国や地域に広がっており、学生にとって幅広い留学や短期派遣の選択肢を提供しています。特にアジアや欧米の協定校との交流が活発で、語学だけでなく経済や経営に直結する学問領域での学修機会が整っています。
東京経済大学経済学部の海外提携校数(47校)はやや限定的ですが、少数精鋭型の協定校を重視している傾向があります。特にアジア圏の大学とのつながりが強く、地域経済や国際関係を学ぶ場として活用されており、学生にとっては手厚いサポートの下で留学を実現できる仕組みが整っています。
他大学群と比べると、日東駒専クラスでは協定校の数に限りがあり、選択肢が狭まる場合があります。一方、GMARCHクラスでは数十校規模の提携を持つ大学もあり、欧米や新興国まで含めた幅広い留学先を選べる点で差が出ています。専修大学や東京経済大学のような大学では、派遣機会の数こそ限られるものの、個別の交流の濃さや学習支援の充実度で特色を打ち出しているといえるでしょう。
結局専修大学経済学部と東京経済大学経済学部のどちらが良いか

専修大学経済学部と東京経済大学経済学部は、ともに日本の私立大学として経済学教育を主軸に据えていますが、その規模やブランド力に違いがあります。専修大学は日東駒専の一角を占める大規模大学で、学生数や卒業生ネットワークが豊富であり、OB・OGの存在は就職活動における安心材料となります。一方、東京経済大学は小規模ながらも少人数教育を特徴とし、学生一人ひとりに対する指導が手厚い点が強みです。
有名企業就職率においては、専修大学が日東駒専水準の約10%前後に位置するのに対し、東京経済大学はやや低めの数値にとどまる傾向があります。これは大学規模やOBネットワークの差が背景にあり、特に大手企業を志望する場合には専修大学の方が優位に立つ場面が多いといえます。ただし、東京経済大学も地元志向の学生に対して中小企業や地域金融機関などへの就職実績を積み重ねており、進路選択に応じた支援体制を備えています。
他の大学群と比べると、GMARCHと比較した場合には両校とも有名企業就職率やブランド力で劣りますが、学費や学生規模を考慮するとコストパフォーマンスの良さが強みとなります。特に専修大学は全国的な知名度と豊富な学生数で選択肢を広げられる点が魅力であり、東京経済大学は少人数教育による学びやすさと地域密着型の進路支援が特徴です。進学先を選ぶ際には、全国規模でのキャリアを志向するか、地域での安定を重視するかで判断するのが適切でしょう。