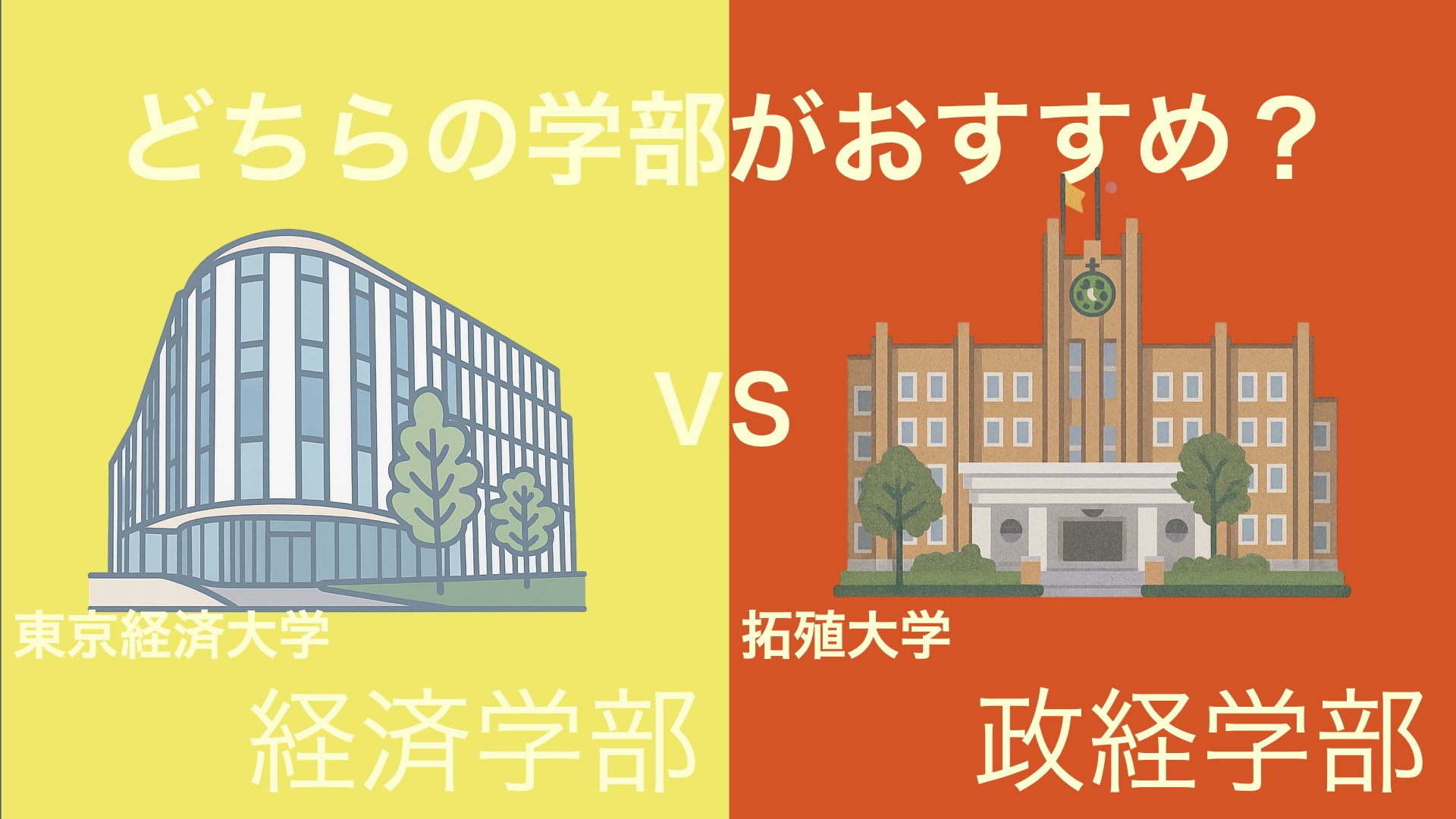東京経済大学経済学部と拓殖大学政経学部はどんな大学?

基本情報
| 項目 | 東京経済大学経済学部 | 拓殖大学政経学部 |
|---|---|---|
| 学部設立 | 1949年 | 1949年 |
| 所在地 | 東京都国分寺市南町1-7-34(国分寺駅) | 東京都文京区小日向3-4-14(茗荷谷駅) |
| 学部理念 | 経済学部は、グローバル化の進展する経済社会における多様な諸問題を分析し、その解決に努め、以って国内外の様々な要請に応えて活躍できる、高度な専門的経済知識と倫理観を備えた良き市民、良き経済人を養成し、その基盤となる教育研究を推進する。 | 法律学・政治学分野における理論的・実践的知識を身につけ、グローバル化時代の実社会の諸問題を的確に指摘し、解決できる能力と意欲を持った人材を育成する。 |
東京経済大学経済学部は、1949年の設立以来、実学重視の教育理念を継承しながら、経済の理論と実践を結びつけたカリキュラムを展開しています。キャンパスは国分寺駅から徒歩圏内にあり、閑静で落ち着いた学習環境が整っています。学生一人ひとりが主体的に学べるよう少人数教育を重視し、ゼミ活動も活発です。実社会と連携した講義や地域経済の分析など、実務的な経済教育を受けられる点も特色です。文系中心の大学でありながら、経済データ分析や政策評価など定量的な視点も育成しています。
拓殖大学政経学部は、1900年の東亜同文書院を母体とする拓殖大学の伝統を引き継ぎ、戦後に現在の学部体制を確立しました。文京区の文京キャンパスに位置し、都心部へのアクセスが良好です。学問的には経済学と政治学の両軸から社会を分析し、グローバル視点を持つ人材の育成を目指しています。特にアジア研究や国際経済分野に強みがあり、海外との交流プログラムも積極的に展開しています。実務的な国際理解と社会科学的な洞察の両立を重視するのが特色です。
他大学群と比べると、東京経済大学は「大東亜帝国」よりやや上位に位置する偏差値58程度で、安定した教育と実務重視の姿勢が特徴です。一方、拓殖大学政経学部は偏差値47で「大東亜帝国」クラスに相当し、特に国際分野の教育力に定評があります。どちらも中堅私大として堅実な学びを提供しています。
大学の規模
東京経済大学経済学部の学生数は530名で、学部としては中規模の構成となっています。少人数教育を重視する方針から、教員との距離が近く、ゼミや演習科目での対話型授業が活発です。授業やキャリア支援においても個々の学生に目が行き届く規模感であり、学習面・進路面のサポート体制が整っています。また、キャンパス全体でもアットホームな雰囲気があり、落ち着いた学習環境の中で専門性を磨くことが可能です。
拓殖大学政経学部の学生数は853名で、全学的に見ても比較的大きな規模を有しています。学生数の多さを活かし、学内では多様なバックグラウンドを持つ学生同士の交流が盛んです。授業も講義型から少人数演習まで幅広く、学部内で複数の専門分野を横断的に学べるのが特徴です。また、留学生との交流も多く、国際的な視野を養う教育環境が整っています。
他の大学群と比べると、両校とも「日東駒専」よりややコンパクトな規模に位置します。東京経済大学は学生一人ひとりへのサポートに強みを持ち、拓殖大学は学生数を活かした多様な学びと交流が可能です。どちらを選ぶかは、個別支援を重視するか、幅広い交流を求めるかによって異なるでしょう。
男女の比率
東京経済大学経済学部の男女比は81 : 19で、男子学生が大きく上回る構成となっています。経済学部としての性質上、実証分析や経営系科目に関心を持つ男子学生の志願が多い傾向がありますが、近年は女性の進学者も徐々に増加しています。女子学生の比率が低めである分、少人数でのゼミやキャリア支援では、教員からきめ細かな指導を受けやすい環境といえるでしょう。
拓殖大学政経学部の男女比は78 : 22で、こちらも男子学生の比率が高めです。政治・経済・国際関係といった社会科学系分野では、男性志願者が多く集まる傾向があります。一方で、国際系科目や語学教育の充実によって女性の進学者も一定数を占め、学内では男女のバランスを意識したグループワークや異文化理解教育が行われています。
他の大学群と比べると、両校とも男子比率が高めであり、特に経済・経営分野を志す層に多くの支持を得ています。女性比率が高い文系学部に比べるとやや偏りはあるものの、どちらの大学も近年は多様な学生層の受け入れを進めており、男女を問わず活躍できる環境づくりが進んでいます。
初年度納入金
東京経済大学経済学部の初年度納入金は129.3万円です。私立経済系学部としては比較的標準的な水準であり、授業料とともに施設設備費なども含まれています。経済的な負担を抑えたい学生向けには独自の奨学金制度も整っており、学業成績や経済状況に応じて支援が受けられる点も特徴です。キャンパスの立地や施設環境を考慮すると、コストパフォーマンスの高い大学といえるでしょう。
拓殖大学政経学部の初年度納入金は131万円で、同規模の私立大学の中でもやや低めの水準です。特に政経系の学部では学費の安定性が重視される傾向があり、拓殖大学では長期的な学費支援制度が複数用意されています。また、留学プログラムや資格取得支援に追加費用が発生することもありますが、全体としては堅実で通いやすい学費設定といえます。
他の大学群と比べると、両校とも「日東駒専」や「大東亜帝国」といった中堅私大の平均的な学費帯に位置しています。東京経済大学はコストに対する教育の質で評価が高く、拓殖大学は学費の安さと留学支援の充実が特徴です。経済的な視点から見ると、いずれも現実的な選択肢といえるでしょう。
SNSでの評価
東京経済大学経済学部のSNSでの評価を見ると、「落ち着いた雰囲気」「先生との距離が近い」「ゼミが充実している」といったポジティブな声が目立ちます。学生数が多すぎないため、学内での人間関係が比較的穏やかで、学業に集中しやすい環境が支持されています。一方で、「地味」「知名度がやや低い」といった意見も散見されますが、実直な校風を好む層からは堅実な評価を得ています。SNS上では、勉強やキャリア形成を地道に進めたい学生に向いている大学として語られることが多いです。
拓殖大学政経学部に関するSNSでの評価は、「国際的」「留学生が多く刺激的」「雰囲気が明るい」といった印象が強く、グローバル志向の学生層に人気があります。反面、「課題が多い」「やや通学が大変」といった現実的な意見も見られます。特に海外に関心を持つ学生や語学に強みを持つ層からは前向きな意見が多く、国際的な交流環境を魅力として挙げる投稿が目立ちます。
他の大学群と比べると、東京経済大学は「真面目で実務志向」、拓殖大学は「明るく国際的」という評価軸で語られることが多いです。いずれも派手さはないものの、堅実さや実学志向という面で中堅私大の中でも安定した支持を得ている点が特徴です。
合格難易度(偏差値・倍率)

偏差値(マナビジョン)
東京経済大学経済学部の偏差値は58で、日東駒専クラスとほぼ同程度のレベルに位置しています。経済学部としての伝統があり、近年は実学的な授業内容や少人数教育が評価され、偏差値は安定して推移しています。入試方式も多様化しており、共通テスト利用型から一般選抜まで幅広い受験層を受け入れている点も特徴です。堅実で学業重視の学生が集まりやすく、派手さよりも着実な学びを志向する傾向があります。
拓殖大学政経学部の偏差値は47で、全体としては大東亜帝国クラスに近い水準です。偏差値帯としては中堅私立大学の中でも下位から中位に位置しますが、国際系科目や実務科目の人気が高まりつつあり、特定分野では上昇傾向を見せています。入試難易度は比較的穏やかであり、幅広い学力層の学生が進学しやすい環境です。
他の大学群と比べると、東京経済大学は日東駒専と同等の学力帯に属し、学問的にも安定感があります。一方、拓殖大学は大東亜帝国クラスの中では上位に位置しており、国際志向の学生を中心に支持されています。両校とも中堅私大として現実的な入学ラインにあり、学びの方向性によって選択が分かれるといえるでしょう。
倍率
東京経済大学経済学部の倍率(競争率)は2.9倍です。私立中堅大学としては平均的な水準にあり、共通テスト利用方式や一般選抜を含めると、やや倍率に幅があるのが特徴です。特に一般選抜では安定した受験者数を保ち、人気のゼミやコースでは倍率が高くなる傾向があります。堅実な学風と立地の良さもあり、毎年安定的に受験生の支持を集めています。
拓殖大学政経学部の倍率は1.6倍で、比較的落ち着いた水準となっています。入試方式の多様化により、受験生が自分の得意分野を活かして挑戦できる点が魅力です。国際系科目の人気が高いため一部で競争率が上昇するものの、全体としては受けやすい大学に分類されます。入試難易度のわりに実践的な教育が受けられることも評価されています。
他の大学群と比べると、東京経済大学は日東駒専クラスの中でも堅実な競争率を維持しており、一定の人気を誇ります。拓殖大学は大東亜帝国クラスに位置しつつも国際色の強い特色で志願者を集めています。全体として両校とも無理なく受験を検討できる現実的な難易度といえるでしょう。
卒業後の進路

有名企業の就職率
東京経済大学経済学部の有名企業就職率は6.8%です。全国平均と比較すると中堅私大として標準的な水準にあり、特に金融・保険業界や流通系企業への就職に強みがあります。ゼミ活動やキャリア支援が充実しており、実務に即した学びを通じて安定した就職実績を維持しています。地味ながらも堅実な就職力が評価されており、就職支援センターの個別指導が学生から高い満足度を得ています。
拓殖大学政経学部の有名企業就職率は3.9%で、非公開データである点が特徴です。これは就職実績の集計が十分に行われていないためとみられ、対外的に誇れる数値がまだ整っていないことを示唆します。もっとも、独自の海外ネットワークや企業との連携講座を活かし、グローバル系企業への就職を志す学生にとっては魅力的な環境が整っています。
他の大学群と比べると、東京経済大学は日東駒専クラスの中でも堅実な就職力を持つ一方で、拓殖大学は大東亜帝国クラスの中でも国際志向を重視する独自のキャリア支援を展開しています。全体として、国内志向なら東京経済大学、海外志向なら拓殖大学という構図が見られます。
主な就職先
ニトリホールディングス(2名)
EY新日本有限責任監査法人(1名)
東京特別区(3名)
東京国税局(1名)
東京経済大学経済学部では、上記のような実績に加え、金融業界・保険業界・流通業界を中心に安定した就職先が目立ちます。特に地方銀行、損害保険会社、総合商社系のグループ企業などへの就職が多く、堅実なキャリア形成を目指す学生に支持されています。さらに、公務員志向の学生も一定数おり、専門講座や学内セミナーが充実している点も強みです。少人数教育による教員のフォローも厚く、キャリア形成の基盤が整っています。
拓殖大学政経学部では、商社・物流・観光業界など、グローバル志向の学生に対応した就職が目立ちます。特に海外展開を行う企業や、語学力を活かせる職種への進出が特徴で、大学の国際的なネットワークが活かされています。また、OB・OGのつながりも強く、外資系企業や航空関連業界などへの就職も少なくありません。学生の多様な志向を尊重し、キャリア支援センターが個別に対応しています。
他の大学群と比べると、東京経済大学は日東駒専クラスの中で安定した就職先を確保する実績があり、堅実なキャリアを志向する学生に適しています。一方で、拓殖大学は大東亜帝国クラスの中でも国際系・外資系などの就職に特色を持ちます。両校ともキャリア支援体制は充実していますが、目指す業界によって選択が分かれる傾向があるといえるでしょう。
進学率
東京経済大学経済学部の進学率は3.4%です。経済学をより深く探究したい学生が少数ながら大学院へ進学しており、主に経済政策や会計・ファイナンス領域を研究対象とする傾向があります。ただし、同学部の大多数は就職志向が強く、大学院進学者は例年ごく限られた割合にとどまります。進学希望者に対しては研究指導や推薦制度が整っており、学問的な環境も一定の水準を保っています。
拓殖大学政経学部の進学率は3.8%で、全体的には低い水準にあります。大学院進学よりも実務的な就職を選ぶ学生が多く、政治・経済の専門知識を社会で活かすキャリア形成を重視する傾向が強いです。ただし、一部の学生は他大学院や海外大学への進学も見られ、語学力や国際関係の研究を志す学生が中心となっています。
他の大学群と比べると、東京経済大学は日東駒専クラスの中でも平均的な進学率であり、研究志向よりも実務重視の傾向が明確です。拓殖大学は大東亜帝国クラスの中でも特に就職志向が強く、大学院進学率はやや低めです。両校とも、進学よりも社会での即戦力育成を重視している点で共通しています。
留学生

受け入れ状況
東京経済大学の留学生数は100名です。全体の中では比較的控えめな規模ですが、アジア諸国を中心に一定数の留学生を受け入れています。授業の一部では英語による科目が設けられており、日本語教育支援も整っているため、外国人学生が学びやすい環境が整っています。多文化交流を促すイベントも開催され、キャンパス内での国際的な雰囲気づくりに貢献しています。
拓殖大学政経学部の留学生数は1315名で、これは中堅私大の中でも比較的多い水準にあります。特にアジアや中東からの留学生が多く、国際大学としての長い歴史を背景に、留学生支援体制が非常に充実しています。日本語教育センターを併設し、入学前からの学習サポートを行っている点も特徴的です。
他の大学群と比べると、東京経済大学は日東駒専クラスの中で国際化を地道に進めるタイプであり、規模よりも学びの質を重視しています。一方、拓殖大学は大東亜帝国クラスの中でも留学生数の多さが際立っており、国際色豊かな学習環境を提供しています。国際交流を重視するなら拓殖大学、落ち着いた環境で学びたいなら東京経済大学が適しているでしょう。
海外提携校数
東京経済大学の海外提携校数は47校です。提携先はアジア、欧米を中心に幅広く、学生交換や短期留学プログラムが充実しています。特にオーストラリアや韓国、中国の大学との関係が強く、語学研修や現地インターンシップを通して実践的な学びが可能です。また、少人数での派遣制度も整っており、初めて海外に挑戦する学生でも安心して参加できる体制が整っています。
拓殖大学政経学部の海外提携校数は56校で、東京経済大学を上回る規模の国際ネットワークを持っています。長年にわたりアジア諸国との教育交流を続けており、交換留学や国際共同研究の機会も多く提供されています。特に中国・韓国・タイなど東アジア圏の大学との結びつきが強く、政治・経済分野における国際的視点を磨く環境が整っています。
他の大学群と比べると、東京経済大学は日東駒専クラスの中でバランスの取れた国際連携体制を持ち、質の高い交流を重視する傾向があります。一方で拓殖大学は大東亜帝国クラスの中でも提携校数の多さが特徴的で、実践的な国際経験を積みたい学生にとって魅力的な環境です。留学先の選択肢を重視するなら拓殖大学、少人数での丁寧な支援を求めるなら東京経済大学が適しています。
結局東京経済大学経済学部と拓殖大学政経学部のどちらが良いか

東京経済大学経済学部は、偏差値58、有名企業就職率6.8%、進学率3.4%と、日東駒専に近い水準を維持しています。実践的な経済教育と地域社会との連携を重視しており、少人数教育による手厚い指導体制が魅力です。留学生数100名、海外提携校47校と、国際交流も着実に拡大しており、堅実な私大として安定した評価を得ています。
拓殖大学政経学部は、偏差値47、有名企業就職率3.9%、進学率3.8%と、全体的に大東亜帝国クラスの中で平均的な位置にあります。就職実績よりも国際教育への注力が顕著で、留学生数1315名、海外提携校56校と、国際色の強さが特徴です。グローバル志向の学生には魅力的な環境といえるでしょう。
両大学を比較すると、東京経済大学は学業面・就職面ともに堅実で、日東駒専に近い立ち位置を確立しています。一方で拓殖大学は国際教育を軸に発展しており、特に留学生受け入れ体制と提携校ネットワークでは優位性があります。総合的に見て、安定した学習環境と就職力を求めるなら東京経済大学、国際的な経験や語学力を重視するなら拓殖大学がオススメです。