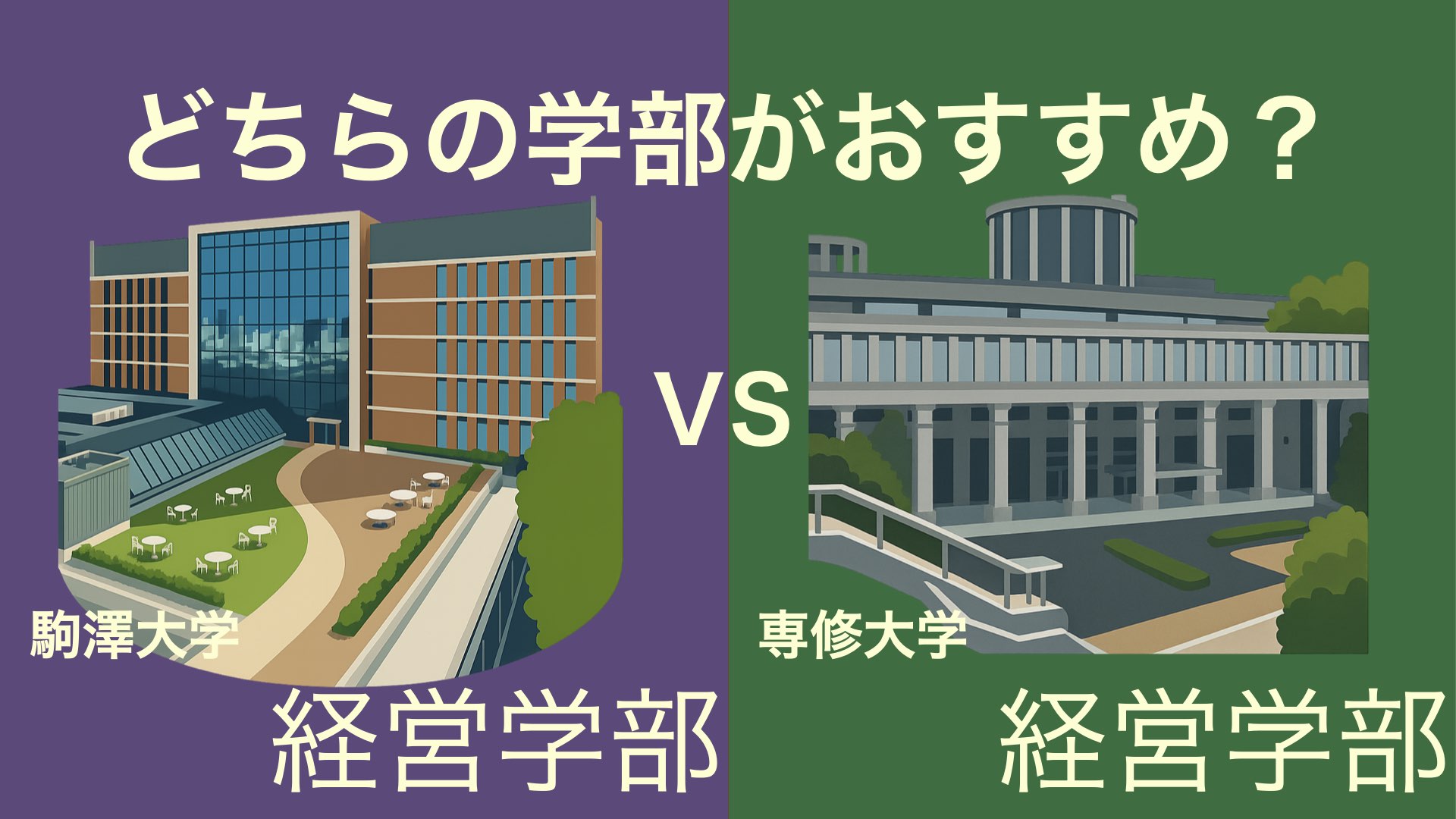駒澤大学経営学部と専修大学経営学部はどんな大学?

基本情報
| 項目 | 駒澤大学経営学部 | 専修大学経営学部 |
|---|---|---|
| 学部設立 | 1969年 | 1962年 |
| 所在地 | 東京都世田谷区駒沢1-23-1(駒沢大学駅) | 神奈川県川崎市多摩区東三田2-1-1(生田駅) |
| 学部理念 | 環境変化に直面する企業や社会において、情報を収集・分析・統合しつつ、自ら課題を発見し、適切かつ迅速に解決できる人材を養成する。そのために、経営に関わる理論的・実践的研究の深い知識、仏教と禅による人間観とグローバルな視野による広い教養を礎に、合理的な分析とチームによる問題解決を実践できる能力を陶冶する。 | 経営学部は、経営学を構成する複数の学問領域を研究・教育することにより、経営に関わる諸問題に対する洞察力を有し、問題を解決する手段を創造的に考察し、その解決に向けて自主的に行動することができる人材を養成することを目的とする。 |
駒澤大学経営学部は、1969年に設立され、都心からアクセスの良い駒沢大学駅にキャンパスを構えています。仏教系大学としての伝統を背景に、人間教育と実学の融合を重視し、特に経営理論と実務のバランスを意識したカリキュラムを整備しています。学生は、会計・マーケティング・経営戦略といった専門領域を学びつつ、ゼミ活動や学外実習を通じて現場感覚を養うことができます。また、地域や企業との連携講座も盛んで、現代社会で求められる経営スキルを実践的に磨ける点が魅力となっています。
専修大学経営学部は、1962年に設立され、生田駅に位置する神田キャンパスを中心に教育を展開しています。長い歴史を持つ大学の中でも商学・経営分野の教育に強みを発揮しており、実学主義の伝統を現代的な経営学に応用しています。カリキュラムは経営戦略・国際経営・会計・ファイナンスなど多岐にわたり、実務家教員による授業や企業との共同研究が多く行われています。また、立地の利便性を活かし、企業インターンシップや外部イベントへの参加機会が豊富で、都市型大学ならではの強みを発揮しています。
他の大学群と比べると、駒澤大学経営学部は日東駒専の中で堅実な教育を提供している一方、専修大学経営学部は歴史的な実学教育の積み重ねから「経営に強い専修」としての評価を確立しています。GMARCHと比較すると両校ともに全国的知名度や研究水準では一歩劣る部分もありますが、日東駒専グループ内では安定した人気を誇ります。特に専修大学は立地条件や実務教育に強みを持つため、経営分野での実践力を重視する受験生にとってはより魅力的に映る傾向があります。
大学の規模
駒澤大学経営学部の学生数(535名)は、日東駒専の中でも標準的な規模に位置しています。中規模であることで、学生と教員の距離が近く、ゼミや授業での発言機会も多いのが特徴です。経営学部としては、学科ごとに専門分野が整備されており、個々の学生が自分の興味に沿った分野を深めやすい環境があります。また、クラブ活動や課外活動も盛んで、学生生活を通じた人間関係の広がりも期待できる点が魅力となっています。
専修大学経営学部の学生数(553名)は、駒澤大学よりもやや大規模で、日東駒専の中でも比較的多くの学生を抱えています。そのため、幅広いカリキュラムや選択科目が整っており、経営分野の学習機会は多様です。一方で大人数ならではの競争意識が高まりやすく、ゼミ配属や資格取得においては主体的に行動する姿勢が求められます。多様な学生が集まることでネットワーク形成の幅が広く、卒業後のキャリアに直結する人脈作りにもつながります。
他の大学群と比べると、日東駒専グループ全体では1学部あたり数千人規模の学生を抱えるケースが多く、専修大学の経営学部はその中でも比較的大きめの学部に分類されます。駒澤大学はやや小規模でアットホームな環境を持つ一方、専修大学は大規模ならではの選択肢や学習機会の豊富さを提供している点が強みです。GMARCHの大規模学部に比べると規模はやや劣りますが、学生数の多さが学部の活動や教育の多様性を支えていることは両校に共通しています。
男女の比率
駒澤大学経営学部の男女比(61.4 : 38.6)は、経営学という分野の特性から男性学生がやや多い傾向がありますが、近年は女性の進学も増加しており、男女比は年々バランスが改善されつつあります。マーケティングや会計分野に関心を持つ女子学生が多く、ゼミや実習でも男女が協働する場が豊富にあります。男女の構成が多様化することで、学びの場における視点が広がり、経営学の実践的理解にも良い影響を与えています。
専修大学経営学部の男女比(66.2 : 33.8)もまた男性が中心ですが、女子学生の割合は比較的高めで、特に国際経営やサービス産業関連の学習に女性の関心が集まっています。授業やゼミでは男女が均等に活躍できる環境が整い、学内活動においても多様な学生が参加しています。このような性別の多様性は、経営学部の学びに不可欠な「多角的な視点」を強化し、将来の職業選択にも幅を与える要因となっています。
他の大学群と比べると、日東駒専の経済・経営系学部では依然として男性比率が高めに推移していますが、専修大学は女子学生の比率が比較的高い点で特徴的です。GMARCHの大規模経営系学部ではさらに女性の割合が増えており、ジェンダーバランスの改善が進んでいます。駒澤大学は伝統的に男性が多い傾向を持ちながらも、徐々に女子学生の進学が増えており、全体的には日東駒専の中で平均的な位置にあります。
初年度納入金
駒澤大学経営学部の初年度納入金(125.0万円)は、日東駒専グループの中でも標準的な水準に位置しています。授業料や施設費、実習関連費用などを含む総額は、学生や家庭にとって負担が大きすぎないよう設計されています。学内には奨学金制度や分納制度も整備されており、経済的背景を問わず学びやすい環境が提供されています。また、キャンパスの立地は通学利便性に優れているため、学費に加えて生活費や通学費を含めた総合的な負担も比較的抑えやすいのが特徴です。
専修大学経営学部の初年度納入金(122.6万円)も、私立大学としては平均的な水準であり、同じく日東駒専に属する大学群とほぼ同等の額となっています。専修大学では、授業料のほかに学部特有の演習費や教材費がかかる場合がありますが、奨学金や学費サポート制度が幅広く利用可能で、多様な家庭状況に対応しています。また、専修大学は都心部にキャンパスを構えており、交通の利便性やキャンパス設備の充実度を考慮すると、学費に見合った学修環境を提供しているといえます。
他の大学群と比べると、日東駒専の経済・経営系学部の初年度納入金はおおむね同水準で、100万円前後に収まるのが一般的です。一方、GMARCHの大学群になると学費はやや高めに設定される傾向があります。駒澤大学と専修大学は同じ日東駒専に属するため大きな差はなく、学費面だけでは優劣をつけにくいのが実情です。そのため、両校を比較する際には学費そのものよりも教育環境や立地条件、サポート制度の充実度に着目することが重要となります。
SNSでの評価
駒澤大学経営学部のSNSでの評価は、学生生活やゼミ活動の充実度に関する投稿が目立ちます。特に、少人数制で教員や仲間との距離が近い点はポジティブに評価されています。一方で、経営学部の専門性を高めるために資格取得やインターンシップに励む学生も多く、自己成長の機会が豊富だと発信されています。ただし、キャンパスが混雑気味であることや課題の多さについては改善を望む声も散見され、現実的な側面も共有されています。
専修大学経営学部に関しては、都心に位置する利便性や実践的な授業への満足度がSNS上で多く語られています。グループワークや発表の機会が豊富で、学生が主体的に学べる環境であると評価されています。加えて、学部独自のキャリア支援制度や就職活動に役立つセミナーも高く評価される一方、通学の混雑やキャンパスの施設面でやや不満を感じる学生の声も確認できます。全体としては、学習環境や進路サポートに強みがあると考えられています。
他の大学群と比べると、日東駒専に属する大学は総じてSNS上で「アットホームさ」「学生生活の充実度」が評価されやすい傾向にあります。一方、GMARCHになると「学問的権威性」や「ブランド力」に関する話題が増えるため、同じ学びであっても注目される点に違いが見られます。駒澤大学と専修大学はいずれも日東駒専に属しており、SNS評価のトーンは学生生活や身近な成長機会に焦点があてられる点で共通しており、両校の差はそれほど大きくないといえます。
合格難易度(偏差値・倍率)

偏差値(マナビジョン)
駒澤大学経営学部の偏差値は 60 です。日東駒専グループに属する学部としては標準的な水準であり、特に経営学やマーケティングを学びたい受験生から根強い支持を得ています。授業では実務的な科目や演習も多く取り入れられ、専門性を深めやすい環境が整っている点が特徴です。偏差値が安定していることは、学部の知名度や就職実績が受験生に一定の安心感を与えている証拠といえます。
専修大学経営学部の偏差値は 57 で、駒澤大学経営学部と近い水準に位置しています。専修大学もまた日東駒専の一角として、経営学を中心にした教育に力を入れており、安定的な人気を集めています。経営戦略や会計分野など、幅広い領域をカバーしているため、将来の進路に直結する学びを求める受験生にとっては魅力的です。偏差値の安定は大学全体の伝統や就職支援体制が評価されていることに起因しています。
他の大学群と比べると、日東駒専の経営学部は総じて偏差値が60未満で安定する傾向にあり、難関とされるGMARCHの経営学部と比較すると若干低めの位置づけになります。しかし、日東駒専は中堅私大として知名度が高く、就職や資格取得での支援体制も整っているため、実践的な学びを重視する層にとっては堅実な選択肢となっています。駒澤大学と専修大学はその中でも比較的安定した人気を誇り、偏差値の面で大きな差は見られません。
倍率
駒澤大学経営学部の倍率(3.7倍)は、ここ数年大きな変動はなく安定しています。日東駒専に属する学部として、知名度や就職実績に裏打ちされた堅実な人気を誇り、毎年一定数以上の志願者を集めています。倍率が安定していることは、入試制度や受験生の層が固定化している傾向を示しており、大学全体として受験生からの信頼を得ている証といえます。
専修大学経営学部の倍率(3.9倍)も同様に安定しており、駒澤大学と比べても大きな差は見られません。経営分野の学びを志向する受験生にとって、両大学とも日東駒専の中核学部として広く認知されており、志願者が毎年一定数確保されています。倍率が落ち着いていることで、過度な競争を避けつつも、安定した入学難易度を維持しているのが特徴です。
他の大学群と比べると、日東駒専の経営学部の倍率は概ね2倍前後で安定しており、GMARCHの経営学部と比較すると低めの水準にあります。ただし、倍率が低いからといって魅力が劣るわけではなく、教育内容や就職実績を重視する受験生にとっては依然として価値の高い選択肢です。駒澤大学と専修大学は、倍率の安定感という点で共通しており、受験生にとっては安心感のある出願先となっています。
卒業後の進路

有名企業の就職率
駒澤大学経営学部の有名企業就職率(7.8%)は、日東駒専グループの中では平均的な水準に位置しており、安定した実績を残しています。特に金融業界や流通・サービス業など、首都圏での就職機会が豊富である点が強みで、多様な企業への進路を確保しています。安定した就職実績は、大学の長い歴史や卒業生ネットワークに支えられています。
専修大学経営学部の有名企業就職率(7.5%)も同程度の水準で、駒澤大学と大きな差は見られません。特に経営学の専門性を活かせる業界への就職に強く、企業との産学連携やキャリア支援プログラムを積極的に展開している点が特徴です。学生は幅広い業界に挑戦できる環境を持ち、社会に出てからも安定したキャリア形成につながっています。
他の大学群と比べると、日東駒専全体の有名企業就職率は10%前後にとどまるのに対し、GMARCHでは20%前後と高い水準を誇ります。そのため、両学部はトップ大学群には及ばないものの、安定した就職力を備えている点で受験生にとって現実的な進路選択肢となっています。駒澤大学と専修大学の差は小さく、いずれも堅実なキャリア形成を目指す学生に適しています。
主な就職先
株式会社大塚商会(5名)
警視庁(4名)
レバレジーズ(3名)
船井総合研究所(3名)
駒澤大学経営学部では、上記の就職率の水準を背景に、金融業界、製造業、流通・小売業といった幅広い業種への進出が目立ちます。特に東京都内や首都圏に強い立地条件を活かし、大手銀行や証券会社、総合商社といった堅実な就職先を獲得する学生も多いのが特徴です。また、OB・OGネットワークの存在が就職活動において一定の支援力を発揮しており、キャリア形成に直結する実績を重ねています。
専修大学経営学部では、経営やマーケティングを学んだ知識を活かせる業種への就職が強みです。具体的には情報通信業やサービス業、さらには広告代理店やメーカーといった分野に進出する学生が多く見られます。大学としても産学連携プログラムを積極的に導入しており、実務に近い経験を積んだ学生が企業から高く評価される傾向があります。キャリアサポートセンターも充実しており、学生一人ひとりが自らの強みを発揮しやすい環境です。
他大学群と比べると、日東駒専全体は就職先の幅広さに特徴があり、安定した進路選択が可能です。これに対し、GMARCH以上の大学群では大手企業や中央省庁といった難関就職先への実績が豊富で、選択肢の「質」の面で差が見られます。しかし駒澤大学と専修大学はいずれも学生数の規模や立地を活かし、幅広い業種で堅実な就職を実現できる点で、将来を現実的に考える受験生にとって信頼性の高い学部といえます。
進学率
駒澤大学経営学部の進学率(1.2%)は、学部全体としては比較的低めですが、経営学の学びをより深めるために大学院進学を選ぶ学生も一定数存在します。特に会計学や経営戦略を専門的に研究したい層が進学を志向しており、公認会計士試験や税理士試験の準備と並行して大学院を活用するケースが見られます。ただし、進学する割合はあくまで少数派であり、多くの学生は企業への直接就職を選んでいます。
専修大学経営学部の進学率(1.2%)も同様に全体的には低い傾向にありますが、大学院への進学希望者は年々微増しています。特にマーケティングや国際ビジネス分野を研究対象とする学生が、修士課程でさらに専門性を高めるケースがあり、これらは海外志向の学生や研究職を視野に入れる学生に多いです。ただし、専修大学でも就職に直結するカリキュラムが充実しているため、進学を選ぶ学生は全体のごく一部にとどまっています。
他大学群と比べると、日東駒専レベルでは全体的に進学率は低めであり、就職を第一志望とする学生が大多数を占めています。一方で、経済学部は比較的大学院進学を選ぶ割合が高く、理論研究を重視する学生層が一定数存在します。これに対し、経営学部では実務志向が強いため進学率はさらに低い傾向にあります。GMARCH以上の大学群では、研究志向や海外大学院への進学者も目立ち、進学率の高さで差を見せています。
留学生

受け入れ状況
駒澤大学経営学部の留学生数(100名)は多くはないものの、アジア圏を中心に一定数の留学生を受け入れており、ゼミやグループワークにおいて異文化交流の機会を提供しています。経営学の分野は実務的要素が強く、留学生と共に取り組むことで国際ビジネスの視点を学ぶ場となっています。教育環境としては、英語での講義や異文化交流プログラムが徐々に充実しており、国際的な実務能力を養うことが可能です。
専修大学経営学部の留学生数(385名)は駒澤大学よりも多めであり、国際交流に積極的な姿勢が伺えます。特に中国や韓国を中心とするアジア諸国からの留学生が多く、授業や課外活動における交流は学生にとって実践的な国際経験となります。専修大学は協定校との交換留学制度を整えているため、留学生の存在はキャンパス全体の国際性を高める役割を果たしています。
他大学群と比べると、日東駒専レベルの大学では留学生の受け入れは年々増加しているものの、全体的には数十名から百名程度にとどまることが多いです。GMARCH以上の大学群では留学生数が大幅に多く、英語開講科目や国際寮の整備などが進んでおり、国際性において明確な差を見せています。そのため、駒澤大学・専修大学ともに一定の国際交流の機会はあるものの、他大学群と比較すると規模や制度面で見劣りする傾向があります。
海外提携校数
駒澤大学経営学部の海外提携校数(84校)は限られた数にとどまっているものの、アジア地域を中心に実務的な連携を強めており、経営学の教育内容に国際的な実践視点を取り入れる基盤となっています。提携校を通じた短期留学や研修制度は、学生に国際的なビジネス感覚を育む機会を提供し、国内志向の学生にとっても身近な国際経験の入り口となっています。
専修大学経営学部の海外提携校数(36校)は駒澤大学と比べてやや多めであり、長期交換留学やダブルディグリープログラムなど選択肢の幅が広いことが特徴です。これにより学生は多様な文化や教育環境を直接体験でき、将来の国際的なキャリア構築に役立てることができます。また、海外提携校からの留学生との交流も盛んで、国内にいながら国際的な視点を磨ける点も強みです。
他大学群と比べると、日東駒専の大学は海外提携校数が数十校規模であり、一定の国際的な学びの機会を提供していますが、GMARCH以上の大学群では百校規模の協定先を有する大学も珍しくありません。そのため、国際ネットワークの広さや留学制度の多様性では上位大学群に差をつけられているものの、駒澤大学・専修大学も基礎的な国際交流の体制を整えており、学部生が実際に国際経験を積む機会は十分に確保されています。
結局駒澤大学経営学部と専修大学経営学部のどちらが良いか

駒澤大学経営学部のまとめとしては、伝統ある私立大学の一学部として、経営学を実務的かつ体系的に学べる環境が整っており、中規模の学部ならではのアットホームな雰囲気と教員との距離の近さが魅力です。就職面では安定した実績を持ち、金融や流通、サービス業など幅広い業界に卒業生を送り出しており、実学志向の学生に適しています。加えて、国際交流や実務教育の取り組みも進んでおり、基礎から応用まで一貫して学べる学修環境が整っている点は強みです。
専修大学経営学部は、伝統的に商学・経営学教育に注力してきた大学の特色を受け継ぎ、経営学の専門性を深めつつも現代的な課題に対応できる教育体制を整えています。規模も大きめであり、豊富なゼミ活動やキャリア教育の機会が確保されているため、多様な進路を志向する学生にとっては柔軟性の高い環境です。海外提携校の多さや国際交流の活発さも特筆すべき点で、グローバル志向の学生にとって有益な選択肢となります。
他大学群と比べると、両学部は日東駒専という枠組みの中で標準的な教育水準と就職力を有していると言えます。GMARCHの経営・商学系学部に比べるとブランド力や大手企業への就職率で差を感じる部分はあるものの、実務的な学びとキャリア形成の支援体制は十分に整っており、コストパフォーマンスの高い選択肢です。特に駒澤大学は落ち着いた規模と安定感が、専修大学はネットワークや国際性の高さが強みとなり、学生の志向によって選択が分かれる結果となるでしょう。