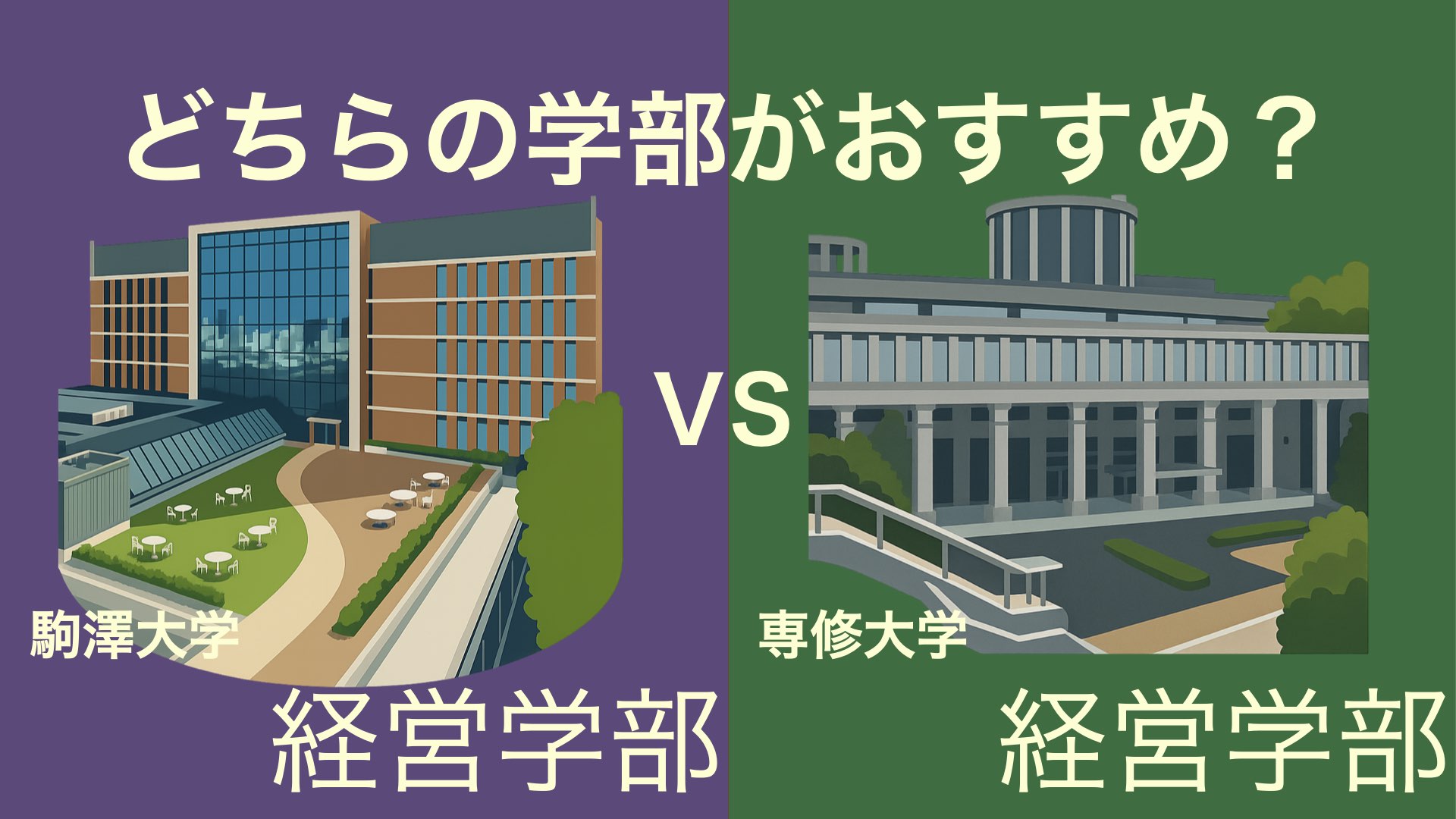駒澤大学経営学部と専修大学経営学部はどんな大学?

基本情報
| 項目 | 駒澤大学経営学部 | 専修大学経営学部 |
|---|---|---|
| 学部設立 | 1969年 | 1962年 |
| 所在地 | 東京都世田谷区駒沢1-23-1(駒沢大学駅) | 神奈川県川崎市多摩区東三田2-1-1(生田駅) |
| 学部理念 | 環境変化に直面する企業や社会において、情報を収集・分析・統合しつつ、自ら課題を発見し、適切かつ迅速に解決できる人材を養成する。そのために、経営に関わる理論的・実践的研究の深い知識、仏教と禅による人間観とグローバルな視野による広い教養を礎に、合理的な分析とチームによる問題解決を実践できる能力を陶冶する。 | 経営学部は、経営学を構成する複数の学問領域を研究・教育することにより、経営に関わる諸問題に対する洞察力を有し、問題を解決する手段を創造的に考察し、その解決に向けて自主的に行動することができる人材を養成することを目的とする。 |
駒澤大学経営学部は1969年に設立され、東京都世田谷区に位置しています。最寄り駅は駒沢大学駅であり、都心からのアクセスの良さも魅力です。経営学部では、会計・マーケティング・経営戦略など幅広い分野を学べるカリキュラムが整備されており、理論と実践を両立できる環境があります。駒澤大学は仏教系大学としての背景を持ちつつも現代的な教育への対応が進んでおり、地域社会や企業との連携も積極的です。こうした立地と教育内容の両面から、安定した人気を保っている学部といえます。
専修大学経営学部は1962年に設立され、神田キャンパスや生田キャンパスを拠点に教育を展開しています。最寄り駅は生田駅であり、都市型キャンパスの利便性を生かし、企業や社会とのつながりを活かした教育を推進しています。経営学部は専修大学の看板学部の一つであり、企業経営の理論から実践に至るまで幅広い科目を配置し、資格取得や実務に直結する学びを重視しています。歴史的にも日本で早い段階から商学教育を展開してきた伝統を受け継ぎつつ、グローバル化に対応する教育体制を整えているのが特徴です。
他の大学群と比べると、GMARCHの経営学部はより高度な研究環境や企業との連携力で一歩上の評価を得ていますが、日東駒専の中では専修大学は伝統と実務教育に強みを持ち、駒澤大学は安定した教育環境とアクセスの良さ
大学の規模
駒澤大学経営学部の学生数(535名)は、同大学の中でも中規模の学部として位置付けられており、経営学の幅広い分野を学ぶことができる環境が整っています。学生数が適度であるため、ゼミや演習での個別指導や議論の機会が多く、学習の深まりや学生同士の交流に直結しています。また、都心に近い立地を活かした産学連携プログラムやインターンシップへの参加機会も豊富であり、学生数の規模感と学修環境が良いバランスを保っています。大規模すぎない学部だからこそ、学生同士や教員との距離が近く、アットホームな雰囲気で学べる点が特徴です。
専修大学商学部の学生数(553名)は、私立大学の商学部としては比較的大規模であり、幅広い科目と多彩な専攻が用意されています。大規模学部ならではの充実したカリキュラムに加えて、留学制度や資格取得支援なども手厚く、学生一人ひとりが自分の関心に合わせた進路を選択しやすい環境があります。規模の大きさによって、学内に多様な人材が集まり、人的ネットワークが広がりやすいことも強みです。また、大人数であることで競争意識が高まり、切磋琢磨する雰囲気が自然と形成されている点も特徴です。
他の日東駒専やGMARCHと比べると、学生数の規模感は大学ごとに大きく異なります。日東駒専グループ内では数千人規模の学部が一般的であり、専修大学商学部のように大規模な学部は、より幅広い学びやネットワーク形成が可能です。一方、駒澤大学経営学部のように中規模の学部は、教員と学生との距離の近さや少人数教育のメリットが際立ちます。したがって、どちらが適しているかは、規模の大きさを活かした多様な学びを求めるか、アットホームな雰囲気で集中した学びを重視するかによって評価が分かれるといえます。
男女の比率
駒澤大学経営学部の男女比(61.4 : 38.6)は、男子学生がやや多い傾向にありますが、近年は女子学生の割合が徐々に増えてきています。経営学部は将来のビジネスや企業活動に直結する実学を扱うため、性別を問わず幅広い層から支持を集めています。特に女子学生は、マーケティングや国際経営といった分野への関心が高く、学内では男女双方が活発に活動する姿が見られます。こうした男女比のバランスの変化は、社会の多様化を反映したものであり、学内の議論やゼミ活動の質をより高めています。
専修大学商学部の男女比(66.2 : 33.8)は、商学という学問分野の特性から女子学生の割合が比較的高めになっています。商学部では会計やマーケティング、流通などの実務的な領域を幅広く学ぶため、就職に直結する分野として女性からの支持も強く、男子学生とほぼ均衡した構成となっています。特に資格取得や企業との共同プロジェクトに積極的に取り組む女子学生が増えており、性別を超えた活発な学修環境が形成されています。多様なバックグラウンドを持つ学生が集まることで、互いに刺激を受けやすい点も魅力です。
他の日東駒専やGMARCHと比べると、経済学部や経営学部、商学部といった社会科学系の学部は男女比の偏りが比較的少なく、全国的にもバランスが取れています。日東駒専グループの中では男子学生がやや多い傾向が残るものの、近年は女子学生が積極的に進学するケースが増えており、大学全体の男女比は均衡化しつつあります。これにより、学修や課外活動において性別の違いを意識せず、多様な視点から議論や研究が進められる環境が整っています。
初年度納入金
駒澤大学経営学部の初年度納入金(125.0万円)は、私立大学としては標準的な水準に位置しています。経営学部は学問の性質上、幅広い実学的な学びを展開しているため、学費に見合った実務的教育環境を得られる点が特徴です。特に演習やゼミ、企業連携プログラムが整っており、費用対効果を重視する学生にとっても納得感のある金額となっています。また、大学として奨学金制度や学費分納制度を備えており、経済的な理由で学びを諦めずに済むサポート体制も整っています。
専修大学商学部の初年度納入金(122.6万円)は、駒澤大学とほぼ同水準にあり、私立文系学部として一般的な金額です。商学部は資格取得支援や実務教育に注力しており、学費の中で多様な学修機会を得られるのが大きな魅力です。さらに、大学独自の奨学金や特待制度の充実も専修大学の特徴で、経済的に負担の大きい学生でも安心して学べる体制が整っています。学費面で大きな差がないため、教育内容や立地条件を重視して進学を検討する学生が多い傾向にあります。
日東駒専やGMARCHの大学群と比較すると、両校の初年度納入金はほぼ同じ水準に収まっています。私立大学文系学部の多くは同程度の費用設定となっているため、学費そのものが決定的な差になるケースは少ないのが実情です。そのため、他大学群と比較する場合でも、費用対効果をどう捉えるかが重要なポイントとなり、学費の水準よりも教育環境や就職実績、学生サポートの充実度といった側面で違いが現れることが多いといえます。
SNSでの評価
駒澤大学経営学部のSNSでの評価は、落ち着いたキャンパス環境と学生生活の充実度に言及する投稿が多く見られます。特に渋谷や新宿といった都心へのアクセスの良さに魅力を感じる学生が多く、学業とアルバイト、サークル活動を両立できる点が評価されています。一方で、経営学部としての学びは「ゼミや授業次第で大きく変わる」という声もあり、学生自身の主体性が重要であることが強調されています。総じて、学習環境と学生生活のバランスに満足している意見が多い印象です。
専修大学商学部のSNSでの評価は、資格取得支援や実務的教育が充実している点をポジティブに捉える学生が多く見られます。簿記や会計、マーケティングといった実学に直結する分野で力をつけられることに魅力を感じ、進路選択に直結する学びを得られる点が高く評価されています。その一方で、キャンパスがやや郊外に位置するため「アクセス面で不便さを感じる」という意見も見られます。ただし、その分アットホームな雰囲気や学生同士のつながりを重視する傾向があり、温かみのある学習環境として支持されています。
日東駒専やGMARCHと比較すると、両校は「アットホームで学生生活に密着した学び」を評価されやすい一方で、ネームバリューやブランド力ではやや劣る傾向がSNS上でも見られます。ただし、駒澤は立地の良さ、専修は資格支援の手厚さといった特色を持ち、学生生活を豊かにしたいか、将来のキャリア形成を重視したいかによって評価が分かれています。他大学群ではより研究色やブランドを重視する傾向が強いため、両校は「学生主体で充実度を高めやすい大学」としてポジティブに捉えられています。
合格難易度(偏差値・倍率)

偏差値(マナビジョン)
駒澤大学経営学部の偏差値は 60 です。首都圏の私立大学の中では日東駒専の水準に属し、標準的な難易度として位置づけられています。経営学という分野は実学的な人気を持ち、受験生からの志望動機も幅広いのが特徴です。立地条件が良く、都心へのアクセスも便利であるため、安定的に多くの志願者を集めており、偏差値は安定した水準を維持しています。学科選択やカリキュラムの多様性から、自分の進路を具体的に描きやすい学部として知られています。
専修大学商学部の偏差値は 57 です。同じ日東駒専の水準に属しますが、実務教育や資格取得支援の充実度から、学びを実社会に直結させたい受験生に人気があります。特に商業・会計・流通に関する教育に力を入れており、就職に強い学部としてのイメージが定着しています。近年は入試改革や学習支援体制の強化もあり、安定した志願者数を確保しているため、偏差値も堅調に推移しています。就職に直結する専門教育が志望者の関心を引く傾向にあります。
日東駒専全体としては、いずれの学部も偏差値は60未満の中堅水準に位置しており、学部ごとの特色が受験生にとって選択の決め手となります。駒澤は立地や学習環境のバランスを重視する層に支持されるのに対し、専修は資格や実務的スキルを重視する層からの人気が高い点で住み分けができています。他の大学群、特にGMARCHに比べると難易度は劣るものの、日東駒専の中では両校とも安定した位置を占めています。
倍率
駒澤大学経営学部の倍率(3.7倍)は、日東駒専グループの中でも標準的な水準であり、毎年安定した志願者数を確保しています。経営学部は将来のキャリアに直結する実学的な人気が高いため、倍率は大きく変動せず、安定した入試難易度を維持しています。特に都市部にキャンパスを構えることから、立地面の利便性が志願者の動機に影響している点も見逃せません。
専修大学商学部の倍率(3.9倍)も同じく標準的で、駒澤大学と大きな差は見られません。専修は商学教育に特化していることから、資格取得や就職を意識する受験生に支持され、安定した入試人気を保っています。ここ数年は出願方式の多様化により、倍率が過度に上昇することは少なく、受験生にとって挑戦しやすい学部としての位置づけを維持しています。
日東駒専全体としては、倍率は総じて中堅私立大学の平均的な範囲に収まっており、いずれも極端に高倍率となるケースは少ない傾向です。これは受験生が現実的な進学先として日東駒専を併願に組み込むことが多いためであり、駒澤と専修の倍率もその枠組みの中で安定的に推移しています。GMARCHに比べると倍率は低めで、受験のハードルは相対的に下がる一方、合格後の進路選択や教育環境の特色で差別化が図られています。
卒業後の進路

有名企業の就職率
駒澤大学経営学部の有名企業就職率(7.8%)は、日東駒専グループ全体の中では標準的な水準に位置しています。学部として資格取得支援やインターンシップ制度を強化しており、金融、流通、サービス業界など幅広い分野に卒業生を送り出しています。ただし、GMARCHと比較するとやや見劣りする数値であり、上位層を目指す学生は努力や実績づくりが求められる傾向があります。
専修大学商学部の有名企業就職率(7.5%)も同程度の水準で、駒澤大学と大きな差は見られません。専修は特に商学領域に強みがあり、会計や流通、メーカー関連企業への就職実績を持っています。実学教育の充実によって就職支援も積極的であり、就職率そのものは安定している一方、超大手企業を志望する場合は個人の努力が結果を大きく左右します。
日東駒専の平均値は概ね10%前後であり、両校の数値はその範囲内に収まっています。これに対してGMARCHでは20%前後となるため、駒澤・専修ともに上位層との差は存在します。ただし、各大学は立地やカリキュラムの特色を生かして安定的な就職を支えており、キャリア形成においては学部の特性と学生自身の取り組みが成果を大きく左右するといえます。
主な就職先
株式会社大塚商会(5名)
警視庁(4名)
レバレジーズ(3名)
船井総合研究所(3名)
駒澤大学経営学部の就職先は、金融業界では都市銀行や地方銀行、証券会社など安定した業種への就職が目立ちます。加えて、製造業や情報通信業、流通・小売業といった幅広い分野に進む学生も多く、特に営業や企画職に強みを持つ傾向があります。大学が持つOB・OGのネットワークや、学部で培う経営知識を実務に活かせる点が評価され、安定的な就職実績につながっています。
専修大学商学部の就職先は、商社やメーカー、金融機関、さらにサービス業や情報通信業に至るまで幅広い分野に広がっています。特に流通やマーケティング関連企業に強みを持っており、学部の教育内容がそのままキャリア選択につながる点が特徴です。また、就職支援講座や企業との共同プログラムを通じて、実践的な能力を磨きながら進路選択を行える環境が整っています。
日東駒専の他学部と比較すると、駒澤大学経営学部は金融や営業職に安定的な就職が多く、専修大学商学部は流通や商社といったビジネスの最前線に直結する進路が多い傾向にあります。両者とも大手企業への就職実績は一定水準を維持していますが、GMARCHと比べると就職先の選択肢や待遇面ではやや控えめです。ただし、学生の学びと適性に応じた進路が実現しやすい点は強みといえます。
進学率
駒澤大学経営学部では、卒業生の進学率(1.2%)は比較的低めであり、多くの学生が学部卒業後にそのまま就職を選ぶ傾向にあります。経営学部という性質上、企業での実務や即戦力としてのキャリアを早期に築きたいと考える学生が多いためです。ただし一部の学生はMBAや会計系の大学院に進学し、専門性をさらに高めていますが、進学は少数派となっています。
専修大学商学部の進学率(1.2%)も同様に低めであり、商学を学んだ知識を社会に直結させたいという意識から、多くの学生が卒業後すぐに就職しています。進学を選ぶ場合は、専修大学の大学院に進むか、他大学のビジネス系大学院に進学するケースが見られます。進学希望者の割合は全体の中では限定的であり、キャリア志向が強く表れています。
日東駒専グループ全体としても、進学率は低水準に留まる傾向が強く、両校の結果もその流れに一致しています。経済学部と比較すると経営・商学系の学部は大学院進学よりも即戦力としての就職を重視する学生が多いため、進学率はやや低めに出るのが一般的です。進学する学生の数値は少ないものの、両校ともに教育内容を応用して実務へとスムーズに移行できる環境が整っている点は評価に値します。
留学生

受け入れ状況
駒澤大学経営学部の留学生数(100名)は、大学全体の国際交流政策の影響を受けて増加傾向にあります。経営学部は実践的な教育を重視しており、留学生との共同学習やプロジェクト活動を通じて国際的な視点を身につける機会が豊富です。特にアジア地域からの留学生が多く、経営戦略やマーケティングの授業では異文化の考え方を交えた議論が活発に行われています。
専修大学商学部の留学生数(385名)は、商学部の特性上、アジアを中心とした経済・経営分野に関心を持つ留学生に支持されています。交換留学制度を活用した受け入れも多く、学部内ではグローバルビジネスに関連する演習やゼミに積極的に参加する留学生の姿が見られます。商学部は国際的な視点を教育課程に取り入れており、留学生が学部全体に与える刺激は大きいといえます。
日東駒専グループと比較すると、両校の留学生受け入れ数は平均的な水準に位置しています。特に大規模大学と比べると絶対数では劣るものの、授業や学生活動における留学生との接触の密度は高く、国際交流の質という点では一定の強みがあります。こうした環境は日本人学生にとっても異文化理解や国際的な協働力を高める大きな契機となっています。
海外提携校数
駒澤大学経営学部の海外提携校数(84校)は、比較的幅広い地域との連携を持っているのが特徴です。特にアジアや欧米の大学との交流協定を結んでおり、学生は短期・長期の留学プログラムを通じて、海外の教育システムや文化を直接体験することができます。経営学部の実践的な学びに加え、こうした提携校との協力は国際的なビジネス感覚を養う機会を提供しています。
専修大学商学部の海外提携校数(36校)は、伝統的に国際交流に力を入れてきた大学全体の方針に基づき、積極的に拡充されています。アジア太平洋地域をはじめ、欧米のビジネススクールとの提携も多く、商学部の学生は海外インターンシップや研修プログラムに参加する道が開かれています。これにより、商学を学ぶ学生が海外での実践経験を積みやすい環境が整っています。
日東駒専グループと比較すると、両大学とも平均的な提携校数を有しており、特にアジアとの交流に強みを持つ点が共通しています。GMARCHと比べると規模や数では劣る部分もありますが、学部教育と直結した交流プログラムを設けている点で、国際性を実際の学びに活かす工夫が見られます。学生にとっては、ただの留学経験にとどまらず、将来のキャリア形成につながる国際的な学びを得られる機会となっています。
結局駒澤大学経営学部と専修大学経営学部のどちらが良いか

駒澤大学経営学部のまとめとしては、比較的規模の大きな学部であり、経営学の理論から実践まで幅広く学べるカリキュラムを整えています。留学生や提携校との交流によって国際性も一定程度確保されており、学生のキャリア形成に直結する学びが提供されています。一方で、日東駒専グループの中では標準的な水準にあり、より上位のGMARCHと比べると就職先や難易度で劣る側面もあります。
専修大学商学部は、伝統的に商学教育に強みを持ち、特にビジネスや経営に直結する実務教育を重視しているのが特徴です。就職支援体制や国際交流の仕組みが充実しており、学生にとって実践的なキャリア形成が可能な環境が整っています。学内外のネットワークを活かした就職活動や海外経験を積める機会も豊富で、学生生活全般において学びを社会につなげやすい傾向があります。
日東駒専全体の位置づけと比べると、両大学とも平均的な水準を持ちながらも、分野ごとに異なる強みを発揮しています。駒澤大学経営学部は学内外での活動の幅広さと安定性が評価され、専修大学商学部は実務的な教育と国際性の高さが特徴です。学生が求めるキャリアビジョンに応じて選択肢が分かれるため、より実務志向で国際的な経験を重視するなら専修大学、幅広い基礎学習と安定した学びを求めるなら駒澤大学が適しているといえるでしょう。