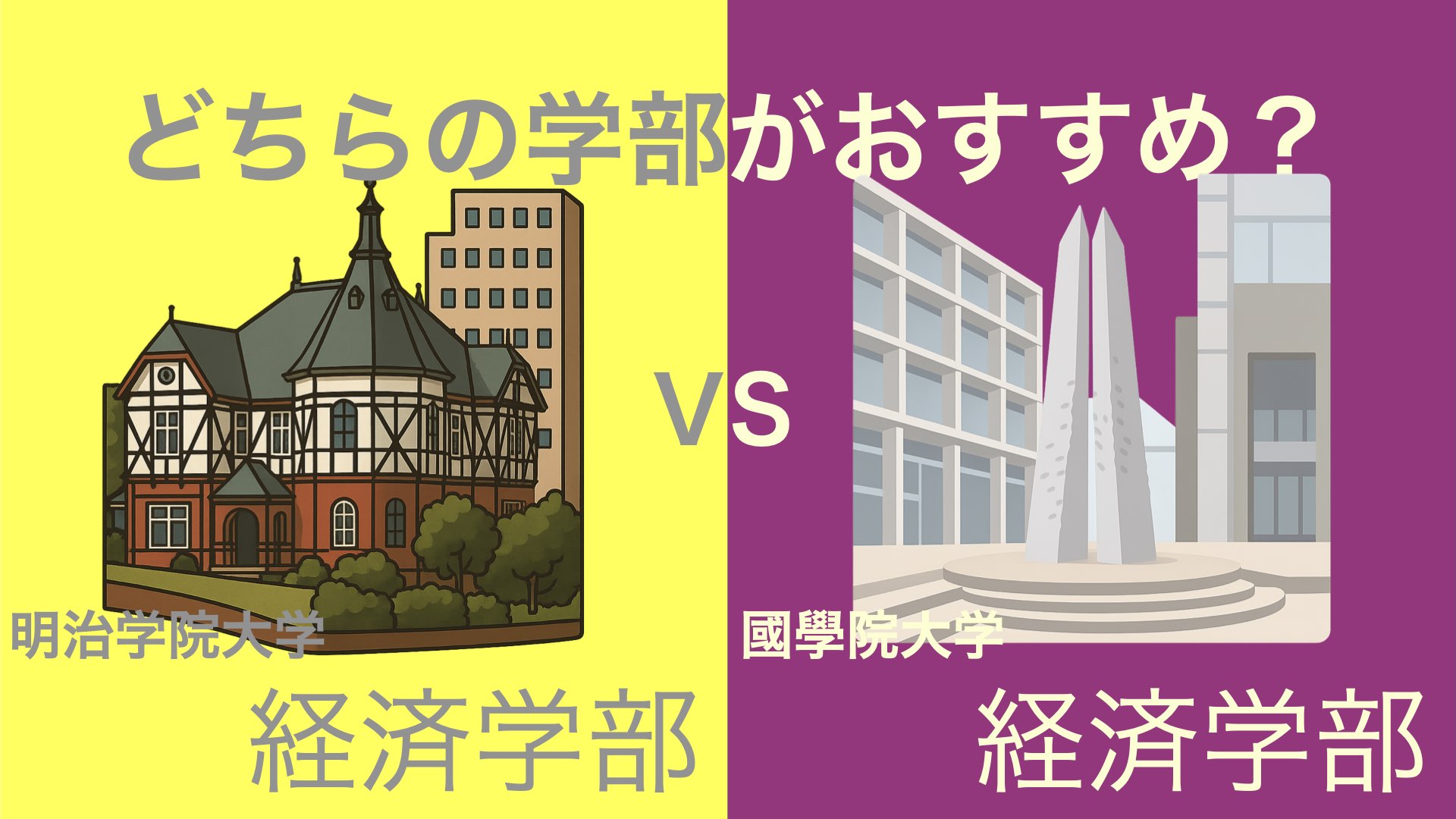明治学院大学経済学部と國學院大学経済学部はどんな大学?

基本情報
| 項目 | 明治学院大学経済学部 | 國學院大学経済学部 |
|---|---|---|
| 学部設立 | 1949年 | 1966年 |
| 所在地 | 東京都港区白金台1-2-37(白金台駅) | 東京都渋谷区東4-10-28(渋谷駅) |
| 学部理念 | 経済学部が目標とするのは、健全な倫理観を持ちながら経済学の知識によって社会で活躍できる人材の育成であり、経済学の多様性を理解し、新しい変化に弾力的に取り組めるようなバランス感覚を身につけた「良識のある経済人」の育成である。 | 経済学部は、多元化しグローバリゼーションの進展する社会の中にあって、経済学の基礎力と日本経済に関する知見を兼ね備え、未来への実践的で創造的な対応力を身につけた、社会に貢献できる専門的教養人を育成することを目的とする。 |
明治学院大学経済学部は1949年に端を発し、キリスト教主義と国際性を背景に都市型キャンパスで実学とリベラルアーツを交差させる学びを展開してきました。立地面では最寄駅として白金台駅が挙げられ、首都圏の産業・行政・NPO等との接点を日常的に得やすい点が大きな利点です。創設以来の歴史資産と都心アクセスの良さは、講義外の学修機会やインターン、ゲスト講義の誘致にも直結し、経済学の理論と現場を往還できる環境を形成しています。学内外のネットワークが濃密に重なることで、学部生段階からのプロジェクト参加や課題解決型の学びが促される土壌が整っています。
獨協大学経済学部は…ではなく今回は國學院大学経済学部との比較です。國學院大学経済学部は1966年の学統を受け継ぎ、伝統知と現代経済の課題を結びつける教育を志向してきました。最寄駅は渋谷駅で、都心部へのアクセスと落ち着いた学習環境の両立が図られています。神道学・日本文化研究で知られる総合大学の資源を背景に、歴史・文化への洞察と経済分析を接続しうる点が特色で、地域社会や文化産業、公共政策分野との連携学修にも展望が開けます。フィールドワークや資料調査の導線が確保され、理論と文脈理解を重ねる学びが可能です。
他の大学群と比べると、いずれの学部も都心アクセスの良さを活かした学外連携や実務家交流の機会を得やすく、交通利便性が学生生活の密度を高める要素として機能します。明治学院大学経済学部は都市ネットワークの広がりをテコに実践機会の量を確保しやすく、國學院大学経済学部は伝統知・文化資源の近接性を生かして文脈に根差した探究を深めやすいという違いが見えます。いずれも通学動線の短さが日々の学修効率を高め、課外活動やアルバイト、インターンを柔軟に組み合わせられる点が学修設計上の強みになっています。
大学の規模
明治学院大学経済学部の学生数は690名で、学内の規模としては中堅からやや大規模に属します。人数が多いことで開講科目の幅が広がり、ゼミや講義の選択肢が豊富に用意されている一方で、クラス編成や指導体制に工夫が求められています。学内施設の利用や課外活動への参加も盛んで、多様な学生同士の交流から新しい視点や考え方を得る機会が豊富です。一定規模の学生数は学部独自の研究会やプロジェクト活動を活発化させ、経済学的知見を現場に結びつける取り組みを後押ししています。
國學院大学経済学部の学生数は510名で、こちらも安定した規模を持ち、大学全体の伝統と文化研究の強みを背景にした経済学教育を展開しています。規模が適度であることから、学生と教員の距離感が比較的近く、少人数教育や双方向的な授業スタイルが確立されやすい環境にあります。学部内での人的ネットワークが緊密になりやすく、同じ志を持つ仲間と切磋琢磨する中で専門性を磨くことができます。
他の大学群と比べると、いずれも学生数において突出した大規模校ではないため、きめ細やかな教育や学生同士の密接な関わりが維持されやすい点が特徴です。明治学院大学経済学部は規模の大きさを生かして幅広い選択肢を提供し、國學院大学経済学部は規模を抑えたことによる一体感や面倒見の良さを強みとしています。それぞれの規模感が学生生活に異なる学びの形をもたらし、進学を検討する際の重要な判断材料となります。
男女の比率
明治学院大学経済学部は男女比54.3 : 45.7となっており、女子学生がやや多い傾向にあります。このバランスは講義やゼミナールの雰囲気にも影響し、特に文系学部として多様な意見が交わされやすい環境を生み出しています。また、女子学生の割合が高いことからキャリアセンターや学生支援の面でも、女性を意識したサポート体制が整えられている点が注目されます。男女双方にとって学びやすい環境を重視する受験生にとって、この点は魅力的な特徴といえるでしょう。
國學院大学経済学部は男女比67.7 : 32.3で、男子学生の割合が多くなっています。この傾向は経済学部の性質上、数理的な研究や実証分析を好む学生層が一定数存在することと関連していると考えられます。ゼミやグループワークでは積極的に意見を主張する学生が多く、活発なディスカッションが期待できる環境が形成されています。男子の比率がやや高い一方で、女子学生の存在感も確保されており、全体として偏り過ぎないバランスを維持しています。
他の大学群と比べると、日東駒専レベルでは男女比がほぼ均等に近い学部が多く、GMARCHでは大学や学部ごとにばらつきが大きいのが特徴です。その中で明治学院大学経済学部は女子比率が高めで、國學院大学経済学部は男子比率が高めという違いがあり、志望者にとっては学習環境やキャンパスの雰囲気を選ぶ際の参考材料となります。特に学生生活の過ごし方や人間関係を重視する受験生にとって、この差異は進学先を決めるうえで考慮すべきポイントといえるでしょう。
初年度納入金
明治学院大学経済学部は初年度納入金が132.7万円であり、私立大学としては比較的標準的な水準に位置しています。特に経済学部は授業や演習に必要な費用が安定しており、学費面の負担を抑えつつも教育内容の充実を期待できる点が魅力です。また、学生生活においては奨学金や学費減免制度の活用も視野に入れることで、経済的な不安を軽減しながら学びに専念する環境を整えることができます。
獨協大学経済学部は初年度納入金が126.7万円となっており、首都圏の私立大学として妥当な範囲に収まっています。授業料に加えて実験や演習にかかる追加費用は比較的少なく、コストパフォーマンスの良さが際立ちます。さらに、獨協大学でも学内奨学金や支援制度が整備されているため、経済的背景に左右されず多様な学生が学べる体制が確立されています。
他の大学群と比べると、両大学の初年度納入金はほぼ同水準にあり、学費面で大きな差は見られません。それぞれが提供する教育内容やキャンパス環境、また奨学金制度の柔軟さといった点を比較することで、自身に合った学習環境を選択する判断材料とすることができます。学費の数値だけでなく、実際の学生生活全体を含めて検討することが重要です。
SNSでの評価
明治学院大学経済学部はSNS上での評価において、学生生活の充実やキャンパスの雰囲気に関する投稿が目立ちます。特に横浜キャンパスの環境やアクセスの良さを評価する声が多く、都市型キャンパスでの学びやすさが強調されています。また、授業の自由度や留学制度に関するポジティブな体験談がシェアされる一方で、課題や授業負担については人によって意見が分かれる傾向も見られます。
獨協大学経済学部はSNS上で、落ち着いたキャンパス環境やアットホームな雰囲気が好意的に取り上げられることが多いです。学生間の交流やクラブ活動の活発さを伝える投稿もあり、学業と課外活動の両立がしやすい点が評価されています。一方で、都心から距離があるため通学時間についての言及も散見され、利便性よりも学習環境を重視する学生に合う大学であることが伺えます。
他の大学群と比べると、両大学ともに学生同士の交流やキャンパスライフの魅力がSNS上で強調されており、特定の学問的成果よりも生活全般や学習環境に関する評価が多い傾向にあります。進学を考える際には、単なる授業内容だけでなく学生生活全体の印象が進路選択に影響することがうかがえる点が特徴です。
合格難易度(偏差値・倍率)

偏差値(マナビジョン)
明治学院大学経済学部は偏差値63であり、これは大学群基準で日東駒専の55をちょうど示す水準にあたります。学生にとっては入学難易度が比較的抑えられているため、幅広い受験層に門戸を開いていることが特徴です。その一方で、教育環境やサポート体制には独自の特色があり、入試の偏差値だけでなく学びの幅広さが評価されています。比較的安定した入学難易度で挑戦しやすい学部といえるでしょう。
國學院大学経済学部は偏差値66であり、日東駒専の55をやや上回る数値となっています。これは基準値よりも高く、一定の学力を持つ受験生が集まる傾向を示しており、受験難易度は相対的に高めです。國學院大学は伝統的な教育理念を背景に経済学教育を展開しており、偏差値に反映された学習意欲の高さが学部の雰囲気を特徴づけています。受験生にとっては競争を意識しやすい環境です。
他の大学群と比べると、明治学院大学経済学部の偏差値63は日東駒専の基準である55と一致しており、標準的な位置にあるといえます。一方、國學院大学経済学部は66で、この水準は日東駒専よりやや高くGMARCH基準の62.5には届かない中間域に位置します。そのため、両者を比較すると國學院大学のほうが入学難易度は高めであり、明治学院大学は挑戦しやすく、國學院大学はより競争が求められるという構図が明確に浮かび上がります。
倍率
明治学院大学経済学部は倍率2.9倍で、易しすぎず難しすぎない現実的な競争環境です。出願方式の選択や過去問の的確な分析が結果を分けやすく、特に共通テスト利用や英語重視型など、自分の得点源を最大化する戦略が有効です。年度によって志願動向が揺れるため、安全校・挑戦校のポートフォリオを組みつつ、英語・国語・選択科目の弱点を早期に潰す計画性が合格率を押し上げます。
國學院大学経済学部は倍率4.1倍とやや高めで、完成度の高い答案作りが要求されます。出題の癖(用語の正確さ、設問文の条件処理、資料読解の精度)に対応できるかが鍵で、過去問の縦解きに加えて出題分野の頻度管理が有効です。記述・マークともにケアレスミスの影響が大きく、時間配分の訓練と見直しプロトコルの徹底が競争力を左右します。
他の大学群と比べると、日東駒専は概ね3.0倍前後、GMARCHは4.0倍超のケースも見られます。これに照らすと、明治学院の2.9倍と國學院の4.1倍は中堅〜中堅上位帯の標準〜やや高めのレンジです。併願設計では、科目配点と形式適性の一致度を最重視し、得点源の再現性を高めることで倍率の影響を緩和できます。
卒業後の進路

有名企業の就職率
成城大学経済学部は有名企業就職率12.6%であり、同じ文系の学生が多い私立大学の中では比較的堅実な数字を示しています。特に金融や流通などの分野で採用枠を持ちやすいことが背景にあり、安定的なキャリア形成を志す学生にとって一定の強みとなります。他大学と比べて突出した高さは見られないものの、学内でのキャリア教育や就職支援体制によって数値が維持されていると考えられます。卒業後の進路を具体的に描きやすい環境が整っている点は安心材料といえるでしょう。
獨協大学経済学部は有名企業就職率8.8%となっており、成城大学の水準と比較するとやや低めの数値です。語学教育や国際系のカリキュラムに特色がある一方で、卒業後に専門性を活かせるフィールドが限られる場合もあり、その影響が就職率に現れています。ただし、近年は学内でのキャリア形成支援が強化されつつあり、特定の業界では安定した採用実績も見られます。経済学の基礎と国際性を組み合わせたキャリア志向を持つ学生には適した環境といえるでしょう。
他の大学群と比べると、日東駒専レベルの大学では有名企業就職率が10%前後、GMARCHレベルでは20%前後が一般的です。これに照らすと、成城大学経済学部12.6%と獨協大学経済学部8.8%はいずれもこれらの大学群の水準を上回っており、特に成城は安定した数値であることが確認できます。両大学とも就職力においては一定の優位性を持っていると評価でき、学生の志向やキャリア形成の方向性に応じて選択肢が広がるといえるでしょう。
主な就職先
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(4名)
トランス・コスモス(4名)
国家公務員(9名)
ニトリホールディングス(5名)
成城大学経済学部では上記の主な企業に加え、金融機関や保険業界への就職が目立ちます。特に地方銀行や信用金庫への就職者が多く、安定志向の学生に支持されている傾向が見られます。また、情報通信業やサービス業への就職も一定数存在し、幅広い業界で卒業生が活躍しています。公務員試験に挑戦する学生も多く、地方自治体や国家公務員への就職実績も積み重ねられてきています。このように就職先は多様であり、学生の進路選択に柔軟性があることが特徴です。
獨協大学経済学部では上記の就職先に加え、航空業界や旅行・観光関連企業への就職も比較的多く見られます。外国語教育に力を入れている大学の特色が反映され、国際物流や貿易関係の企業に進む卒業生も少なくありません。また、公務員試験合格を目指す学生も一定数存在し、特に地方自治体職員や税務署関連職種に進む例が見られます。資格取得支援制度も整っており、卒業後に会計・経理系職種で活躍するケースもあります。
他の大学群と比べると、日東駒専レベルの大学でも大手企業に入る学生は一部に限られる傾向がありますが、成城大学経済学部と獨協大学経済学部はいずれも金融、サービス、公共分野で安定的な就職実績を示しています。特に成城は金融・保険関連に、獨協は国際関連分野に強みがあり、学生の志向に応じて選択肢が広がる点が大きな特徴といえます。
進学率
成城大学経済学部の進学率は1.5%となっており、卒業後に大学院へ進む学生は限られています。そのため多くの学生が就職を選択していることが分かりますが、研究志向の学生にとっては進学支援制度や提携大学院などを活用することで、より専門性の高い学問を追求できる環境が用意されています。就職実績に比べると進学は少数派ではあるものの、選択肢として一定の存在感を保っています。
獨協大学経済学部の進学率は1.4%であり、こちらも進学者は少数にとどまっています。ただし、語学や国際経済の分野で学びを深めたい学生にとっては、大学院進学の道が一定の割合で選ばれており、特に外国語教育や国際的な学習環境の強みを生かした進学先が目立ちます。就職が主流である一方、専門性をさらに磨く学生には相応の進路が整備されています。
他の大学群と比べると、日東駒専や同レベルの大学でも進学率は全体的に低めに推移しています。成城大学経済学部と獨協大学経済学部も例外ではなく、両校とも進学は少数派です。しかし、進学を選んだ場合には大学の特色を反映した専門分野で学びを深められるため、数字以上に内容の濃い進学実績を持つといえます。
留学生

受け入れ状況
成城大学経済学部の留学生数は197名となっており、全学的に見ても比較的コンパクトな規模の中で国際交流を図れるのが特徴です。経済学の学びにおいても、授業やゼミで留学生と交流する機会があり、異文化理解や多様な価値観を身近に感じられる環境が整っています。特にグローバルな視点を養いたい学生にとっては、少人数だからこそ得られる濃密な交流体験が魅力となります。
獨協大学経済学部の留学生数は40名であり、大学全体で国際教育に力を入れている点が反映されています。語学教育に強みを持つ大学として、キャンパスに多様なバックグラウンドを持つ学生が集まっているため、経済学を専攻する学生にとっても英語や他言語を活用した交流の機会が豊富にあります。国際性の強い環境に身を置くことで、経済学的な知識とともに実践的な語学力も培うことができます。
他の大学群と比べると、日東駒専レベルの大学でも30〜50名程度の留学生が在籍することが多いですが、成城大学経済学部や獨協大学経済学部もその範囲に収まっており、国際的な学習環境を備えています。特に獨協大学は語学教育を背景に留学生数を確保しており、成城大学は少人数教育と組み合わせて濃密な国際交流の場を提供している点で、それぞれ特色を発揮しているといえるでしょう。
海外提携校数
成城大学経済学部の海外提携校数は59校であり、比較的多様な留学先を提供しています。学生は短期留学や交換留学を通じて、自身の研究テーマや関心に合わせて海外経験を積むことが可能です。こうした制度は、専門的な経済学の学びを国際的な視点から補完する役割を果たし、語学力の向上だけでなく、異なる経済システムや文化を比較する実践的な機会を提供しています。
獨協大学経済学部は海外提携校数が36校であり、大学全体が持つ語学教育への強みを背景に幅広い国際的な交流先を用意しています。特に英語圏やアジア圏の大学との協定が多く、学生は在学中に多様な地域での学びを経験できる点が特徴です。こうした取り組みにより、語学力と専門知識を組み合わせてグローバルに活躍できる基盤が整えられています。
他の大学群と比べると、日東駒専では10〜20校程度の海外提携校を持つ大学が多いですが、成城大学経済学部と獨協大学経済学部はいずれもそれを上回る規模を有しています。そのため、学生が自らの進路や目的に応じた留学先を選びやすく、国際的な学びを重視する学生にとって魅力的な環境が整っているといえるでしょう。
結局明治学院大学経済学部と國學院大学経済学部のどちらが良いか

成城大学経済学部は偏差値63に加え、有名企業就職率12.6%を持つ点が際立っています。さらに海外提携校数59校により国際的な学びの場を広く提供しているため、入学難易度の高さと就職力、留学機会のバランスが取れた学部といえるでしょう。
獨協大学経済学部は偏差値66に加え、進学率1.4%の低さが特徴的であり、学生の多くは早期に就職を志向していることがわかります。一方で海外提携校数36校という強みを持ち、語学教育の伝統を背景に幅広い国際交流の機会が確保されています。
他の大学群と比べると、日東駒専は偏差値55程度、就職率10%前後、海外提携校数は10〜20校程度が一般的です。これに対して成城大学経済学部と獨協大学経済学部はいずれも偏差値や就職率、提携校数の面で一定の強みを有しており、進路の多様性や国際性を意識する学生にとって選びやすい環境を整えています。