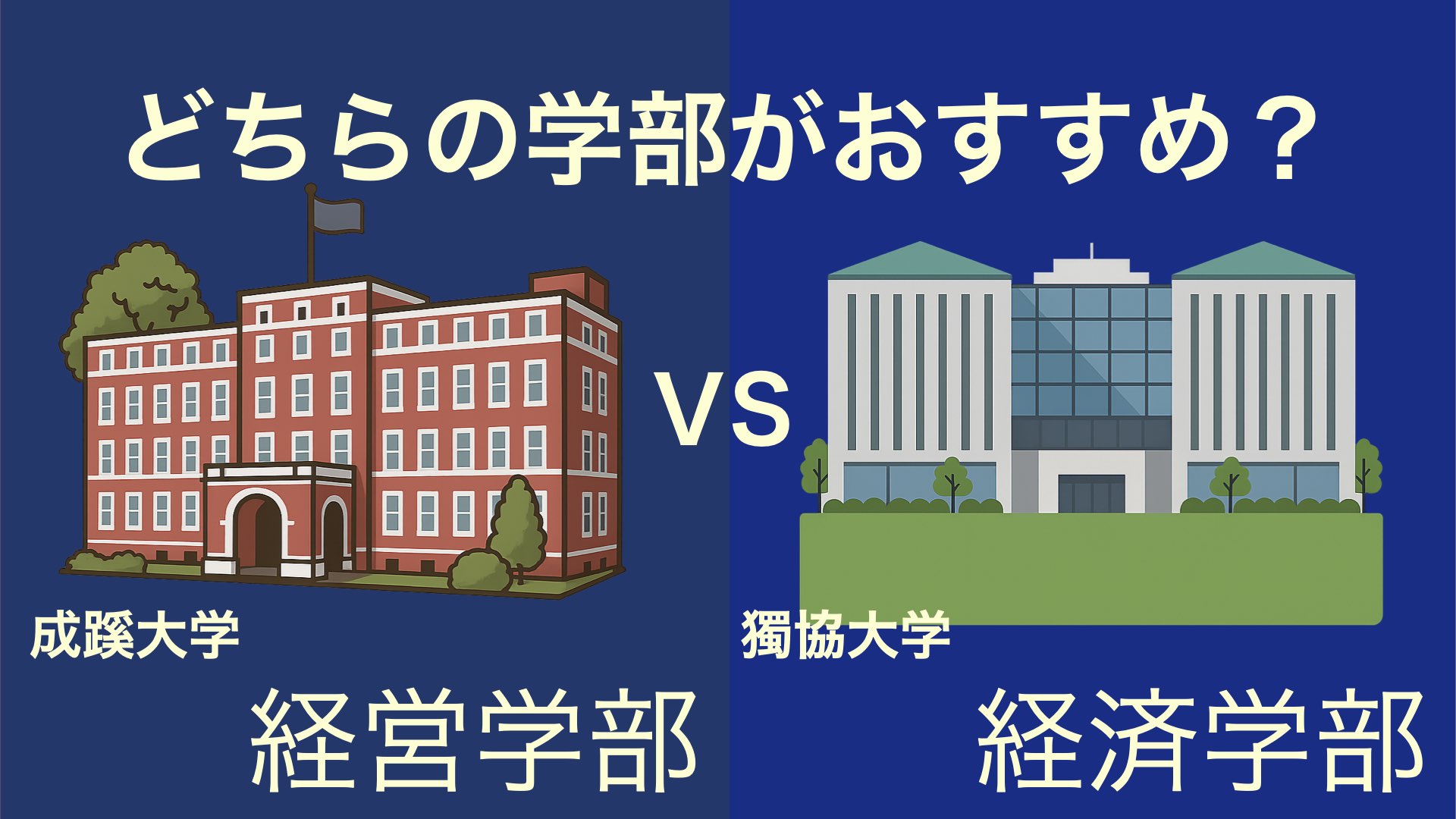成蹊大学経営学部と獨協大学経済学部はどんな大学?

基本情報
| 項目 | 成蹊大学経営学部 | 獨協大学経済学部 |
|---|---|---|
| 学部設立 | 2020年 | 1964年 |
| 所在地 | 東京都武蔵野市境南町1-1-1(吉祥寺駅) | 埼玉県草加市学園町1−1(獨協大学前) |
| 学部理念 | 人文科学、社会科学、自然科学及びこれらにまたがる幅広い視野 で思考・判断できる能力を有し、経営学の基礎的な概念と理論及び経営学の各専 門分野を理解していることに加え、国際文化や情報コミュニケーション技術に関 する知識をあわせ持つことで、企業や企業の経営活動に関する諸問題を柔軟かつ 適応的に解決できる実践的な総合マネジメント能力を修得した、職業人を養成するとともに、総合科学としての経営学を探求し、その研究成果を的確かつ明瞭に 発信することで社会に貢献することを目的とする。 | 経済学部は、外国語の能力、ならびに、豊かな歴史観、自然観、および、倫理観を中核とする教養に基礎付けられた経済学、経営学・情報、環境学の専門知識を習得した、国際的視野を有する優れた社会人、地域社会や国際社会に貢献できる実践的な人材を育成することを教育目的とする。 |
成蹊大学経営学部は2020年に設立された比較的新しい学部で、現代的な経営課題に対応する実践的な教育を展開しています。キャンパスの最寄り駅は吉祥寺駅で、都心からのアクセスも良く利便性に優れています。新設学部ならではの柔軟なカリキュラム設計が特徴で、アクティブラーニングや企業連携授業を取り入れることで、学生が理論だけでなく実務にも対応できる力を養う環境が整っています。歴史の浅さはあるものの、社会の変化に即応できる先進性を重視しており、次世代型の経営教育を志向する受験生にとって注目度の高い学部といえます。
獨協大学経済学部は1964年に設立され、長い歴史を持つ伝統ある学部です。最寄り駅は獨協大学前で、キャンパスは交通の利便性が高いとはいえず、都心とは少々郷里があります。経済学部として幅広い理論と実証研究を重視しており、学生は政策分析や国際経済など多様な分野で基礎から応用まで体系的に学ぶことができます。長年にわたり積み重ねられた教育と研究の蓄積があり、社会的評価や卒業生のネットワークの広さが強みとなっています。歴史と伝統を重視する受験生にとって安定感のある選択肢です。
他の大学群と比べると、日東駒専の経済学部は戦後に設立された学部が多く、安定した教育基盤を築いています。GMARCHの経営学部は近年になって設立された学部も多く、現代的な教育を反映しています。成蹊大学経営学部は2020年設立という新しさが特徴で、GMARCHの経営系学部に近い革新性を備えています。一方で獨協大学経済学部は伝統を持つ点で日東駒専の経済系に近い安定感を示しており、革新性か伝統かという観点で志望動機が分かれるといえるでしょう。
大学の規模
成蹊大学経営学部の学生数は290名で、学部としては中規模の人数構成です。学生数が多すぎず少なすぎないため、ゼミや演習では教員からのきめ細かい指導を受けやすく、学びの密度を高めることができます。同時にクラブ活動や学内イベントも活発に行える規模であり、学生生活の充実度も高い点が特徴です。個別指導と幅広い交流の両立が可能で、落ち着いた環境で学びたい学生にとって魅力的な環境となっています。
獨協大学経済学部の学生数は680名で、成蹊大学経営学部の約2倍を超える規模を誇ります。大規模学部ならではの多様な学生層が集まり、学問分野や進路に関して幅広い交流や競争を経験できる点が強みです。科目選択の幅も広く、経済学の理論から応用まで体系的に学べる環境が整っています。ただし人数が多い分、個別指導の機会はやや限定的となる傾向がありますが、その分多様な価値観や人脈形成に恵まれる学部です。
他の大学群と比べると、日東駒専の経済・経営学部は数百名規模が一般的で、獨協大学経済学部の680名はむしろ上限に近い大規模さを示しています。GMARCHの経済・経営学部も大規模であることが多いですが、成蹊大学経営学部の290名という規模はその中間に位置し、個別性と多様性のバランスが取れた水準です。規模の大きさを重視するか、落ち着いた環境を重視するかによって、志望者の選択が分かれるといえるでしょう。
男女の比率
成蹊大学経営学部は52 : 48という男女比で、比率表示のとおり多様なバックグラウンドの学生が集まっています。経営学の学修では会計・ファイナンスの数理的領域からマーケティングや人的マネジメントの実践領域まで幅広い関心が交差し、演習やプロジェクトでも異なる視点を取り込む機会が多く得られます。授業内外でのグループワークや発表では役割分担が自然に生まれ、企画・分析・調整といった仕事を回しながらコミュニケーション力や合意形成力を鍛えやすい点が特徴です。男女に依存しない参加機会を確保する設計が進んでおり、学びの密度と実践性を高める基盤として機能しています。
獨協大学経済学部は67 : 23という男女比で、学部内には理論・統計・政策・国際など多彩な関心領域を持つ学生が在籍しています。経済学の特性上、数理的な分析やデータ処理、制度や歴史・国際関係の理解など異なるアプローチが併存し、ゼミや輪読、実証研究の場で多様な意見交換が生じやすいことが強みです。演習ではレポート作成や討論、発表が重視され、チームでの作業を通じて問題設定から結論提示までのプロセスを体系的に学べます。男女比の表記に基づき、参加の偏りが生まれないよう配慮された運営が行われ、互いの視点を補完し合う学修環境が整っています。
他の大学群と比べると、経済・経営系の学部では男子比率がやや高めになりやすい一方、近年は授業設計やキャリア教育の多様化に伴い、演習やプロジェクトでの協働体験が広く重視される傾向があります。日東駒専でもグループワークや地域連携科目の導入が進み、学修の場面で役割の固定化を避ける工夫が見られます。GMARCHでは演習科目の充実により、発表・討論・レビューを循環させる形式が一般化し、多様な視点を取り入れるトレーニング機会が豊富です。成蹊大学経営学部と獨協大学経済学部も、男女比の数値に依らず協働を前提にした実践的学びを組み込み、将来の職場で必要なコミュニケーションやチーム運営の力を育てる点で共通しています。
初年度納入金
成蹊大学経営学部の初年度納入金は135.5万円で、授業料のほか教育充実費や施設費を含めた総額となっています。この水準は私立大学の一般的な範囲に位置しており、教育内容や学習環境の整備と費用負担のバランスが意識されています。加えて、大学独自の奨学金や授業料減免制度が用意されており、経済的な事情を抱える学生でも安心して学修を継続できる体制が整っています。少人数教育や企業連携科目など特色ある学びのために投資されていることから、学費に見合った教育体験が得られるといえます。
獨協大学経済学部の初年度納入金は135.2万円で、成蹊大学経営学部の額とほぼ同水準にあります。学部の特色として語学教育や国際交流プログラムを重視しており、それに伴う施設整備や教材費が含まれています。奨学金制度や経済的支援制度も充実しており、学費の負担を軽減しながら幅広い学びを得られる環境が整っています。学費の透明性が高く、学生や保護者にとって納得感のある費用設定といえるでしょう。
他の大学群と比べると、成蹊大学経営学部の135.5万円、獨協大学経済学部の135.2万円はいずれも私立大学として標準的な範囲に位置しており、特に突出した高額や低額ではありません。両学部とも奨学金や減免措置が整っているため、経済的な背景に左右されずに学修を継続しやすい環境といえます。教育環境の特色をどう評価するかが、学費水準に加えて進学先を選ぶ際の判断基準となるでしょう。
SNSでの評価
成蹊大学経営学部はSNS上で、少人数教育による学習環境の良さや教員との距離の近さが評価される声が多く見られます。特に新しい学部としての柔軟性やアクティブラーニングの導入が学生から高く評価され、就職活動に直結する実践的な授業や企業との連携プロジェクトに対して肯定的な意見が多いのが特徴です。また、吉祥寺という立地の利便性や学生生活の充実度もSNSで頻繁に言及され、生活面と学修面の両立が取りやすい環境である点が強調されています。新設学部として注目度が高く、口コミやレビューでもポジティブな意見が多数を占めています。
獨協大学経済学部については、語学教育や国際交流プログラムの充実ぶりに関する評価がSNS上で多く見受けられます。特に外国語教育に強みを持つ大学全体の特色が経済学部にも浸透しており、語学力を武器にした就職活動や海外留学の体験談がポジティブに発信されています。一方でキャンパスの立地や施設の古さについては意見が分かれる部分もありますが、総じて教育内容や国際性の面での評価は高く、経済学の基礎を幅広く学びながら国際的な視野を養える環境として支持されています。
他の大学群と比べると、日東駒専の経済・経営系学部ではSNSでの発信がやや少なく、学生数や地域性の影響で口コミが限定されがちです。これに対してGMARCHの学部では就職活動や学修環境に関する情報発信が活発で、教育資源の豊富さがSNSでも強調されています。成蹊大学経営学部は新設学部としての話題性と吉祥寺立地の人気、獨協大学経済学部は語学教育や国際交流の特色がSNSでの評価に強く反映されており、いずれも他大学群と比較して独自の魅力を発信している点が注目されます。
合格難易度(偏差値・倍率)

偏差値(マナビジョン)
成蹊大学経営学部の偏差値は66で、難易度は高めに位置しています。一般的に日東駒専の目安が55程度、GMARCHの目安が62.5程度とされる中で、この数値はGMARCH水準を上回る水準であり、入学にあたっては学力的に相応の準備が必要となります。経営学部は新設ながらも注目度が高く、学部自体のブランド力も向上している点が受験生にとって魅力です。学修内容の先進性や企業との連携なども難易度を押し上げる要因といえます。
獨協大学経済学部の偏差値は60で、日東駒専の基準を上回りつつも、GMARCHよりはやや下の水準に位置しています。学部の伝統や安定した教育体制が背景となり、幅広い受験層を集めていることがうかがえます。比較的取り組みやすい難易度でありながら、しっかりとした経済学の基礎を学べる点が強みであり、幅広い学生にとって挑戦しやすい環境です。
他の大学群と比べると、成蹊大学経営学部の66はGMARCHを超える数値で、入試の難易度においては大きな優位性を持っています。これに対し獨協大学経済学部の60は日東駒専よりも上で、安定感を備えた実力を示しています。難易度の高い学びに挑むか、比較的取り組みやすい環境で着実に学ぶかが、受験生にとっての判断材料となるでしょう。
倍率
成蹊大学経営学部の入試倍率は4.9倍で、厳しい競争を勝ち抜かなければならない学部といえます。新設ながら注目度が高い学部であり、教育内容の充実や就職力の高さが志願者を集めています。一般的に3倍を超えると合格難度は高いとされますが、成蹊大学経営学部はそれを上回る水準であり、受験生にとっては十分な準備が必要となるでしょう。偏差値と倍率の両面から見ても、同大学内で比較的難関の学部として位置づけられます。
獨協大学経済学部の入試倍率は2.7倍で、成蹊大学経営学部と比べるとやや穏やかな競争率です。教育内容は幅広く、経済学の基礎から応用まで体系的に学べる環境が整っていますが、入試においては比較的取り組みやすい倍率であるため、多様な層の学生に門戸が開かれています。安定感のある教育と伝統を背景に、幅広い進路選択を可能とする学部として人気を維持しています。
他の大学群と比べると、日東駒専の経済・経営系学部は2倍から3倍程度の倍率が一般的であり、獨協大学経済学部の2.7倍はその範囲内に収まっています。一方でGMARCHの学部では4倍を超えることも珍しくなく、成蹊大学経営学部の4.9倍はGMARCHに迫る高倍率といえます。受験生は倍率の高さから生じる競争の厳しさを覚悟しつつ、どの環境で学ぶことを優先するかを考える必要があるでしょう。
卒業後の進路

有名企業の就職率
成蹊大学経営学部の有名企業就職率は21.6%で、私立大学の中でも高い水準を示しています。これは日東駒専の目安である10%前後を大きく上回り、GMARCHの20%前後に匹敵する数値です。企業連携授業やキャリア支援プログラムの充実が背景にあり、金融、メーカー、コンサルティングなど多様な業界で卒業生が活躍しています。新設学部でありながら既に大学全体のブランド力を反映した成果が現れており、将来的な伸びしろも期待できる環境です。
獨協大学経済学部の有名企業就職率は8.4%で、成蹊大学経営学部と比べると低い水準にあります。これは日東駒専の目安である10%前後と同等であり、一定の実績はあるものの有名企業就職を目指す場合は学内のサポートを積極的に活用する必要があります。ただし語学教育や国際交流に強みを持つ大学であるため、専門性を高めたり海外経験を積んだりすることでキャリア形成の幅を広げることが可能です。自ら主体的に進路を切り開く力が求められる環境といえるでしょう。
他の大学群と比べると、成蹊大学経営学部の21.6%はGMARCHに匹敵する高さで、就職面での強みを裏付けています。獨協大学経済学部の8.4%は日東駒専に近い水準にあり、進路選択の幅広さは担保しつつも、難関企業を狙う場合には努力や工夫が不可欠です。どの水準を目指すかによって、受験生の学び方やキャリア戦略が分かれる点が特徴的です。
主な就職先
スミセイ情報システム(4名)
NECソリューションイノベータ(2名)
千葉銀行(6名)
東京国税局(4名)
成蹊大学経営学部では上記の他に、金融業界や大手メーカー、情報通信関連企業など幅広い分野で卒業生が活躍しています。企業連携科目やインターンシップを通じて実務経験を積める仕組みが整っており、学生は在学中から社会で求められるスキルを体得することが可能です。こうした実践的教育の成果が、安定した就職実績として表れています。
獨協大学経済学部では上記の他に、地方銀行や中堅企業、サービス業界など地域や業界の多様な企業に卒業生を送り出しています。語学教育や国際交流を活かして海外企業や外資系企業に進む学生も見られ、キャリアの幅は広いといえます。大学の教育方針として、自ら主体的に進路を切り開く力を育成する点が就職活動にも反映されています。
他の大学群と比べると、日東駒専の就職先は地方金融機関や中堅企業が中心であり、獨協大学経済学部の傾向と重なる部分があります。GMARCHでは大手企業への就職実績が豊富であり、成蹊大学経営学部の就職傾向はそれに近い水準にあります。結果として、難関企業や有名企業を志向するなら成蹊大学経営学部、幅広い業界での就職を考えるなら獨協大学経済学部という棲み分けが見られます。
進学率
成蹊大学経営学部の進学率は1.1%で、大学院に進む学生は少数派ですが一定数存在しています。経営学の分野では実務経験を早期に積む学生が多い一方で、研究志向の学生は経営戦略や会計学、マーケティングなどを専門的に掘り下げるために大学院進学を選ぶ傾向があります。進学率が低めであることは就職市場での評価が高いことの裏返しともいえ、学部教育だけで社会に出る力を身につけられる点が強調されています。
獨協大学経済学部の進学率は0.3%で、非常に低い数値となっています。経済学部の学生の多くは学部卒業後に直接就職を選択し、大学院に進むケースはごく一部にとどまります。これは実学としての経済学を社会で即戦力として活かす意識が強いことを示しており、企業や公的機関など多様な就職先に直結している点が背景にあります。研究職や高度な専門職を目指す学生は少数派ですが、その分、就職実績の多さが際立っています。
他の大学群と比べると、日東駒専やGMARCHの経済・経営学部でも進学率は総じて低めで、1〜3%程度に収まることが多いです。成蹊大学経営学部の1.1%はその範囲内に位置しており、獨協大学経済学部の0.3%はさらに低い水準です。いずれも進学より就職を選ぶ傾向が強い点で共通しており、学部段階で社会での活躍を前提とした教育設計が反映されています。
留学生

受け入れ状況
成蹊大学経営学部の留学生数は79名で、学内には一定数の国際的な交流の機会が用意されています。経営学の授業では海外事例やグローバルビジネスを取り上げることが多く、留学生との協働を通じて国際感覚を養うことができます。英語での授業や国際交流プログラムも設けられており、経営学を学びながら実践的に異文化理解を深められる点が特徴です。留学生の存在はキャンパスの多様性を高め、グローバル社会で求められる柔軟性を育成する基盤となっています。
獨協大学経済学部の留学生数は45名で、成蹊大学経営学部と比べると少なめではありますが、語学教育に強みを持つ大学全体の特色から、授業やキャンパス内で国際交流の機会を得られる環境があります。経済学の学びと外国語教育を組み合わせることで、海外進出を視野に入れた学生にとって有益な経験となります。留学生数自体は多くはないものの、交流の密度を高めやすい規模であり、学生同士の距離感も近い点がメリットです。
他の大学群と比べると、日東駒専やGMARCHの経済・経営系学部では留学生数が数十名から百名前後であることが多く、成蹊大学経営学部の79名は十分に高い水準にあります。獨協大学経済学部の45名はそれに比べれば控えめですが、語学教育の強みを活かして国際的な体験を深めることができる点は大きな特徴です。どちらも国際感覚を養う環境を持ち、留学や海外キャリアを志向する学生にとって有益な場を提供しています。
海外提携校数
成蹊大学経営学部の海外提携校数は44校で、アジアや欧米を中心に多彩な大学と協定を結んでいます。交換留学や短期研修といったプログラムが整備されており、経営学の知識を国際的な文脈で学ぶことが可能です。提携校の多さは学生に幅広い選択肢を提供し、異文化理解や語学力向上を図るうえで大きな強みとなっています。特に経営分野では海外経験が就職活動にも直結するため、国際舞台での学びを志向する学生にとって大きな魅力を持つ学部です。
獨協大学経済学部の海外提携校数は59校で、成蹊大学経営学部を上回る数のネットワークを有しています。経済学の基礎や政策研究を国際的な視点から学ぶための交流が活発であり、学生は長期留学から短期プログラムまで幅広く活用できます。語学教育に強みを持つ大学全体の特色が背景にあり、海外大学との結びつきが進路やキャリア形成に直結する事例も少なくありません。より多くの提携先を持つことで、経済学の幅広いテーマに国際的にアプローチできる環境が整っています。
他の大学群と比べると、日東駒専やGMARCHでも数十校規模の提携先を有していますが、成蹊大学経営学部の44校は標準的な水準といえます。一方で獨協大学経済学部の59校はその水準を上回り、特に語学教育との相乗効果によって国際的な学びをより深められる点が強調されます。国際性を重視するかどうかが、志望先を決める際の重要な要素になるでしょう。
結局成蹊大学経営学部と獨協大学経済学部のどちらが良いか

成蹊大学経営学部は入学段階の学力水準が高く、偏差値66に加えて競争の厳しさを示す倍率4.9倍が志願者の選抜性を物語ります。卒業後の出口でも有名企業就職率21.6%が裏付けとなり、少人数の演習や企業連携科目、実践型の学びがキャリア形成へ直結しやすい構造です。国際交流の機会も活用しつつ、数理・データ・マネジメントの横断学修で「学力×実務」の両輪を磨ける点が強みで、受験前から入学後、就活に至るまで一貫した成長ストーリーを描きやすい学部といえます。
獨協大学経済学部は語学・国際交流の基盤が厚く、海外提携校数59校というネットワークの広さが学外経験の選択肢を押し広げます。加えて学生規模680名という大所帯を活かし、理論から実証、政策・国際まで関心の幅に応じた履修が取りやすいのが特色です。多様な学生同士の協働や語学を軸にした学びが相乗し、将来の進路選択で地域・業界の幅を持たせやすい環境が整備されています。国際志向や語学力強化を核に、経済学の基礎を厚く積み上げたい志望者と相性が良いでしょう。
他の大学群と比べると、偏差値の目安では日東駒専が55程度、GMARCHが62.5程度とされるなかで、成蹊大学経営学部の66はGMARCH基準を上回る位置づけ、獨協大学経済学部の60は日東駒専をしっかり超えるレンジに入ります。就職面の目安では日東駒専が10%前後、GMARCHが20%前後ですが、成蹊大学は有名企業就職率21.6%で上位帯の水準に達しています。難関就職を志向するなら成蹊、国際ネットワークを生かして学外経験を広げたいなら獨協という選び分けが明確です。