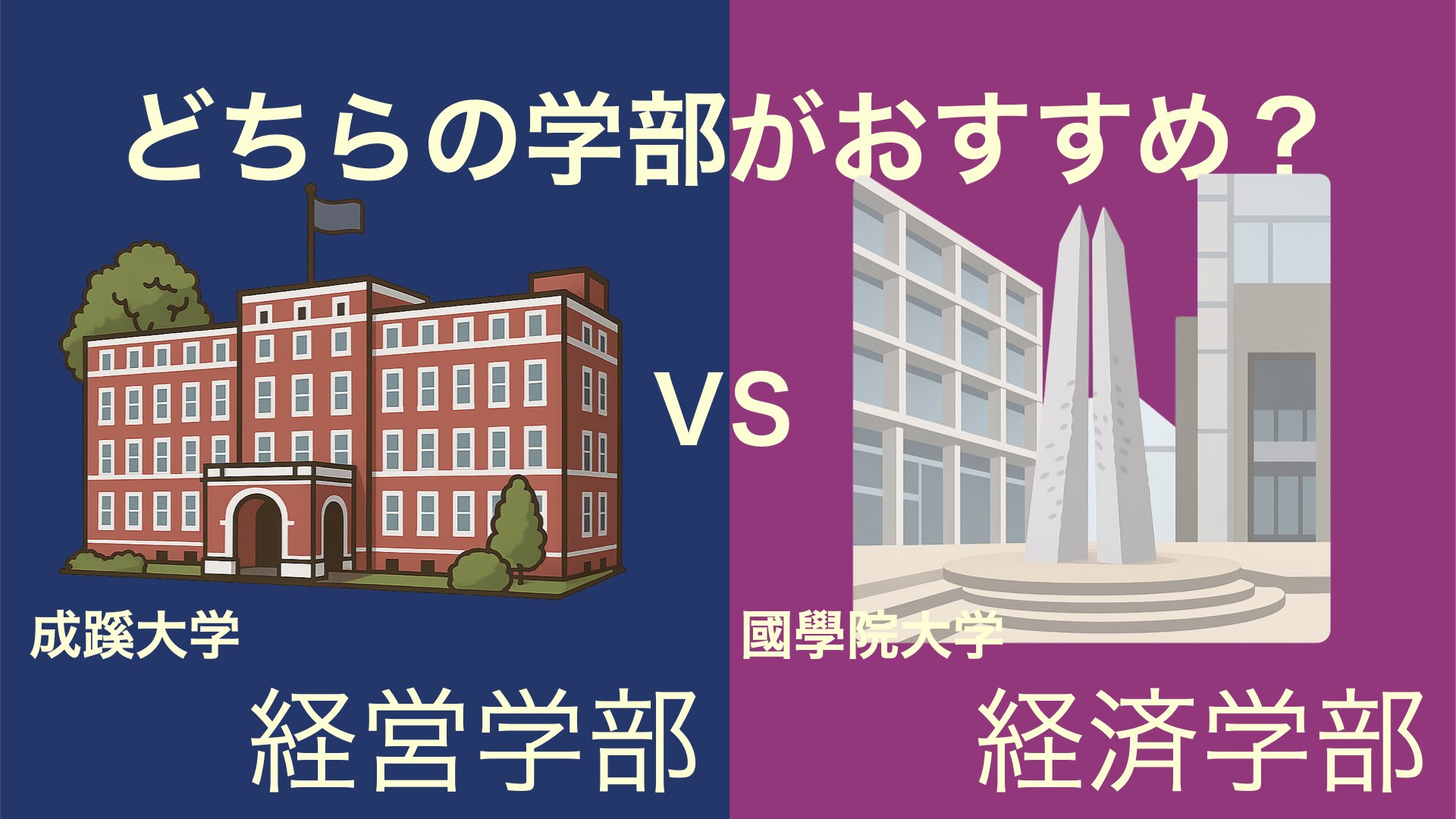成蹊大学経営学部と國學院大学経済学部はどんな大学?

基本情報
| 項目 | 成蹊大学経営学部 | 國學院大学経済学部 |
|---|---|---|
| 学部設立 | 2020年 | 1966年 |
| 所在地 | 東京都武蔵野市境南町1-1-1(吉祥寺駅) | 東京都渋谷区東4-10-28(渋谷駅) |
| 学部理念 | 人文科学、社会科学、自然科学及びこれらにまたがる幅広い視野 で思考・判断できる能力を有し、経営学の基礎的な概念と理論及び経営学の各専 門分野を理解していることに加え、国際文化や情報コミュニケーション技術に関 する知識をあわせ持つことで、企業や企業の経営活動に関する諸問題を柔軟かつ 適応的に解決できる実践的な総合マネジメント能力を修得した、職業人を養成するとともに、総合科学としての経営学を探求し、その研究成果を的確かつ明瞭に 発信することで社会に貢献することを目的とする。 | 経済学部は、多元化しグローバリゼーションの進展する社会の中にあって、経済学の基礎力と日本経済に関する知見を兼ね備え、未来への実践的で創造的な対応力を身につけた、社会に貢献できる専門的教養人を育成することを目的とする。 |
成蹊大学経営学部は2020年の創設以来、経営学の実学教育を柱に企業社会との連携を進めてきました。キャンパスは吉祥寺駅に位置しており、都心からのアクセスの良さが学生生活や就職活動における機動力を高めています。少人数教育やゼミ活動を重視し、理論と実務を結びつける科目が数多く用意されていることから、経営学を専門的に学びたい学生にとって環境が整った学部といえるでしょう。学部設立の歴史は比較的新しいものの、特色ある教育カリキュラムと立地の優位性が合わさり、学生にとって充実した学びの場を提供しています。
國學院大学経済学部は1966年に設立され、日本の伝統的な人文系大学の中で経済学の専門教育を担ってきました。所在地は渋谷駅で、落ち着いた学習環境と都心へのアクセス性を兼ね備えています。経済学の基礎理論を重視しつつも、現代社会の課題に即した教育内容を導入しており、伝統と革新を調和させた学部として評価されています。経済学を幅広く学ぶ中で、他学部や他分野との交流も可能であり、学際的な視点を養う機会も豊富に存在しています。
他の大学群と比べると、日東駒専の経済学部は戦後の高度経済成長期に多く設立され、地域社会に根差した教育を展開してきた歴史を持っています。一方、GMARCHの経済・経営学部は伝統とブランドを背景に長い歴史を築き、社会的評価も高いのが特徴です。これに対し、成蹊大学経営学部は実学的な経営教育を志向し、國學院大学経済学部は学問的伝統と文化的素養を基盤にしているため、両者の立ち位置は異なりつつも、それぞれが独自の教育理念と特色を持っているといえます。
大学の規模
成蹊大学経営学部の学生数は290名で、中規模の学部として少人数教育の利点を活かした学びを提供しています。教員と学生との距離が近く、ゼミ活動や演習において主体的に学ぶ環境が整えられており、学生一人ひとりの学習やキャリア形成に目が行き届きやすい規模といえます。また、人数が適度であることで施設利用の混雑も少なく、落ち着いた学修環境を維持できる点も特徴です。大学全体としても規模を抑えつつ教育資源を集中させる戦略が見られ、効率的に学生支援が行われています。
國學院大学経済学部の学生数は510名で、比較的大規模な構成となっています。講義科目の選択肢は幅広く、経済学の基礎から専門分野まで多様な学習機会が確保されているのが強みです。学生数の多さは交流関係の広がりや学外活動の活発さにつながり、人脈形成にも有利に働きます。一方で、大人数講義が中心になる場面もあり、学習への主体性やゼミでの密度ある学びをどう活かすかが重要となるでしょう。規模の大きさを強みに変えられる学生にとっては豊かな環境といえます。
他の大学群と比べると、日東駒専の経済・経営系学部は数千名規模の学生を抱えることも多く、講義や課外活動における人数の多さが特色です。GMARCHでも大規模な学部が一般的で、研究やゼミの選択肢は豊富になります。これに対して、成蹊大学経営学部は中規模ならではの少人数教育が強みであり、國學院大学経済学部は大規模ならではの多様性と選択肢の豊かさが際立ちます。学生数の規模は教育環境や交流機会に直結するため、どちらを重視するかで志望の方向性は異なるといえるでしょう。
男女の比率
成蹊大学経営学部の男女比は52 : 48であり、男女の比率がほぼ均衡している点が特徴です。男子学生と女子学生の割合に大きな偏りがないため、ゼミやグループワークにおいて多様な視点が交わりやすく、学習環境のバランスが良好です。男女双方が主体的に参加する雰囲気は、学びの幅を広げるだけでなく、就職活動や社会で必要とされる協働力を高める場にもつながります。均衡した割合は大学生活全般においてコミュニティ形成のしやすさをもたらし、安心して学べる環境が整っています。
國學院大学経済学部の男女比は67.7 : 32.3で、男子学生の割合が女子学生よりも高い傾向が見られます。この構成は経済学を志望する学生の関心や進路傾向を反映しており、男子学生が中心となる場面が多くなりやすい点が特徴です。ただし、女子学生が少数派であることが逆に積極的な意見発信の機会となる場合もあり、講義やゼミでは男女双方の視点を生かした議論が行われています。男女比の偏りはあるものの、それを強みに変える学びが可能です。
他の大学群と比べると、日東駒専の経済・経営系学部は男子学生の比率が高めである傾向が見られますが、女子学生の進学も増えており学内の多様性は拡大しています。GMARCHでは学部によって男女比が大きく異なり、経済系は男子学生が多数派になるケースが多い一方、商学部や国際系では女子学生の比率が高くなる傾向にあります。成蹊大学経営学部の均衡した比率は珍しい特徴であり、國學院大学経済学部は男子比率の高さが経済系学部としての一般的傾向を反映しているといえるでしょう。
初年度納入金
成蹊大学経営学部の初年度納入金は135.5万円で、教育内容や都心へのアクセス環境を踏まえると標準的な水準に位置しています。授業料に加えて施設費や諸経費が含まれるため一定の負担感はありますが、奨学金制度や学費減免措置なども整備されており、経済的支援を活用すれば学びの質を保ちながら負担を軽減できます。少人数教育やキャリア支援の体制が整っていることを考えると、費用に見合った教育効果を得やすい点が強みです。学費と教育資源のバランスの観点からも十分に評価できる環境といえるでしょう。
國學院大学経済学部の初年度納入金は126.7万円で、私立大学の経済系学部の中では比較的抑えられた水準となっています。費用を抑えつつも経済学の基礎から応用まで幅広く学べる教育体制が整備されており、費用対効果の高い学部といえます。また、学内外の奨学金制度や通学環境の利便性なども相まって、経済的な負担を意識しつつも充実した学修が可能です。教育資源の提供と費用面での配慮を兼ね備えた点が特色です。
他の大学群と比べると、日東駒専やGMARCHといった大学群では初年度納入金に幅がありますが、両学部の費用水準はその範囲内に位置しており、特段に突出して高いあるいは低いという状況ではありません。成蹊大学経営学部の135.5万円は教育資源の厚みを背景とした水準であり、國學院大学経済学部の126.7万円は負担を抑えた中で質の高い教育を実現している点が特徴です。両者は志望者の経済的条件や教育への投資観点に応じて選択肢となり得ます。
SNSでの評価
成蹊大学経営学部に関するSNSでの評価は、少人数教育による学びやすさや教員との距離の近さが好意的に取り上げられています。特にゼミ活動や課題解決型の授業に関して「実践的で役立つ」という声が多く、就職活動に直結する体験が得られる点が高評価です。一方でキャンパスがコンパクトであるため、クラブやサークル活動においては規模の大きな大学に比べて選択肢が限られるといった指摘も見られます。それでも落ち着いた雰囲気や学習環境に魅力を感じる受験生や在学生が多く、総じて肯定的な評価が優勢です。
國學院大学経済学部については、伝統ある大学の安心感や立地の利便性がSNS上で評価されています。特に文学部や法学部と並ぶ看板学部の一つとして認知されており、学内外からの信頼感を背景に「安定した学びができる」という印象を持たれているのが特徴です。ただし経済学部自体は大規模であるため、個別対応の手厚さを求める声や「もっと実務的なカリキュラムが欲しい」といった意見も散見されます。それでもキャンパスライフや人間関係の充実度は高く、バランスの取れた大学生活を望む学生から支持を得ています。
他の大学群と比べると、日東駒専の経済・経営系学部では「親しみやすい雰囲気」や「仲間づくりのしやすさ」といった点が話題になることが多く、SNSでもフレンドリーな印象が強調されます。これに対してGMARCHクラスでは、アカデミックな学習環境やブランドイメージの高さが強調され、受験生からの憧れを集めやすい傾向にあります。成蹊大学経営学部と國學院大学経済学部はそれぞれ中規模と大規模という違いから、SNS上での評価も異なりますが、いずれも学生生活の充実度や安心感が高く評価されている点は共通しています。
合格難易度(偏差値・倍率)

偏差値(マナビジョン)
成蹊大学経営学部の偏差値は66であり、受験生にとっては難易度の高い学部として位置づけられます。この数値は一般的な私立大学群と比較しても上位に属し、入学者の学力水準の高さを裏付けています。入試では基礎学力に加え、思考力や表現力を問う試験が行われるため、準備不足では合格が難しい環境です。学部での学修においても、優秀な学生が集まることで切磋琢磨できる学習環境が形成されており、学業や課外活動を通じて成長する機会が豊富に用意されています。高い偏差値が示す通り、入学後も高い学習意欲を求められるのが特徴です。
國學院大学経済学部の偏差値は66で、成蹊大学と比較すると僅差に位置しており、いずれも難易度の高い水準です。この偏差値は日東駒専クラスの大学群と比べて明確に高く、安定した学力層の学生を集めていることがわかります。入試においては基礎学力を問う問題を中心に、思考力を測る課題も含まれており、単なる暗記ではなく応用力を必要とする点が特徴です。受験生にとっては実力をしっかり発揮する準備が欠かせず、合格後も一定の学力レベルを前提とした授業が展開されています。
他の大学群と比べると、日東駒専の偏差値がおおむね55程度、GMARCHが62.5程度とされるなかで、成蹊大学経営学部の66と國學院大学経済学部の66はいずれもGMARCHの目安を上回る位置にあります。このことから両学部は学力面で難関大学群と同等以上の評価を得ており、入試における学力要求の高さが顕著です。つまり、受験生にとって両学部は日東駒専よりもはるかに高い壁であり、GMARCHと肩を並べる難易度を誇る選択肢といえます。
倍率
成蹊大学経営学部の倍率は4.9倍であり、比較的高い競争率が見られます。この数値は受験生の人気を反映しており、出願者数に対して合格者数が限られているため、入学を目指すには十分な学力と入念な準備が必要となります。偏差値と相まって、入試における難易度の高さがうかがえ、合格者層は学力的にも意欲的にも一定水準以上に保たれる傾向があります。倍率の高さは学部の評価や将来の就職力への期待を裏付けるものであり、成蹊大学経営学部のブランド価値を押し上げている要因といえます。
國學院大学経済学部の倍率は4.1倍で、成蹊大学経営学部と比べるとやや低めですが、それでも受験生にとっては十分に狭き門といえる数値です。適度な倍率は志願者にとって挑戦しやすさと合格の可能性のバランスを示しており、堅実な人気を集める要因となっています。大規模な学部であることも倍率に影響を与えており、学科の選択肢や教育体制の広がりと結びついています。競争率は高すぎず低すぎず、受験生にとって挑戦しやすい環境を形成しています。
他の大学群と比べると、日東駒専の経済・経営系学部はおおむね2〜3倍程度、GMARCHの学部では4〜6倍前後となるケースが多く見られます。これに照らすと、成蹊大学経営学部の4.9倍はGMARCH並みの難易度に匹敵し、國學院大学経済学部の4.1倍は日東駒専よりもやや高く安定した水準にあるといえます。両学部はそれぞれ異なる位置づけを持ちながらも、いずれも受験生にとって決して容易ではない選択肢であることが示されています。
卒業後の進路

有名企業の就職率
成蹊大学経営学部の有名企業就職率は21.6%で、全国的な水準から見ても高い割合を誇っています。この数値はGMARCHの目安である20%前後と同等であり、学部教育の実践性や企業とのネットワークが実を結んでいることを示しています。ゼミ活動やキャリア支援の充実度が反映されており、大手企業を志望する学生にとっては魅力的な環境です。教育内容と就職実績が結びついている点は学部選択の大きな決め手となります。
國學院大学経済学部の有名企業就職率は8.8%で、成蹊大学経営学部と比べると低めの水準にあります。この値は日東駒専の目安である10%前後に近く、堅実な進路選択をする学生が多いことを反映しています。必ずしも大企業志向ではなく、中小企業や公務員を含む幅広いキャリアに分散しているのが特徴です。教育の幅広さを生かし、多様な進路を歩む学生が多いことが見て取れます。
他の大学群と比べると、成蹊大学経営学部の21.6%はGMARCHと同等の高さを示し、國學院大学経済学部の8.8%は日東駒専の基準に近い値です。したがって、就職実績の観点では成蹊大学経営学部が優位に立ち、ブランド力や就職活動での強さを重視する受験生に向いています。一方で國學院大学経済学部は就職先の多様性を活かし、自分の志向に合わせて柔軟なキャリア形成を目指す学生に適しているといえるでしょう。
主な就職先
スミセイ情報システム(4名)
NECソリューションイノベータ(2名)
国家公務員(9名)
ニトリホールディングス(5名)
成蹊大学経営学部では有名企業就職率の高さに加え、金融、メーカー、情報通信など幅広い分野への就職実績が見られます。特に大手銀行や保険会社といった金融業界への進出が目立ち、ゼミや授業で培われる実践的な知識やネットワークが活かされています。さらにメーカーや商社、IT関連企業などでも存在感を示し、総合的なキャリア形成を支える環境が整っています。キャリアセンターのサポートも充実しており、学生が多様な進路を選べる点は強みといえるでしょう。
國學院大学経済学部では、金融や製造業を中心に安定した就職先が多く見られ、公務員や教育関連への進路も一定数存在しています。特に地方銀行や信用金庫など、地域社会に密着した金融機関への就職が目立ち、堅実なキャリア選択を志向する学生に合った環境を提供しています。また、製造業やサービス業など幅広い分野に人材を送り出しており、多様性を重んじたキャリア形成が可能です。安定志向の学生にとっては信頼できる進路実績を備えた学部です。
他の大学群と比べると、日東駒専の経済・経営学部では中小企業や地元志向の就職先が多く、地域社会に根差した進路を歩む学生が目立ちます。これに対してGMARCHの学部では大手企業や国家公務員といった全国的に評価の高い進路が中心となります。成蹊大学経営学部はGMARCHに近い有名企業就職実績を備え、國學院大学経済学部は日東駒専に近い堅実な進路傾向を持つため、就職先の性質やキャリアの方向性に応じて志望校を選ぶことが重要といえるでしょう。
進学率
成蹊大学経営学部の進学率は1.1%であり、多くの学生が学部卒業後にそのまま就職を選択する傾向が強く表れています。大学院進学を目指す学生は少数派ですが、研究志向の学生には大学院への進学支援が用意されており、専門性を深める道も確保されています。ただし大多数はキャリア教育や企業との結びつきを重視し、就職活動に軸足を置くのが特徴であり、就職実績の高さと連動しています。進学率が低いことは必ずしも不利ではなく、学部教育で得られる実践的スキルが就職市場で評価されていることの裏付けといえるでしょう。
國學院大学経済学部の進学率は1.4%で、成蹊大学経営学部と同様に極めて低い数値を示しています。これは経済学部の学生が大学院進学よりも就職を選ぶ傾向が強いことを反映しており、学部段階での学びが社会に直接結びついていることの証といえます。一方で、一部の学生は大学院や法科大学院、専門職大学院などに進むケースもあり、専門的な研究や資格取得を目指す道も確立されています。全体としては安定した就職志向が優勢です。
他の大学群と比べると、日東駒専やGMARCHの経済・経営系学部でも進学率は低めであり、多くの場合5%を下回る水準となります。そのなかで成蹊大学経営学部の1.1%と國學院大学経済学部の1.4%はいずれもさらに低い水準であり、両学部が実践的な就職重視型であることが明確です。進学よりも社会での即戦力を志向する学生に適した環境といえるでしょう。
留学生

受け入れ状況
成蹊大学経営学部の進学率は1.1%であり、多くの学生が学部卒業後にそのまま就職を選択する傾向が強く表れています。大学院進学を目指す学生は少数派ですが、研究志向の学生には大学院への進学支援が用意されており、専門性を深める道も確保されています。ただし大多数はキャリア教育や企業との結びつきを重視し、就職活動に軸足を置くのが特徴であり、就職実績の高さと連動しています。進学率が低いことは必ずしも不利ではなく、学部教育で得られる実践的スキルが就職市場で評価されていることの裏付けといえるでしょう。
國學院大学経済学部の進学率は1.4%で、成蹊大学経営学部と同様に極めて低い数値を示しています。これは経済学部の学生が大学院進学よりも就職を選ぶ傾向が強いことを反映しており、学部段階での学びが社会に直接結びついていることの証といえます。一方で、一部の学生は大学院や法科大学院、専門職大学院などに進むケースもあり、専門的な研究や資格取得を目指す道も確立されています。全体としては安定した就職志向が優勢です。
他の大学群と比べると、日東駒専やGMARCHの経済・経営系学部でも進学率は低めであり、多くの場合5%を下回る水準となります。そのなかで成蹊大学経営学部の1.1%と國學院大学経済学部の1.4%はいずれもさらに低い水準であり、両学部が実践的な就職重視型であることが明確です。進学よりも社会での即戦力を志向する学生に適した環境といえるでしょう。
海外提携校数
成蹊大学経営学部の海外提携校数は44校であり、比較的多くの大学と国際的なネットワークを構築しています。この提携関係は交換留学や短期研修など多様なプログラムに活用されており、在学生がグローバルな環境で学ぶ機会を広げています。特に経営学という学問分野において、国際的な視野を身につけることは将来のキャリア形成に大きなプラスとなり、実務的な能力を鍛える場としても機能しています。学内にとどまらず海外へと学びを広げたい学生にとって大きな魅力を持つ環境といえるでしょう。
國學院大学経済学部の海外提携校数は36校で、成蹊大学経営学部と比べるとやや少なめではありますが、安定した数を維持しています。提携先との交流を通じて語学力や異文化理解力を養う機会が提供されており、海外経験を重視する学生にとって十分な環境が整っています。経済学の学修に国際的な要素を組み込むことで、学部教育の幅を広げる役割を果たしています。
他の大学群と比べると、日東駒専の経済・経営系学部では提携校数が数十校規模にとどまることが多く、国際交流の幅は限定的です。これに対し、GMARCHクラスでは提携校数が増加し、積極的に海外派遣や共同研究が行われています。成蹊大学経営学部の44校という数値は中規模大学としては非常に充実した国際ネットワークを示し、國學院大学経済学部の36校も堅実な国際展開を反映しています。両者ともにグローバルな学習機会を備え、学生に広い選択肢を与えている点が評価できます。
結局成蹊大学経営学部と國學院大学経済学部のどちらが良いか

成蹊大学経営学部は偏差値66や有名企業就職率21.6%といった数値が示すように、入学難易度と就職実績の両面で強みを発揮しています。さらに留学生数79名や海外提携校44校の実績からも、国際性を重視した教育環境が整っていることがうかがえます。これらの特徴は学生にとって学びとキャリア形成をバランス良く実現する大きな要素となっています。
國學院大学経済学部は偏差値66に加え、海外提携校36校や留学生数40名といった国際性の要素が目を引きます。有名企業就職率8.8%は成蹊大学に比べて控えめですが、その分幅広い進路選択が可能であり、多様なキャリア形成を志向する学生に適した環境といえます。堅実な教育と国際的な学びを両立させる基盤を備えていることが強みです。
他の大学群と比べると、成蹊大学経営学部はGMARCHと同等水準の就職力を誇り、國學院大学経済学部は日東駒専に近い堅実な進路傾向を示しています。両者は進学率の低さに共通点を持ちながら、それぞれ異なる特色を備えており、就職実績や国際性を重視するなら成蹊大学、幅広い進路や学びの堅実さを評価するなら國學院大学を選ぶと良いでしょう。