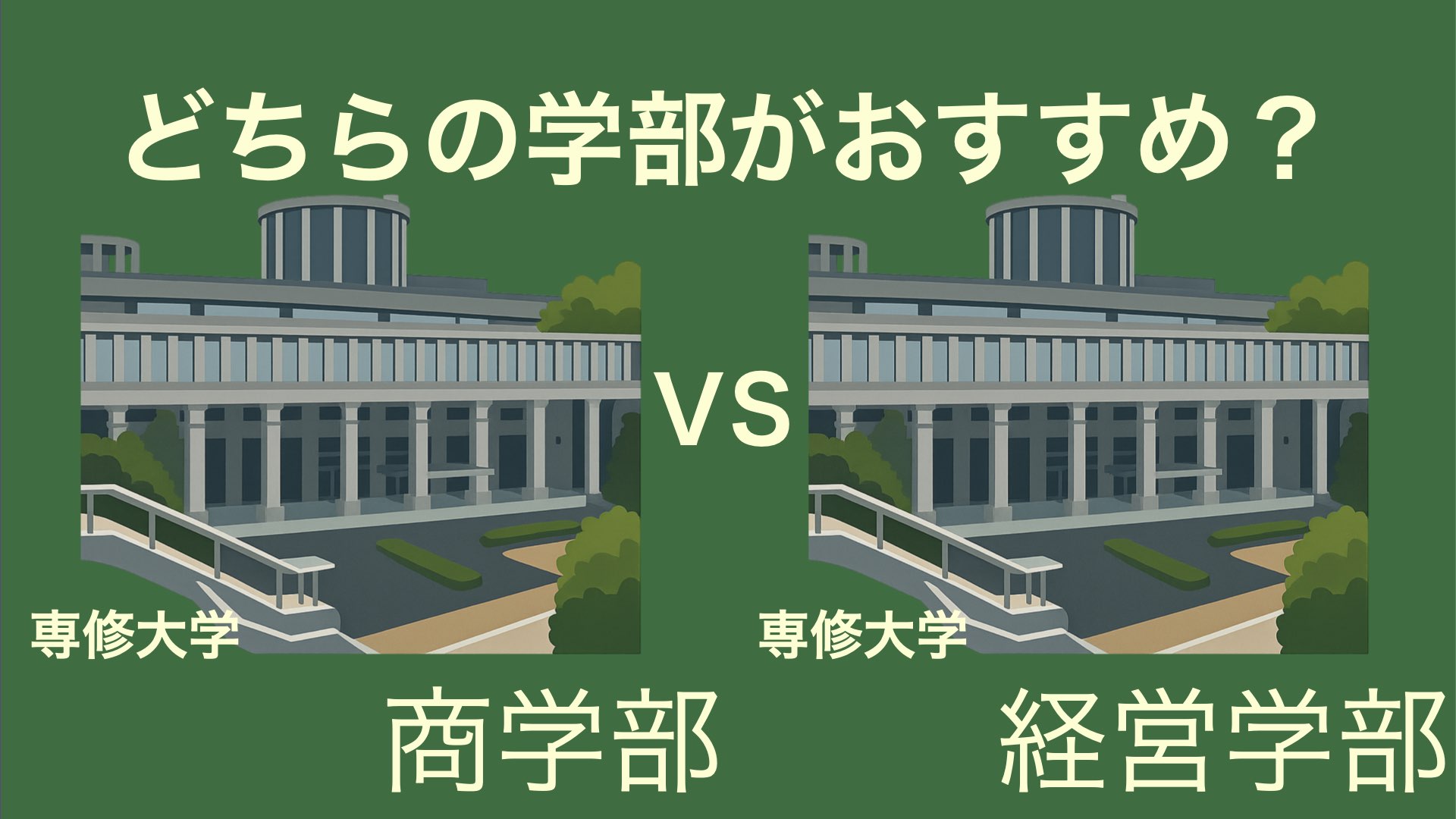専修大学商学部と専修大学経営学部はどんな大学?

基本情報
| 項目 | 専修大学商学部 | 専修大学経営学部 |
|---|---|---|
| 学部設立 | 1965年 | 1962年 |
| 所在地 | 東京都千代田区神田神保町3-8-5(神保町駅) | 神奈川県川崎市多摩区東三田2-1-1(生田駅) |
| 学部理念 | 専修大学商学部はビジネスに関わる「 ヒト」「モノ」「カネ」、そして「 情報 」の「 仕組み」を明らかにして、ビジネスに必要とされる実践的な知識や技術、倫理観および国際的視点について基礎から学習することを教育理念 としています。 | 経営学部は、経営学を構成する複数の学問領域を研究・教育することにより、経営に関わる諸問題に対する洞察力を有し、問題を解決する手段を創造的に考察し、その解決に向けて自主的に行動することができる人材を養成することを目的とする。 |
専修大学商学部は、学生数が648名と、専修大学内でも比較的大規模な学部のひとつに数えられます。学部生の多さは多様な交流の機会を提供し、授業やゼミにおける選択肢の広さにもつながっています。経済や経営といった近接分野との協働も盛んであり、他学部の学生と接する場面も多く、専修大学全体の学習環境の中で柔軟に学びを広げることが可能です。規模の大きさは就職活動や課外活動におけるネットワークの広さにも直結しており、多様な進路選択を後押ししています。
専修大学経営学部は、学生数が553名で、こちらも専修大学における主要学部の一つです。商学部に比べてやや規模は小さいものの、経営学という実学的なテーマを中心に据えた教育を展開し、学生同士のつながりが密接になりやすい点が特徴です。人数規模のバランスから、教授との距離も比較的近く、学習や研究へのフォローが受けやすい環境があります。またゼミ活動やケーススタディに重点を置くカリキュラムを展開しているため、実践的な学びに直結しやすいのも魅力のひとつです。
他の大学群と比べると、日東駒専レベルの大学群全体では商・経済・経営学部の学生数はいずれも数千人規模で、学部としての規模は大きいといえます。専修大学の商学部・経営学部はいずれも日東駒専の中で標準的な位置づけであり、学生数の多さから大学全体の雰囲気も活気に満ちています。これに対して、GMARCHクラスではより規模の大きな学部を有するケースも多く、学生数の観点からは専修大学は「中堅私大らしいバランス」といった評価に収まります。
大学の規模
専修大学商学部は、1965年に設立され、長い歴史を持つ学部の一つです。立地は都心からアクセスの良い神保町駅に位置し、交通の便の良さが学習環境を支えています。商学の基礎から応用に至る幅広いカリキュラムを提供し、専修大学の発展を牽引してきた伝統的な学部であり、ビジネスや会計、流通など多様な分野に対応する教育が整っています。
専修大学経営学部は、1962年に設置され、比較的新しいながらも実践的な経営教育を中心に発展してきました。キャンパスは生田駅に位置し、商学部と同じく首都圏からの通学利便性が高い点が魅力です。経営学部ではマネジメント理論や組織論、マーケティングなど現代社会で必要とされる実践的スキルを重視し、学生が社会に出て即戦力となることを目指した教育体系を展開しています。
他大学群と比べると、日東駒専に属する専修大学の学部は、いずれも明治期や戦後復興期に設立され、伝統を重視しながらも時代に即した学びを提供してきました。商学部は古くからの実績がある一方、経営学部は比較的新しい学部として実学的な要素を強めています。GMARCHの大学群と比較すると、学部設立の歴史はやや浅い部分もありますが、学生の学びやすさや立地条件においては十分に競争力を持っているといえます。
男女の比率
専修大学商学部は、男女比において56.5 : 43.5とされ、比較的バランスの取れた構成になっています。男子学生が多い傾向が見られるものの、女子学生も安定した割合を占めており、講義やゼミなどでは多様な視点から意見交換が行われています。このため、商学部の教育環境は性別に偏らず、多角的なビジネスの理解を育む点で有利に働いているといえます。
専修大学経営学部は、66.2 : 33.8という男女比を示しており、商学部と同様に男子学生が多めですが、女子学生の存在感も着実に高まっています。近年では経営分野への女性進出も目立ち、授業やグループワークでの多様性を反映した学びが広がっているのが特徴です。性別を問わず、リーダーシップやマネジメントスキルを身につける機会が提供されています。
他大学群と比べると、日東駒専に属する大学では、全体的に男子学生比率がやや高い傾向があります。商学や経営といった分野は依然として男性人気が根強い一方、女子学生の割合も徐々に拡大しています。GMARCHクラスの大学と比較すると、男女比の差は大きくなく、むしろ大学ごとの特色やカリキュラム内容に基づく学習環境の違いが目立つといえるでしょう。
初年度納入金
専修大学商学部の初年度納入金は、122.6万円とされています。これは私立大学の商学系学部としては標準的な水準で、学費面で極端な負担は生じにくい構造となっています。学費に対して提供される教育資源や施設環境は比較的充実しており、専門的なビジネス教育を受けられることを考えると、納得感のある投資といえるでしょう。
専修大学経営学部の初年度納入金は、122.6万円で、商学部と大きな差はありません。経営学という学際的な分野において、学費に見合った教育内容と就職支援体制が整っており、長期的なキャリア形成を視野に入れた学びを支援しています。同一大学内の学部間比較では、学費差よりも教育方針やカリキュラムの特色が重要な判断要素となります。
他大学群と比較すると、日東駒専に属する大学の商・経営学系学部は、おおむね初年度納入金が100万円前後に設定されています。これはGMARCHの同系統学部と比べると若干低めで、費用対効果を重視する学生や家庭には魅力的です。結果として、コストパフォーマンスを重視したい層には十分選択肢となる水準といえるでしょう。
SNSでの評価
専修大学商学部は、SNS上では「資格取得に向けた支援が充実している」「ゼミ活動が活発で学びやすい」といった声が見られます。一方で「課題が多く大変」と感じる学生もおり、主体的な学びを求める人には評価されやすい傾向があります。総じて、学びの環境や実践的な教育への取り組みについて好意的な意見が多く、安定した評価を得ています。
専修大学経営学部は、「実務に直結する授業が多く就職活動に役立つ」「企業とのつながりを感じられる」といった肯定的な評価がSNSで目立ちます。ただし「授業の難易度が幅広く、自己管理が必要」との声もあり、能動的に学びを深めたい学生に適していると言えます。キャリア意識の高い学生から特に支持されやすいのが特徴です。
日東駒専やGMARCHの類似学部と比較すると、商学部・経営学部いずれも学びの姿勢やキャリア形成支援に関して高評価を得やすく、学生の発信からは「努力すれば伸びやすい環境」という印象が伝わります。特にGMARCHと比べるとリソース面で劣る点はあるものの、学生が主体的に行動することで十分に補えると評価されています。
合格難易度(偏差値・倍率)

偏差値(マナビジョン)
専修大学商学部の偏差値は 59 です。商学は実務志向の人気領域で出願者が毎年安定しており、難易度は中堅上位帯で推移します。共通テスト利用や英語外部試験換算の方式を選ぶと優位に働くケースがあり、得点源の設計次第で合格可能性が大きく変わります。数学・簿記を強みにできる受験生は相性が良い学部です。また、学科間の出題傾向差は小さめで、基礎力の積み上げがそのまま得点に結びつきやすいのが特色です。
専修大学経営学部の偏差値は 57 です。企業経営やマーケティング志望の受験生が集中し、実務性の高さから出願人気は高水準です。方式によっては小論文や総合型で評価軸が広がるため、学力一本勝負に加えて活動実績や志望理由の完成度が結果を左右します。計数系が得意なら経営分析分野で強みを示しやすいです。過去問研究で問われやすい用語・事例の整理を進めると、安定して合格点を積み上げられます。
他の大学群と比べると、日東駒専のボリュームゾーンは偏差値55前後、GMARCHはおおむね62.5前後が目安です。専修の商・経営はいずれも日東駒専内で上位レンジに位置づき、方式選択や科目配点の相性で僅差が生まれます。数英で得点を取り切れる受験生は上振れを狙いやすく、総合型を活かせるなら経営がやや有利になる局面もあります。反対に標準化の影響を受けにくい記述主体の方式では、基礎の安定がより重要です。
倍率
専修大学商学部の倍率は 3.2 倍です。商学部は資格取得や実務系のカリキュラムが充実しているため出願数が多く、一般入試でも高い競争率を示すことがあります。特に共通テスト利用型は志望者が集まりやすく、倍率が上振れする傾向があります。ただし多様な方式が用意されているため、戦略的に受験方式を選べば合格のチャンスは広がります。過去問研究で出題傾向を把握し、得意科目を活かすのが重要です。
専修大学経営学部の倍率は 3.9 倍となっています。経営学部は経営戦略やマーケティングに関心のある受験生からの人気が高く、方式によっては特に高倍率を記録することがあります。小論文や推薦・総合型選抜を利用する層も厚く、学力試験一本での挑戦は相応の準備が必要です。経営学部独自の問題傾向に対応するため、基礎学力に加えて実例や時事知識を活用できると優位に立てます。
他大学群と比較すると、日東駒専全体の倍率はおおむね2〜3倍程度で安定していますが、専修は人気学部ではこれを上回ることが少なくありません。一方でGMARCHは全体として専修以上の高倍率を示すケースが多く、特に看板学部では5倍を超えることも珍しくありません。専修の商・経営は日東駒専の中では上位帯に属し、受験戦略次第で合格可能性を高められる位置にあります。
卒業後の進路

有名企業の就職率
専修大学商学部の有名企業就職率は 7.5%となっています。これは日東駒専グループの平均である10%前後と同程度であり、大手企業や金融業界への就職を果たす学生も一定数います。商学部は企業実務や会計、流通などに強みを持つため、商社や金融機関への就職を目指す学生にとっては環境が整っていますが、全体的には中小企業や地元企業への就職者が多数を占めています。
専修大学経営学部の有名企業就職率は 7.5%です。経営学部では経営戦略や人材マネジメント、情報システムなど幅広い知識を学ぶことができるため、就職先も製造業、サービス業、情報通信業など多岐にわたります。大企業への就職を実現する学生もいますが、比率としては商学部と同様に日東駒専水準に留まり、特定の業種に集中しているわけではありません。
他大学群と比較すると、日東駒専全体の有名企業就職率はおおむね10%前後であり、専修大学の両学部もその平均的な範囲に収まります。一方でGMARCHに進学すると20%前後まで数値が上がる傾向があり、学歴フィルターの影響もある程度見られます。そのため、専修大学で有名企業を目指す場合には、資格取得やインターンシップ参加など、学外での実績づくりが重要な差別化要因となります。
主な就職先
東京都特別区Ⅰ類(4名)
エン・ジャパン(4名)
レバレジーズ(3名)
船井総合研究所(3名)
専修大学商学部では上記の他に、金融機関や流通業界を中心に幅広い就職実績があります。特に地方銀行や信用金庫などの地域金融機関への就職が目立ち、安定志向の学生に人気があります。また、保険業界や商社系の中堅企業への進出も多く、営業職や事務系総合職としてキャリアをスタートさせる例が多く見られます。
専修大学経営学部では上記の他に、情報通信業やメーカー企業に就職する学生が比較的多い傾向にあります。特にIT関連の企業や中堅製造業への就職が目立ち、システム開発や経営管理部門での活躍が期待されています。また、卸売・小売業など幅広い分野での就職実績があり、経営学の知識を生かした企業運営や企画業務を担うケースも見られます。
日東駒専全体と比較すると、専修大学の就職実績は安定した傾向を示しており、特に商学部は金融機関、経営学部はITや製造業に強みがある点が特徴です。GMARCHに比べると大手企業への就職比率では劣るものの、幅広い中堅企業や地域経済を支える企業への就職機会が確保されており、安定的なキャリア形成が可能です。
進学率
専修大学商学部の進学率は 2.2%です。商学部は実学志向が強く、在学中から資格取得やインターンシップに力を入れる学生が多いため、大学院に進む割合は比較的低めです。多くの学生が学部卒業後に就職する道を選びますが、一部の学生は会計大学院やMBAなど専門性を高める大学院へ進学し、税理士や経営コンサルタントを目指す傾向もあります。
専修大学経営学部の進学率は 1.2%で、こちらも数値としては低めにとどまっています。経営学部の場合は学部卒業時点でのキャリア選択が中心であり、大学院進学者は経営学研究科やビジネススクールに進む少数派に限られます。特に研究志向よりも実務志向が強い学生が多く、就職活動に注力する傾向が際立っています。
他大学群と比べると、日東駒専全体では進学率が低いことが共通点であり、専修大学も例外ではありません。これに対し、GMARCH以上の大学では研究志向の強い学生が多く、大学院進学率も相対的に高めです。したがって専修大学で大学院進学を目指す場合には、明確な研究テーマや専門性の強化を意識し、早い段階から計画的に準備を進めることが重要になります。
留学生

受け入れ状況
専修大学全体では、385名の留学生を受け入れており、アジアや欧米からの学生が多く学んでいます。授業内で国際的な交流の機会があり、語学教育や留学生との協働活動も盛んに行われています。商学部や経営学部の学生も国際的な視点を自然に養うことができ、学内の多文化環境がキャリア形成に好影響を与えています。
同じ専修大学内の学部同士であるため、商学部と経営学部の間に大きな差は見られません。大学全体としての国際交流体制に依存するため、学部選びにおいては留学生数の違いは比較要素になりにくいといえます。両学部の学生は同様に、専修大学が提供する国際教育資源を活用可能です。
日東駒専全体では、留学生受け入れ数は数百名規模が一般的で、基準的な国際性を有しています。一方、GMARCHクラスになると千名規模の留学生を抱える大学もあり、国際交流の選択肢はさらに広がります。そのため、専修大学は日東駒専の中では標準的な位置づけにありつつ、上位校と比較すると規模や機会で差が見られるといえるでしょう。
海外提携校数
専修大学は海外に36校の提携大学を持ち、学生が交換留学や短期研修を通じて海外経験を積む機会を整えています。協定校はアジアを中心に欧米にも広がっており、語学力向上だけでなく異文化理解を深める環境が整備されています。商学部・経営学部の学生もこの制度を共通に利用でき、国際的な視野を広げることが可能です。
同じ大学内の学部比較であるため、商学部と経営学部の間に海外提携校数の差は見られません。専修大学全体の取り組みとして提供されるため、学部選択では大きな違いが出にくい点が特徴です。そのため、国際交流の観点からは学部ごとの差ではなく、大学の制度活用の姿勢が重要となります。
日東駒専全体では、提携校数は数十校規模であることが一般的で、専修大学も標準的な水準に位置づけられます。一方、GMARCHクラスになると百校以上の提携を有する大学も多く、留学先の幅や選択肢の豊富さにおいて優位性を持ちます。この点で専修大学は日東駒専の中で安定した国際交流環境を提供しつつ、上位群と比較すると機会の多様性に課題が残るといえるでしょう。
結局専修大学商学部と専修大学経営学部のどちらが良いか

専修大学商学部と経営学部を比較した場合、教育内容や国際交流制度の面では大学全体の共通資源を享受できるため、学部ごとの差異はあまり大きくありません。両学部とも安定した学生数を抱え、首都圏に拠点を持つことから通学利便性も良好です。入試難易度や倍率は日東駒専水準に収まり、幅広い受験生が挑戦しやすい環境にある点も共通しています。
違いが出るのは、商学部がマーケティングや会計など実務寄りの科目群を重視するのに対し、経営学部は組織運営やマネジメント理論に焦点を置く点です。これにより、卒業後の進路として、商学部は流通・金融・サービス業界に直結しやすく、経営学部は企業の総合職やマネジメント系の職種を意識する傾向が見られます。
大学群全体で見ると、専修大学はいずれの学部も日東駒専の中核を担っており、就職率や国際交流環境において標準的な評価を得ています。ただし、就職先の選択肢や海外協定校の数ではGMARCHに一歩譲る面があり、進路選択や国際経験の多様性を重視するなら上位群との違いを認識しておく必要があります。学部の方向性と将来のキャリア志向を照らし合わせて選ぶことが重要となるでしょう。