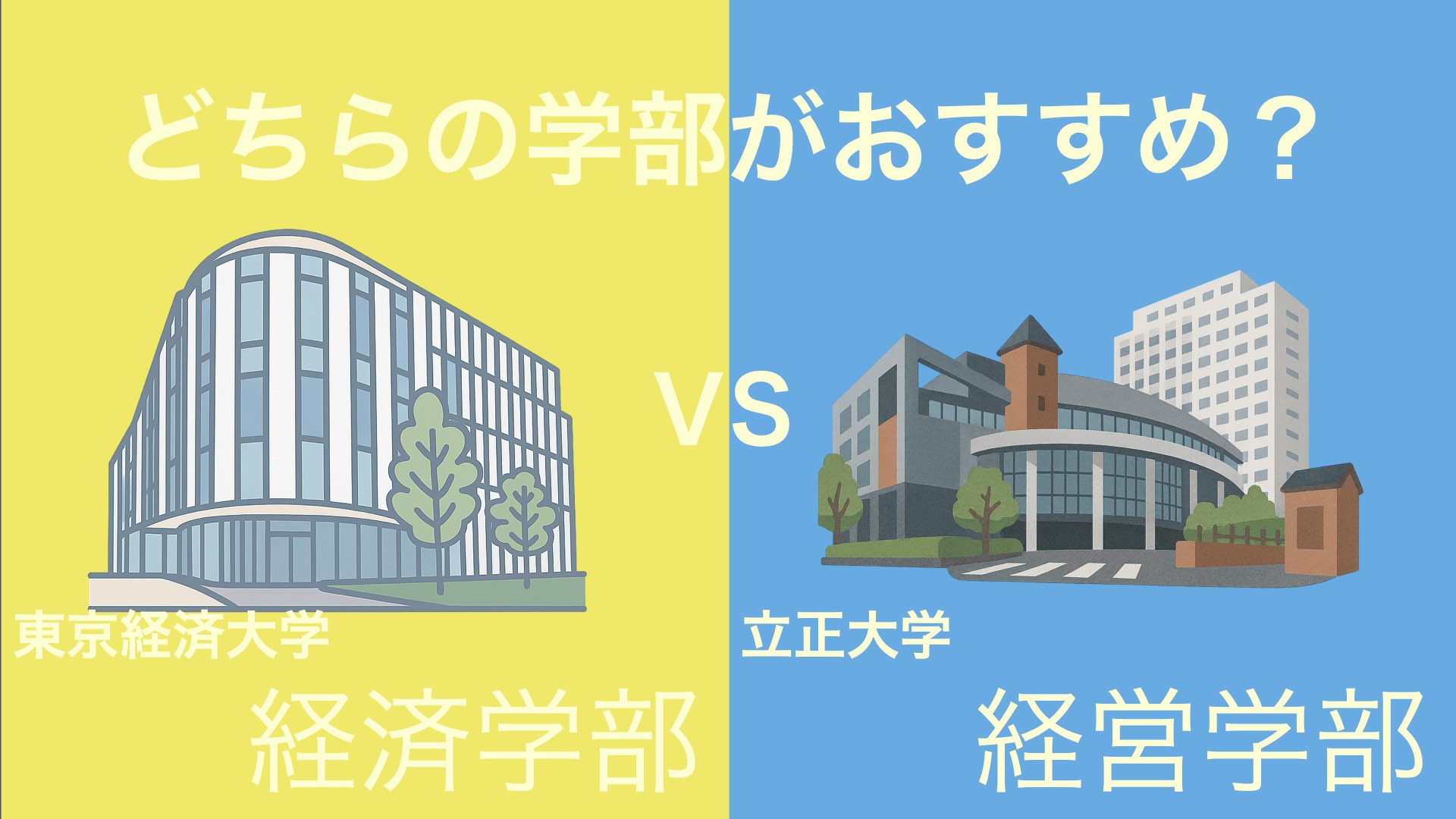東京経済大学経済学部と立正大学経営学部はどんな大学?

基本情報
| 項目 | 東京経済大学経済学部 | 立正大学経営学部 |
|---|---|---|
| 学部設立 | 1949年 | 1967年 |
| 所在地 | 東京都国分寺市南町1-7-34(国分寺駅) | 東京都品川区大崎4-2-16(大崎駅) |
| 学部理念 | 経済学部は、グローバル化の進展する経済社会における多様な諸問題を分析し、その解決に努め、以って国内外の様々な要請に応えて活躍できる、高度な専門的経済知識と倫理観を備えた良き市民、良き経済人を養成し、その基盤となる教育研究を推進する。 | 経営学部経営学科は、その学士課程教育プログラム(正課外のものも含む。)を通じ、持続可能でより良い豊かな和平社会を築くための一個の重心・芯となるべき人材として、経営学分野における「モラリスト×エキスパート」を養成することを教育の目標とします。 |
東京経済大学経済学部は、1949年に設立された伝統ある学部で、戦後の経済発展とともに歩んできた中堅私立大学の代表格です。東京都国分寺市南町に位置し、最寄り駅は国分寺駅。都心へのアクセスが良く、落ち着いた学習環境の中で理論と実証の両面から経済を学べる点が特徴です。
立正大学経営学部は、1967年に開設された経営系学部で、東京都品川区大崎にキャンパスを構えています。最寄り駅の大崎駅から徒歩圏内という利便性に優れ、実社会との接点を重視した教育を展開。「モラリスト×エキスパート」という理念のもと、倫理観を備えた実務家の育成に注力しています。
両学部とも首都圏の都市型キャンパスにあり、通学の利便性や実学志向のカリキュラムを強みとしています。東京経済大学が理論的な経済分析に重点を置くのに対し、立正大学は社会実践型の経営教育を展開している点に違いが見られます。
大学の規模
東京経済大学経済学部の在籍学生数は530名で、私立経済学部としては中規模の構成です。学生一人あたりの学習環境が比較的整っており、ゼミや演習などで教員との距離が近い点が特徴です。国分寺キャンパスは落ち着いた環境にあり、学業に集中しやすい雰囲気が評価されています。また、地域連携型の教育プログラムも多く、首都圏にありながらもアットホームな大学運営を実現しています。
立正大学経営学部の学生数は330名で、東京経済大学よりもややコンパクトな規模です。大崎キャンパスという都心立地ながら、少人数授業や個別指導を重視しており、学生が主体的に学べる体制が整っています。経営学を中心に実務的カリキュラムが多く、学外との連携も盛んで、就職活動期には早期から企業研究やインターンシップに参加する学生が多い傾向にあります。
両大学を比べると、東京経済大学は中規模の安定した学びの場を提供し、立正大学は小〜中規模で実践重視の教育体制を整えています。どちらも大人数化を避け、教員との距離を近く保つ教育方針が見られる点が共通しており、学びの深さを重視する学生に向いた環境といえます。
男女の比率
東京経済大学経済学部の男女比は81 : 19で、男子学生が全体の8割を超えており、経済系学部らしい男性中心の構成となっています。授業では政策分析や統計など数理的要素を含む科目が多いため、理論的思考を好む学生に人気があります。近年では女性の進学希望者も増加傾向にあり、ゼミや学外活動などで男女が協働する機会も広がっています。
立正大学経営学部の男女比は55 : 45で、男女比のバランスが比較的均等に近い点が特徴です。ビジネス実務やマネジメントを扱う講義が多く、女性の社会進出やキャリア形成を意識したカリキュラムが整えられています。都心キャンパスという立地もあり、女性学生の通学しやすさや生活環境の良さも支持されています。
全体として、東京経済大学は伝統的な男子中心の構成を保ちながらも多様性を取り入れ始めており、立正大学は性別に偏らない柔軟な学習環境を実現しています。学風としては、前者が理論的・分析型、後者が実務・協働型といった傾向が見られます。
初年度納入金
東京経済大学経済学部の初年度納入金は129.3万円で、首都圏私立大学の経済系学部としては標準的な水準です。学費の内訳には授業料のほか、教育充実費や施設費が含まれますが、全体的にコストパフォーマンスが高く、奨学金制度や学費分納制度も整備されています。加えて、家計支援を目的とした特待生・給付奨学金制度も利用しやすく、経済的に無理のない範囲で学業を続けられる点が魅力です。
立正大学経営学部の初年度納入金は137.7万円で、都心立地の私立大学としてはやや高めの設定です。最新設備を備えた大崎キャンパスでの学びや、実践的なキャリア教育、企業連携プログラムなどが充実しているため、学費に見合った教育内容を提供しています。また、学業優秀者を対象とした減免制度や、地方出身者向けの支援制度もあり、学びを支える体制は手厚いといえます。
両大学を比較すると、東京経済大学はコストを抑えつつ質の高い教育を提供する「堅実型」、立正大学は都心アクセスと実務教育を重視する「内容充実型」という違いが見られます。経済的負担を抑えたいか、教育環境の充実を重視するかによって適性が分かれるでしょう。
SNSでの評価
東京経済大学経済学部のSNSでの評価は、落ち着いた学風と面倒見の良さに関するコメントが多く見られます。X(旧Twitter)やInstagramなどでは「ゼミでの議論が活発」「教員が親身」「学生生活が穏やか」といった投稿が目立ち、派手さはないものの堅実で真面目な印象が浸透しています。いわゆる“地味だけどしっかりしている大学”という評価が定着しており、安心して学べる環境を重視する学生層から支持を得ています。一方で、課題が多いと感じる学生の声もあり、勉強量が一定以上求められる傾向にあります。
立正大学経営学部に対するSNSでの評価は、都心キャンパスの利便性と明るい学生気風を挙げる声が多いです。「アクセスが便利」「キャンパスが綺麗」「イベントが多い」といったコメントに加え、グループワークや実践型授業を楽しむ学生の発信も多く見られます。その一方で、授業の難易度は比較的易しいとする意見もあり、学生生活と学びのバランスを取りたい層に向いている印象です。
両大学を比較すると、東京経済大学は学問中心で落ち着いた雰囲気が強く、立正大学は社交的で実践志向の印象が目立ちます。真面目に学びたい学生は前者、キャンパスライフを重視する学生は後者を好む傾向が見られます。
合格難易度(偏差値・倍率)

偏差値(マナビジョン)
東京経済大学経済学部の偏差値は58で、日東駒専上位クラスに位置しています。特に経済分野においては理論と実証の両輪を重視した教育が評価され、国公立との併願先としても安定した人気を保っています。受験生の学力層は堅実で、学問志向の学生が多い点が特徴です。立地面でも東京都内ながら落ち着いた環境で、学問に専念したい受験生に向いています。近年は共通テスト利用型入試の比率も上昇しており、実力勝負の傾向が強まっています。
立正大学経営学部の偏差値は53で、首都圏私立大学の中堅層に位置します。経営・マーケティング・会計といった実践的分野を中心に、授業が体系的に構成されています。特にビジネス現場を意識したケーススタディや企業連携型授業が好評で、実務志向の受験生に支持されています。入試では科目数が比較的少なく、文系科目を得意とする学生にとって挑戦しやすい内容となっています。
両大学を比較すると、東京経済大学が学問重視・難易度やや高め、立正大学は実務型・中堅レベルでバランス型という印象です。偏差値面では東京経済大学が優勢であり、経済理論を深く学びたい受験生にはより適した選択といえるでしょう。
倍率
東京経済大学経済学部の倍率は2.9倍で、首都圏の中堅私立経済学部としては安定した難易度を保っています。経済学科では理論重視の教育を行うため、学力層も比較的高く、併願先として日東駒専上位層や国公立志望者が多いのが特徴です。共通テスト利用や英語外部試験利用など、多様な選抜形式が整っており、受験戦略の自由度が高いことも人気の一因です。実力派の受験生が集まりやすく、一定の競争性を維持しています。
立正大学経営学部の倍率は1.6倍とやや落ち着いた水準で、受験生の裾野が広い点が特徴です。入試方式の多様化により推薦・総合型選抜の比率が高く、一般選抜における倍率は穏やかです。志望者層としては首都圏の中堅大学を併願する学生が多く、アクセスや学費面のバランスで選ばれる傾向にあります。比較的受かりやすいとはいえ、経営系の学問に興味を持つ学生が集まる安定した人気学部です。
両大学を比較すると、倍率の面では東京経済大学の方がやや高く、受験生の集中度が高いといえます。難易度としては東京経済が日東駒専下位〜中位水準、立正は大東亜帝国上位に位置する印象です。どちらもアクセス良好な都市型キャンパスですが、学力層と競争性の点で東京経済にやや分があります。
卒業後の進路

有名企業の就職率
東京経済大学経済学部の有名企業就職率は6.8%で、日東駒専クラスの中堅私大としては堅実な実績を示しています。国家公務員や地方自治体職員、民間では金融・メーカー・流通業界など、安定志向の学生が多く、公務員就職支援講座などのキャリア支援も充実しています。OB・OGのネットワークを活かした就職サポート体制が整っており、中小企業を含めた実就職率の高さが特徴です。理論よりも実務を重視する学生層から一定の評価を得ています。
立正大学経営学部の有名企業就職率は0%と公表値が見られず、非公開または数値的に低い水準であることが推測されます。大学としては資格講座やキャリア支援体制を整備していますが、就職実績は専門職・中小企業・販売系などが中心となっています。経営学部として企業分析やマネジメント理論を学べる環境にあるものの、有名企業への就職という観点では課題が残ります。
両学を比較すると、実績の開示・支援体制・進路多様性の点で東京経済大学が明確に優位です。立正大学はアクセスや学びの幅に強みを持つ一方、就職実績の公表・向上が今後の課題となるでしょう。東京経済は日東駒専下位〜中位層に位置し、立正は大東亜帝国上位層と見るのが妥当です。
主な就職先
ニトリホールディングス(2名)
EY新日本有限責任監査法人(1名)
日立社会情報サービス(2名)
大和ハウス工業(2名)
東京経済大学経済学部では上記の就職先のほか、地元自治体や金融機関、商社などへの就職も多く見られます。公務員志望者が一定数存在し、経済産業省や埼玉県庁など、公共性の高い職種に就く卒業生も目立ちます。民間ではニトリホールディングスやEY新日本有限責任監査法人など大手企業への実績もあり、堅実な進路選択が特徴です。大学全体としてキャリア支援講座が整備されており、安定志向の学生に向いた進路形成が可能です。
立正大学経営学部では、公務員や大和ハウス工業、日立グループなど建設・情報・公共分野での就職実績があります。経営理論を実務へ応用する教育方針のもと、企業経営や流通分野への関心が高い学生が多い一方で、地元企業や中堅企業への就職が中心です。企業との接点は多いものの、OBネットワークや全国的なブランド力ではやや控えめな印象を受けます。
両学部を比較すると、東京経済大学は安定志向・実務型キャリア形成を支える教育体制が充実しているのに対し、立正大学は実学的な学びを提供しながらも就職先の規模・多様性では課題が見られます。全体として東京経済大学がより堅実で幅広い就職力を発揮しているといえます。
進学率
東京経済大学経済学部の進学率は3.4%で、日東駒専クラスの中では平均的な水準です。学部卒業後は大学院進学よりも就職を選択する学生が大半を占め、特に公務員志望者や金融・流通業界への就職志向が強い傾向にあります。経済分析や統計、会計の基礎を学んだ上で実務へ進む学生が多く、研究職や学術系に進む層はごく少数です。大学としてもキャリア教育を重視しており、進学よりも社会での即戦力育成に重点を置いています。
立正大学経営学部の進学率は2%で、東京経済大学よりもやや低い水準にあります。経営・会計・マーケティングなど実務系科目が中心であるため、学部卒業後に大学院へ進む学生は少なく、就職を最終目標とする学生が多いのが特徴です。進学希望者は主に経営学研究科や会計専門職大学院へ進みますが、割合としては限られています。
両校を比較すると、どちらも進学率は低く、キャリア志向が強い点で共通していますが、東京経済大学の方が進学率ではやや上回っており、学問的探究と実践的キャリアの両立が見られます。
留学生

受け入れ状況
東京経済大学経済学部の留学生数は100名で、全国平均と比べて中程度の受け入れ規模です。アジア諸国を中心に経済学を学ぶ留学生が在籍しており、授業内での交流や日本経済をテーマとした共同研究も一部で行われています。キャンパス全体としては国際交流の機会は限定的ですが、安定した受け入れ環境が整っています。
立正大学経営学部の留学生数は123名と、東京経済大学を上回る規模で、外国人学生との接点が比較的多いのが特徴です。特に経営や観光、マーケティングを志向するアジア圏の学生が多く、授業内ディスカッションや文化交流を通じて多様な視点を身につける機会が増えています。
両学部を比較すると、立正大学の方が留学生数では明確に多く、国際的な学習環境を体感しやすいといえます。一方で、東京経済大学は少人数ながらも安定した交流体制を維持しており、落ち着いた国際教育環境が特徴です。
海外提携校数
東京経済大学経済学部の海外提携校数は47校で、地方中堅私大としては標準的な規模です。アジア・欧州の大学を中心に学術協定を結び、短期研修や交換留学の機会を提供しています。学生数とのバランスを考えると、限られた人数でも国際経験を得やすい環境が整備されており、堅実な国際連携体制が見られます。
立正大学経営学部の提携校数は45校で、東京経済大学をやや上回る水準です。特にアジア圏との学術交流が盛んで、英語圏への留学支援制度も整っています。グローバル教育を重視する姿勢がカリキュラムにも反映されており、海外ビジネスへの関心が高い学生に適した環境といえます。
両校を比較すると、立正大学は提携先の数と地域多様性で優位に立ち、国際的な学びを推進する姿勢がより明確です。一方で、東京経済大学は安定した制度運営と少人数サポートの強さが特徴で、派手さよりも確実性を重視するタイプの国際教育を実践しています。
結局東京経済大学経済学部と立正大学経営学部のどちらが良いか

東京経済大学経済学部と立正大学経営学部を総合的に比較すると、学問の方向性・教育環境・国際性のいずれも明確な個性が見られます。東京経済大学は偏差値58と高く、就職率6.8%、進学率3.4%と安定したキャリア形成を支える堅実な実績を持っています。一方で立正大学は偏差値53であり、就職率0%、進学率2%と実務的教育による成果を上げています。
また、留学生数では東京経済大学が100名に対し、立正大学は123名と差があり、国際交流機会の多さでは立正が優位です。提携校数でも東京経済大学が47校、立正大学が45校と比較的拮抗していますが、立正大学は都市型キャンパスの特性を活かして海外との学術ネットワークを広げています。
総合すると、理論・分析を重視し堅実な経済教育を志すなら東京経済大学が向き、実務的・国際的な経営を学びたい学生には立正大学が適しています。どちらも安定した教育実績を持ちつつ、学びの方向性が明確に異なる点が選択の分かれ目となるでしょう。