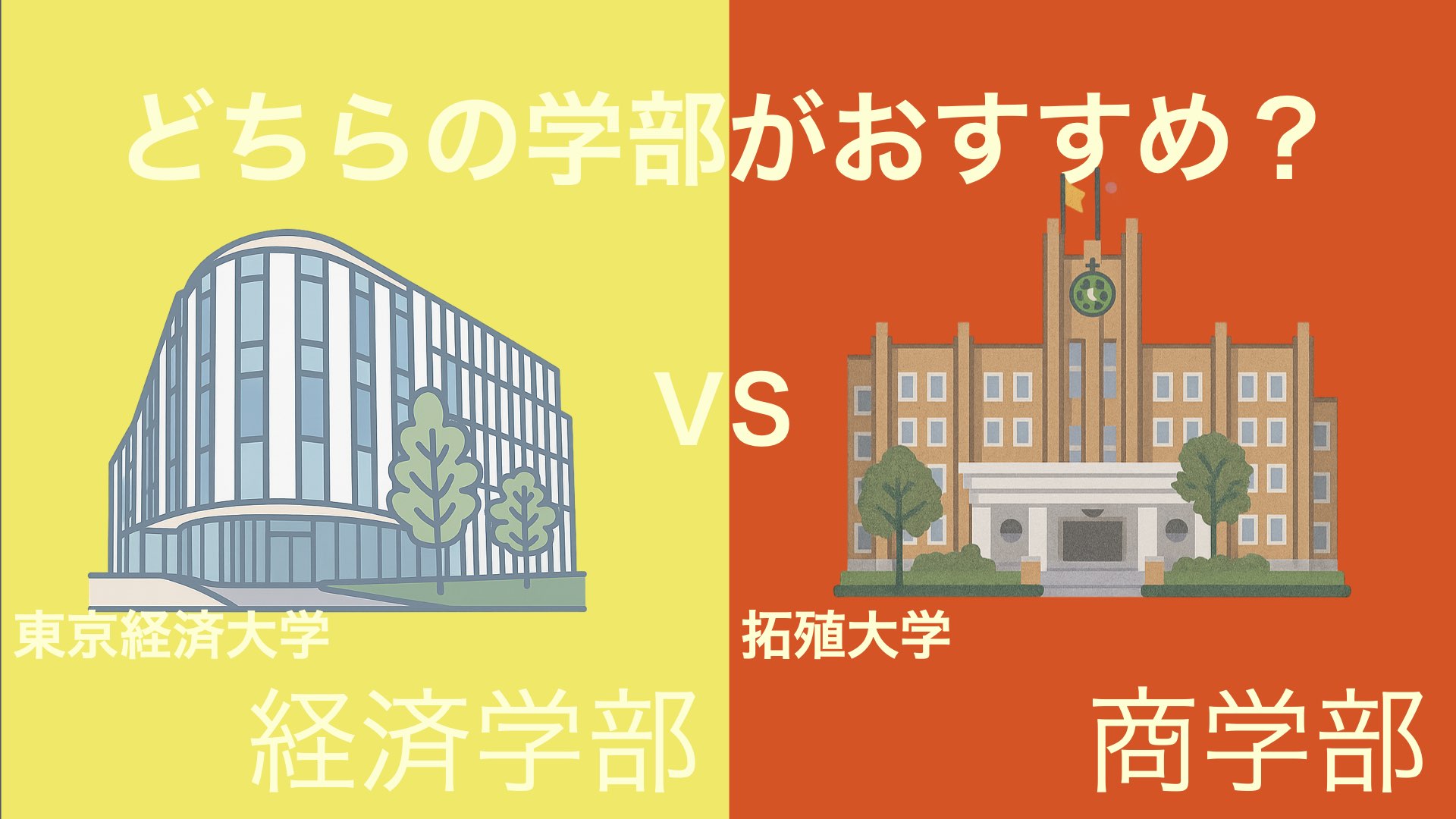東京経済大学経済学部と拓殖大学商学部はどんな大学?

基本情報
| 項目 | 東京経済大学経済学部 | 拓殖大学商学部 |
|---|---|---|
| 学部設立 | 1949年 | 1949年 |
| 所在地 | 東京都国分寺市南町1-7-34(国分寺駅) | 東京都文京区小日向3-4-14(茗荷谷駅) |
| 学部理念 | 経済学部は、グローバル化の進展する経済社会における多様な諸問題を分析し、その解決に努め、以って国内外の様々な要請に応えて活躍できる、高度な専門的経済知識と倫理観を備えた良き市民、良き経済人を養成し、その基盤となる教育研究を推進する。 | 会計・経営・情報・流通・国際ビジネス等の商学の諸分野における実学を身につけ、グローバル化の進むビジネス社会で活躍できる人材を育成する。 |
東京経済大学経済学部は、1949年に設立され、東京都国分寺市に位置するキャンパスを拠点としています。JR中央線の国分寺駅から徒歩圏内にあり、都心へのアクセスも良好です。経済理論とデータ分析を重視した実践教育が特徴で、少人数制のゼミを中心に経済学の基礎から応用まで体系的に学ぶことができます。地域経済との連携や学外活動も盛んで、学生が主体的に社会課題に取り組む機会が多い点も特徴です。
拓殖大学商学部は、1949年に設立され、東京都文京区の文京キャンパスおよび八王子キャンパスを拠点としています。最寄りの茗荷谷駅や高尾駅から通学が可能で、都心と郊外の両面に学習環境を持ちます。商学部では企業経営や国際ビジネスを中心に、経済・会計・マーケティングなど幅広い分野を学べるカリキュラムが用意されています。実務家教員による授業も多く、経営感覚を実践的に磨ける環境が整っています。
他の大学群と比べると、東京経済大学は大東亜帝国の中でも比較的少人数かつ実践志向の教育体制が整っている点が強みです。一方、拓殖大学は学生数が多く国際交流にも力を入れており、多文化的な環境を重視する学生に向いています。両校とも地域密着型の経済・商学教育を展開していますが、より研究志向で落ち着いた学びを求めるなら東京経済、実務志向や国際感覚を養いたいなら拓殖が適しているでしょう。
大学の規模
東京経済大学経済学部の学生数は530名で、比較的コンパクトな規模の学部です。教員との距離が近く、学生同士のつながりも強いため、ゼミやグループワークを通じた双方向的な学びが充実しています。少人数体制のため、授業参加や発言の機会も多く、経済理論の理解だけでなく論理的思考やプレゼンテーション能力を鍛えやすい環境が整っています。また、学生数の適度な規模は、学内の雰囲気を落ち着いたものにしており、アカデミックな学びに集中できることが特徴です。
拓殖大学商学部の学生数は645名と多く、大規模な商学部として活気ある学生生活が展開されています。学生数が多いことから、さまざまなバックグラウンドを持つ学生が集まり、互いに刺激し合いながら学べる環境が形成されています。授業やゼミの選択肢も豊富で、ビジネス、経営、会計などの分野ごとに専門性を高めることが可能です。一方で、授業によっては人数が多くなるため、主体的に発言・参加する姿勢が求められます。
他の大学群と比べると、東京経済大学のような中規模大学は、学習支援が行き届きやすく、個人指導を重視する点でメリットがあります。一方、拓殖大学のような大規模校では、多様な人材と交流し、社会的ネットワークを築きやすい環境が強みです。大東亜帝国レベルの大学群の中でも、東京経済は少人数教育型、拓殖はマンモス型の代表格として位置づけられるでしょう。
男女の比率
東京経済大学経済学部の男女比は81 : 19で、男性の比率が高い学部構成となっています。経済学という分野の特性上、数理的・分析的な志向を持つ学生が多く、男子学生が全体の8割を占める点が特徴です。ただし、近年ではデータ分析や金融リテラシーへの関心の高まりから、女子学生の入学も徐々に増加傾向にあります。男女ともに学習意欲が高く、ゼミ活動やインターンシップなどでの協働も盛んに行われています。
拓殖大学商学部の男女比は59 : 41で、こちらも男性が中心ですが、東京経済大学に比べるとややバランスが取れた構成です。特に商学部ではマーケティングや経営戦略など、コミュニケーション能力を重視する授業が多いため、女性の進出が目立ちます。学生生活においてもクラブ活動やゼミでの男女比の偏りが少なく、活発な意見交換が行われる環境です。
他の大学群と比べると、いずれの大学も日東駒専・大東亜帝国レベルに見られるような「男子中心型」の構成ですが、近年はどちらもジェンダーバランスが改善しつつあります。東京経済は伝統的な経済学志向が強く、堅実な男子学生が多い傾向に対し、拓殖は国際ビジネス系志向の学生層が多く、男女混在のダイナミックな雰囲気が感じられます。
初年度納入金
東京経済大学経済学部の初年度納入金は129.3万円で、私立文系大学の中でも標準的な水準に位置しています。授業料のほか施設費なども含まれていますが、全体としては学生への負担を抑えた設定となっています。特に経済学部では、授業やゼミ活動で使用する教材や統計ソフトなどが整備されており、学費に見合う学習環境が提供されています。また、東京経済大学独自の奨学金制度も充実しており、経済的な支援を受けながら安心して学べる点が評価されています。
拓殖大学商学部の初年度納入金は131万円で、東京経済大学とほぼ同水準にあります。学費に対して提供される教育の幅は広く、語学・会計・マーケティングなど多様な科目が学べることが特徴です。また、留学や資格取得支援制度も整っており、実践的な学びに資金が投じられています。奨学金制度も多様で、成績優秀者や経済的支援を必要とする学生を対象とした減免措置が設けられています。
他の大学群と比べると、東京経済・拓殖両大学ともに大東亜帝国レベルの中では平均的な学費水準です。早慶やMARCHのように高額ではない一方、施設面や教育内容の充実度は十分確保されています。コストパフォーマンスを重視して大学選びを行う学生にとっては、両校とも現実的かつ堅実な選択肢といえるでしょう。
SNSでの評価
東京経済大学経済学部のSNSでの評価を見ると、「落ち着いた環境で学びやすい」「面倒見が良い」といった声が多く見られます。キャンパスの雰囲気はアットホームで、学生と教職員の距離が近い点が好評です。特にゼミ活動や少人数授業での充実度が高く、学問的にじっくり取り組める点がSNS上でも評価されています。一方で、「派手さはないが堅実」「就職支援が丁寧」といったコメントが多く、華やかさよりも実務的・堅実な学びを重視する層に支持されている印象です。
拓殖大学商学部に関しては、「国際色が豊か」「留学生と交流できる環境がある」といったポジティブな投稿が多く見られます。海外志向の学生や語学学習を目的とする学生からの評価が高く、グローバルビジネスに興味を持つ層からの注目を集めています。ただし一方で、「授業の人数が多くややまとまりに欠ける」といった指摘もあり、学部の規模ゆえの課題も指摘されています。それでも全体としては明るく活発な印象が強く、行動的な学生に向いた環境といえるでしょう。
他の大学群と比べると、東京経済大学は大東亜帝国の中でも「真面目で堅実」、拓殖大学は「グローバル志向で活発」という対照的な評価を得ています。どちらも派手さよりも学びや雰囲気を重視する層に安定した人気があり、SNS上でも極端な賛否が少ない点が共通しています。
合格難易度(偏差値・倍率)

偏差値(マナビジョン)
東京経済大学経済学部の偏差値は58で、日東駒専クラスに近い中堅上位の水準に位置します。経済学部の中でも特にデータ分析や金融系の科目に強みを持ち、堅実な進学先として安定した人気を保っています。入試方式も多様で、一般選抜だけでなく共通テスト利用型や総合型選抜でも一定数の合格者を出しています。全体としては実力に見合った学生層が集まり、学業と就職のバランスを重視する層に選ばれる傾向があります。
拓殖大学商学部の偏差値は48で、大東亜帝国の中でも中位にあたる水準です。ビジネス実務や国際交流科目を幅広く提供していることから、英語力を活かした進路を志望する学生が多く集まります。入試難易度は東京経済大学に比べてやや易しめで、共通テスト利用入試でも比較的入りやすい傾向がありますが、内部での学習サポートが手厚く、入学後の成長が期待できる環境です。
他の大学群と比べると、東京経済大学は偏差値的に日東駒専のボーダーライン付近にあり、堅実な学力層を抱えています。一方の拓殖大学は大東亜帝国クラスの中核に位置し、幅広い層の学生を受け入れる姿勢が特徴です。入試難易度では東京経済が一歩上回るものの、両校とも学びの実践性やサポート体制を重視しており、偏差値だけで単純比較できない魅力を持っています。
倍率
東京経済大学経済学部の倍率(競争率)は2.9倍で、受験生の安定志向の高まりもあり、堅調な人気を維持しています。特に一般選抜では実質倍率が比較的落ち着いており、実力相応で挑みやすい大学として評価されています。一方で、共通テスト利用型では倍率がやや高く、学力上位層が安全校として併願するケースも見られます。合格ラインは偏差値に対して妥当な範囲にあり、堅実な受験層が多い印象です。
拓殖大学商学部の倍率は1.6倍で、東京経済大学よりもやや低めの傾向にあります。入試方式の多様化により受験生が分散していることもあり、実質倍率は落ち着いています。特に総合型選抜や学校推薦型選抜の比率が高く、一般入試での競争は比較的緩やかです。ただし、近年は国際ビジネス系の人気上昇により、一部コースでは志願者が増加する傾向も見られます。
他の大学群と比べると、東京経済大学の倍率は日東駒専と同水準、拓殖大学は大東亜帝国の平均的な難易度に近いです。全体として、両校とも入試の難易度が極端に高くない一方で、入学後の教育やサポートに定評があり、「入りやすくて学びが深い」大学として受験生に安定した人気を持っています。
卒業後の進路

有名企業の就職率
東京経済大学経済学部の有名企業就職率は6.8%です。学部単位で見ても実践的なキャリア教育を行っており、金融業界やメーカー、地方銀行など安定した業種への就職が多く見られます。OB・OGのネットワークを活かした求人も多く、地元企業や中堅上場企業への就職実績が堅調です。また、キャリア支援課のサポートが手厚く、早期からの就活ガイダンスや面接対策講座も充実しています。堅実で安定した就職力が同学部の特徴といえるでしょう。
拓殖大学商学部の有名企業就職率は3.9%です。数値上は東京経済大学を下回っており、大学全体として就職支援の成果がやや伸び悩んでいる印象です。ただし、国際的な学びを活かして貿易・物流・観光業界への就職実績が一定数あり、英語を武器にしたキャリア形成を志向する学生には適した環境です。なお、有名企業就職率のデータを公表していない年度もあり、全体像の把握にはやや不透明さが残る点は否めません。
他の大学群と比べると、東京経済大学は日東駒専に近い堅実な就職力を誇り、拓殖大学は大東亜帝国の中では平均的な水準といえます。特に東京経済は、地元企業や中小の有力企業への就職支援が行き届いており、学力と実務力のバランスが取れたキャリア実績を示しています。一方の拓殖は国際的な視野を活かせる職種への進出が目立ち、方向性の異なる強みを持つ両校といえます。
主な就職先
ニトリホールディングス(2名)
EY新日本有限責任監査法人(1名)
芝信用金庫(3名)
トヨタモビリティ東京(3名)
東京経済大学経済学部では上記のほかにも、地元の金融機関や保険会社、メーカー、IT関連企業など幅広い分野への就職実績があります。特に安定性を重視する学生が多く、都市銀行や地方銀行、損保・生保業界などへの内定も堅調です。大学のキャリア支援センターが主導する合同企業説明会や、OB・OG訪問制度が活発に行われており、中堅規模の優良企業に強いネットワークを築いています。また、資格取得支援講座を活用して公務員試験に挑む学生も一定数見られるのが特徴です。
拓殖大学商学部では上記のほかに、貿易・観光・物流業界への進出が目立ちます。特に国際ビジネス系のカリキュラムが充実しているため、商社・空運・海運・観光関連企業などに就職するケースが多く、語学力を活かしたキャリア形成が強みです。一方で、事務職や販売職など、実務経験を重ねてキャリアアップを狙う層も多く、幅広い職種に対応しています。学校推薦を活用した内定も多く、企業とのつながりの強さが際立っています。
他の大学群と比べると、東京経済大学は堅実な金融・メーカー志向、拓殖大学は国際系・実務志向という明確な傾向があります。どちらも大企業志向よりも「安定性」や「成長性」を重視する学生が多く、日東駒専〜大東亜帝国レベルの大学の中では、それぞれのカラーを活かした就職実績を築いているといえるでしょう。
進学率
東京経済大学経済学部の進学率は3.4%です。全体としては大学院進学者は少数派ですが、経済政策や公共経済学を専門的に学ぶために大学院へ進む学生も一定数存在します。進学先は主に東京経済大学大学院のほか、国公立大学の大学院への進学事例も見られます。進学希望者には少人数ゼミでの研究支援や教員の個別指導があり、学部で培った分析力をさらに高める環境が整っています。
拓殖大学商学部の進学率は3.2%です。大学院進学者は非常に少なく、学部卒業後は就職を選ぶ学生が圧倒的多数です。ただし、研究志向の学生は拓殖大学大学院商学研究科に進み、国際ビジネスや経営戦略分野をさらに深めています。全体としては実学重視のカリキュラムが中心であり、理論研究よりも実務能力を磨く方向に比重を置いているといえるでしょう。
他の大学群と比べると、両校の進学率は日東駒専や大東亜帝国の平均的な水準と大差ありません。東京経済大学は研究志向の学生が一定数存在するのに対し、拓殖大学はキャリア志向の学生が多く、どちらも「就職重視・進学補助型」の傾向を示しています。大学院進学率自体は低いものの、実務を意識した教育環境がその理由の一つと考えられます。
留学生

受け入れ状況
東京経済大学の留学生数は100名です。学生総数に対して比率は高くはありませんが、アジア諸国を中心とした学生が多く在籍しており、キャンパス内では多文化交流イベントや語学サポートプログラムが定期的に実施されています。経済学部では国際経済やグローバルビジネスに関連する授業も整備されており、留学生との共同プロジェクトやディスカッションの機会がある点も特徴的です。全体としては規模の割に国際的な学びを体験できる環境といえます。
拓殖大学の留学生数は1315名です。国内でも屈指の国際交流大学として知られており、アジア諸国を中心に多数の留学生が在籍しています。特に商学部では国際経営・貿易を専門とする授業や外国語教育が充実しており、学内の共修授業を通じて日本人学生と留学生が自然に交流する仕組みが確立されています。留学生支援センターも整っており、文化的・生活的サポートも手厚い環境が整っています。
他の大学群と比べると、東京経済大学は「少数精鋭型」、拓殖大学は「多国籍共修型」といえる国際環境を持っています。いずれも大東亜帝国クラスの中では留学生比率が比較的高く、特に拓殖大学は国際志向の学生に強い人気を誇っています。東京経済大学も少人数ながら質の高い国際教育を提供しており、規模よりも実質的な学びを重視する姿勢が見られます。
海外提携校数
東京経済大学の海外提携校数は47校です。提携先は主にアジア・欧米の大学で、学生交換や短期語学研修、オンライン交流プログラムなどを通じて国際的な視野を広げる機会が設けられています。特に経済学部では、アジアの新興経済国との連携プログラムが多く、国際経済の実態を現地で学ぶ短期派遣も人気があります。小規模ながらも実践的な国際教育に力を入れており、留学希望者へのサポート体制も整っています。
拓殖大学の海外提携校数は56校と非常に多く、国内でも屈指の国際ネットワークを誇ります。アジアだけでなく欧米・中東・アフリカなど世界各地に交流先を持ち、長期交換留学から短期研修まで幅広いプログラムを展開しています。商学部では特に「海外ビジネス実務」などの実践型留学が人気で、語学力のみならず国際感覚を磨く機会として高い評価を受けています。学内でも国際交流イベントが多く、留学生との連携が自然に行える環境です。
他の大学群と比べると、東京経済大学は質重視・選抜型の国際交流、拓殖大学は量とネットワークを重視したグローバル展開が特徴です。どちらも大東亜帝国レベルの大学群の中では国際性の高さが際立ち、実践的なグローバル教育を志す学生にとって魅力的な選択肢といえるでしょう。
結局東京経済大学経済学部と拓殖大学商学部のどちらが良いか

東京経済大学経済学部は、偏差値58、実就職率6.8%、海外提携校47校といったデータからもわかるように、堅実で実務志向の教育を重視しています。規模は中程度ながらも、経済理論と社会実践を結びつけるカリキュラム構成が特徴であり、就職面では安定感のある企業就職を実現しています。国際交流の数は控えめですが、内容は濃く、少人数で丁寧な教育方針が際立っています。
拓殖大学商学部は、偏差値48、海外提携校56校、留学生数1315名という数値からも明らかなように、国際性の強さが際立つ大学です。国内外に広がるネットワークを活かしたグローバル教育が特徴で、特に商学部は実践的なビジネス教育と外国語教育を融合させたプログラムを展開しています。一方で、就職率の公表がない点からも、進路データの透明性には改善の余地があります。
両校を比較すると、東京経済大学は「堅実な学びと安定した就職」、拓殖大学は「広い国際ネットワークとグローバル志向」という明確な強みを持っています。日東駒専よりやや下の偏差値帯に属しながらも、いずれも実学重視・社会連携型の教育を展開しており、国内志向の学生は東京経済、国際志向の学生は拓殖を選ぶ傾向が見られます。