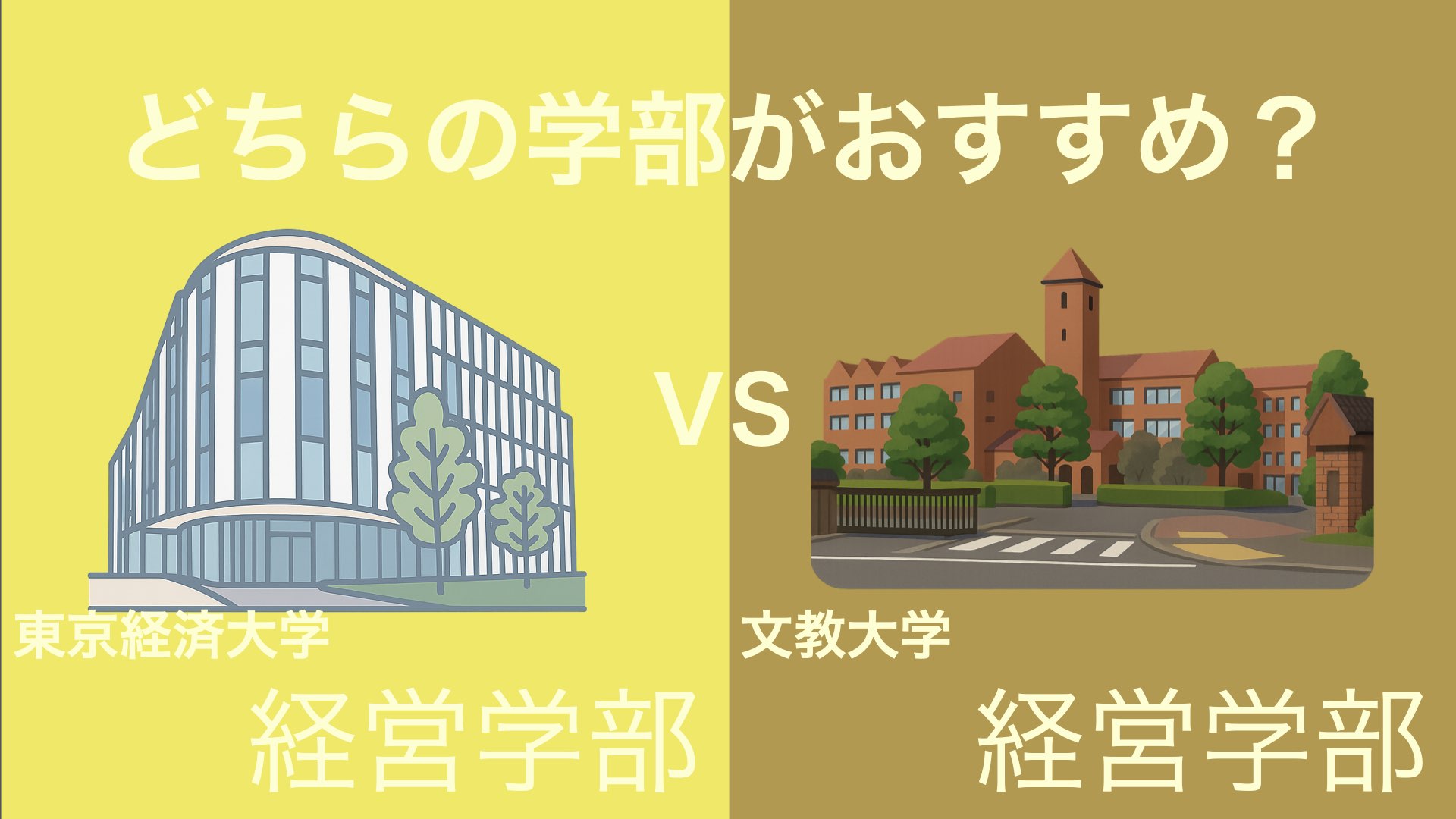東京経済大学経営学部と文教大学経営学部はどんな大学?

基本情報
| 項目 | 東京経済大学経営学部 | 文教大学経営学部 |
|---|---|---|
| 学部設立 | 1964年 | 2014年 |
| 所在地 | 東京都国分寺市南町1-7-34(国分寺駅) | 埼玉県越谷市南越谷1-5-30(南越谷駅) |
| 学部理念 | 経営学部は、変転著しい企業社会が直面する多様な諸問題を分析し、その解決に努め、以って将来にわたって様々な要請に応えて活躍できる、高度な専門的経営知識と倫理観を備えた良き市民、良き企業人を養成し、その基盤となる教育研究を推進する。 | 「人を活かす」人間尊重の経営を実践する自立型の人材を育成します。数多くの体験をとおし、ときには失敗から学ぶことで、成功するために何をなすべきかを自分でみつけることができるマネジメント能力を養います。実社会から学び体験することで、他者をリスペクトしつつ目的を遂行する確かな力を身につけます。 |
東京経済大学経済学部は1949年に設置され、東京都国分寺市南町1-7-34 にキャンパスを構えています。最寄り駅は 国分寺駅 で、落ち着いた住宅街に位置しているため、穏やかな環境で学問に集中しやすい点が特徴です。学部としては経済理論・公共政策・データ分析など学びの範囲が広く、「良き市民・良き経済人」を育成するという建学理念にもとづいた実証的な教育が行われています。長い歴史のある学部であり、ゼミ活動や少人数教育も安定した体制の中で運営されている点が強みです。
文教大学経営学部は比較的新しい学部で、東京都国分寺市南町1-7-34 に位置し、最寄り駅は 国分寺駅 です。駅から徒歩圏内で通いやすい立地ではあるものの、都心直結型キャンパスというよりは「郊外で落ち着いて学べる環境」に近い性格を持っています。「人を活かす経営」をテーマとし、体験学習・演習・グループワークを重視した実践的カリキュラムが特徴で、失敗から学ぶプロセスを組み込んだ授業設計が評価されています。学部が新しい分だけ、柔軟なカリキュラム構成が導入されている点も特色です。
両校を比較すると、東京経済大学は「歴史ある経済学教育を落ち着いた環境で体系的に学べる大学」、文教大学は「体験型・実践型の経営教育を郊外の静かな環境で展開する大学」という違いが明確です。理論と実証を軸に経済の仕組みを深く理解したい場合は東京経済大学、マネジメント能力や実務的スキルを実践的に高めたい場合は文教大学が適していると言えます。
大学の規模
東京経済大学経済学部の在籍学生数は 565 名で、中規模規模の学部として安定した人数構成になっています。この規模感により、授業やゼミでのコミュニケーションが取りやすく、教員との距離も適度に近い環境が確保されています。学内には文系学部が集まっているため、経済学に関連した科目や隣接分野の学びにアクセスしやすいのも特徴で、学生にとっては「大規模すぎず、小規模すぎず」のバランスが取りやすい環境と言えます。
文教大学経営学部の在籍学生数は 565 名で、小規模学部としての特徴がはっきりと表れています。少人数クラスを中心に運営されるため、学生間や教員との距離が近く、体験学習や演習を主体とした授業が実施しやすい規模感です。特に新しい学部であることから、学科運営や授業内容が柔軟に設計されており、学生一人ひとりの成長を細かくフォローしやすいという利点があります。このコンパクトさは実践型カリキュラムとの相性も良く、学びの密度が高まりやすい環境です。
両校を比較すると、東京経済大学は「中規模で比較的広いコミュニティの中で落ち着いて学べる大学」であり、文教大学は「小規模で丁寧な個別指導を受けられる大学」という構図が見えてきます。幅広い学生層の中で視野を広げたい場合は東京経済大学、少人数で教員との関わりを密にしながら学びたい場合は文教大学が向いていると考えられます。
男女の比率
東京経済大学経済学部の男女比は 68 : 32 で、全体として男性学生が大きく上回る構成になっています。経済学部は全国的に見ても男性比率が高くなりやすい傾向がありますが、東京経済大学もその典型的なパターンに当てはまります。講義やゼミでは多様な価値観を持つ学生が集まっているものの、学部全体の雰囲気としては落ち着いており、学修中心の過ごし方を重視する学生にとって馴染みやすい構成です。女性比率が低めである点については、少数派としてのサポートや安心感を得られる環境整備が進んでおり、特別に不利が生じる印象はありません。
文教大学経営学部の男女比は 68 : 32 で、比較的バランスの取れた構成となっています。経営学部としては女性比率が一定程度確保されている点が特徴で、体験型授業やグループワークが多い同学部では、男女双方の視点が自然に混ざり合う学修環境が形成されています。新しい学部であることも相まって、多様な学生を受け入れやすい雰囲気があり、男女を問わず意見を交換しながら学べる空気が整っています。また、小規模学部である特性上、教員が学生一人ひとりに気を配りやすく、学修面でも生活面でも相談しやすいのが強みです。
両校を比較すると、東京経済大学は男性比率が高く、文教大学は男女比がより均衡している点が大きな違いとして挙げられます。キャンパスの雰囲気においても、この男女構成の違いは影響を与え、落ち着いた男性中心のコミュニティが好みなら東京経済大学、男女双方の視点が入り混じる対話的な学修環境を求めるなら文教大学が向いていると判断できます。
初年度納入金
東京経済大学経済学部の初年度納入金は 129.3 となっており、私立経済系学部としては平均的な水準に位置しています。授業料・施設費などの基本構成に大きな特徴はないものの、学部として提供されている学修環境やキャリア支援を踏まえると、費用対効果は比較的安定しています。また、キャンパスの立地が国分寺という点も見逃せず、都心に近いながらも住環境が良いため、通学コストや生活コストのバランスがとりやすいのも強みの一つです。費用面と通学利便性を重視しつつ、落ち着いた環境で学びたい学生にとっては納得感のある金額といえます。
文教大学経営学部の初年度納入金は 129.3 で、こちらも私立文系として標準的な範囲に収まっています。学部が比較的新しいこともあり、最新の設備を用いた授業や体験型のプログラムが積極的に導入されている点が特徴です。南越谷駅から徒歩圏内というアクセスの良さも相まって、キャンパス外での活動やアルバイトとの両立もしやすく、費用の使われ方がわかりやすい構造と言えます。少人数教育の傾向が強い学部であるため、個別支援が受けやすい点も費用面の価値を高めています。
両校を比較すると、初年度納入金には大きな開きはなく、どちらも私立文系の一般的な範囲に収まっています。そのため、費用そのものよりも、キャンパス立地・学部の教育スタイル・学生規模といった周辺条件の違いが選択のポイントになりやすいです。生活面や通学環境まで含めて総合的に考えることで、自身により適した投資先を見極めやすくなるでしょう。
SNSでの評価
東京経済大学経済学部に関するSNSでの印象は、「落ち着いた雰囲気で学業に集中しやすい」「国分寺という立地が意外と便利」といった声が比較的多く見られます。規模が大きすぎない分、学生生活の距離感が心地よいという評価も一定数あり、アットホームな環境を好む学生からは好意的に受け取られています。一方で、派手さや話題性の強い大学ではないため、SNS上では大規模校と比べて情報量が多いわけではなく、地に足のついた印象が中心です。学業面や資格取得のサポートに関する投稿の比率が高く、落ち着いて大学生活を送りたいタイプの学生に支持されている傾向があります。
文教大学経営学部についてのSNS評価は、「キャンパスが清潔で新しい」「南越谷駅に近くアクセスが良い」といった実利的なコメントが目立ちます。特に通学しやすさに関しては高評価が多く、アルバイトや課外活動との両立面でポジティブな投稿が散見されます。また、学生規模が小さめであることから、教員や学生同士の距離が近いと感じる投稿も見られます。ただし、大学全体としてSNSでの話題性が突出して高いわけではなく、地域密着型の落ち着いた雰囲気がそのままオンライン上の印象にも反映されている点が特徴です。
両校を比較すると、SNSでの露出量や話題性はどちらも控えめですが、東京経済大学は「落ち着いた学修環境」、文教大学は「生活利便性とアクセスの良さ」といったポイントで評価が分かれる傾向があります。どちらも極端な意見は少なく、実際のキャンパス暮らしに即したリアルな投稿が多いため、大学生活の雰囲気を事前に把握しやすい点が共通の強みと言えます。つつ
合格難易度(偏差値・倍率)

偏差値(マナビジョン)
東京経済大学経済学部の偏差値は 58 を示しており、首都圏の中堅私大経済系では安定した水準といえます。キャンパスの環境や学部の専門性などを踏まえると、受験生が幅広く挑戦しやすい偏差値帯に位置しており、難易度は中程度ながらも確かな学習基盤を求める層に適したポジションにあります。入試方式も複数あり、得意科目を活かして得点戦略を立てやすい点も受験生にとってはメリットになりやすく、総合的には標準レベルの準備で十分に合格を狙える偏差値圏といえます。
文教大学経営学部の偏差値は 60 となっており、経営系としては比較的入りやすいレンジに位置しています。駅近キャンパスやアットホームな学修環境を背景に、過度な競争よりも自分のペースで学びたい層から支持されやすい難易度帯といえます。総合型や学校推薦型選抜の比率が比較的高い点も影響し、一般選抜では標準的な学力があれば十分に戦える偏差値水準に落ち着いています。
総合すると、両校の偏差値差は 58 と 60 の開きが大きく、難易度においては東京経済大学がワンランク上です。ただし文教大学も堅実な難易度帯で安定しており、学修スタイルやキャンパス環境の相性で選ぶ余地も大きいため、「より専門性の強い経済学を深めたいなら東京経済」「経営を広く学びつつ落ち着いた環境を望むなら文教」といった選び方が向いています。
倍率
東京経済大学経済学部の倍率は 2.9 となっており、数字自体は標準的な領域に収まっています。受験方式の幅があるため受験生の分散が起きやすく、極端に競争が高まらない一方で、一定の学力が安定して求められる入試構造です。基礎問題を確実に得点できる力が結果に直結しやすく、過度な難問対策よりも得点の取りこぼしを防ぐ丁寧な準備が効果的です。
文教大学経営学部の倍率は 3.2 で、落ち着いた受験環境が続いています。地域性のある志望者層と、方式の多さが倍率の急激な変動を抑えており、基礎学力重視の傾向が明確です。標準レベルの学習をしっかり積み上げることで合格ラインに届きやすい構造であり、計画的な対策がそのまま得点に反映されるタイプといえます。
総合すると、倍率の差は大きくなく 2.9 と 3.2 の比較では優劣が明確に分かれる状況ではありません。競争率だけで判断するより、学びたい内容やキャンパス環境、大学との相性に比重を置いて選ぶほうが実利的で、どちらも基礎力を丁寧に整える受験生に適した入試となっています。
卒業後の進路

有名企業の就職率
東京経済大学経済学部の有名企業就職率は 6.8 となっており、首都圏の中規模私大の中では安定して堅調な位置にあります。この数値は、単に大手企業のみに就職者が偏っているということではなく、公務員(経済産業省や国土交通省などの省庁系、自治体職員など)や、安定した業界の企業への就職も含めて総合的なキャリア実績の厚みを示しています。学生規模が大きすぎないことから、個別の支援が届きやすい環境が整っており、キャリアセンターによる面接対策やエントリーシート添削、OB・OGネットワークの活用など、大学としての支援が成果に結びつきやすい構造が特徴です。特に近年はコロナ禍を経て中堅私大の動向が分かれやすい中で、東京経済大学は就職支援体制の強さによって比較的安定した数字を維持しており、実力に対して過度に高望みしすぎない堅実な就活をしたい学生にとって取り組みやすい環境といえます。
文教大学経営学部の有名企業就職率は 0 と表示されており、「0」という数値は就職実績が極端に低いという意味ではなく、大学側が有名企業就職率として公表可能なデータを整備していない、あるいは公表基準に満たないため数値化されていない状態を示しています。そのため、この項目だけで文教大学の就職力を判断することは適切ではありません。文教大学は学生規模が比較的小さく、学部創設からの歴史も浅いため、過去の卒業生データが蓄積し切れていないことや、キャリアパスの傾向が多様であることが影響していると考えられます。実際には、教育系・地域金融・中堅企業・準大手企業など、幅広い進路を選択している学生が多く、実務スキルよりも人柄やコミュニケーション力を重視する企業との相性が良いため、数字だけでは見えない就職のしやすさが存在する点には注意が必要です。
総合すると、数値として明確に比較できるのは東京経済大学の 6.8 のみであり、文教大学の 0 は「未公表」という特性上、直接的な優劣をつけることはできません。ただし、実績が可視化されていること自体は受験生にとっての安心材料になりやすく、東京経済大学は支援体制の厚さや進路データの蓄積という面で一定の強みを持っています。一方で文教大学は、少人数教育や地域との結びつきを背景に個々のキャリア選択を支える柔軟性があり、進路の幅広さを望む学生には適した環境といえます。つまり、データの明確さを重視するなら東京経済大学、個別最適なキャリア形成を求めるなら文教大学というように、志向性によって評価軸を変えることが重要です。
主な就職先
有限責任あずさ監査法人(2名)
みずほ銀行(2名)
(名)
(名)
東京経済大学経済学部では上記の他に、地域の金融機関や専門商社、IT系の中堅企業など、安定した事業基盤を持つ企業への就職が広く見られます。キャリア支援の厚さも相まって、公務員志向の学生が一定数いる点も特徴で、事務職系を中心とした行政分野との相性が良い傾向があります。また、大学として面倒見が良いことから、就活初期の段階で進路の方向性を固めやすく、結果的にミスマッチの少ない就職活動につながりやすい点も強みと言えます。
文教大学経営学部では上記の他に、地域密着型の企業や教育関連事業、サービス業、卸売・小売系の企業など、幅広い領域に卒業生が進んでいます。学部創設からの歴史が浅く、学生規模も比較的小さいため、就職の傾向が分散しやすいことが特徴で、特定の業界に偏らず、自身の興味や強みに沿って柔軟にキャリアを選べる点が魅力となっています。実践的な学びを重視するカリキュラムの影響もあり、コミュニケーション能力を評価する企業との親和性が高いことも見逃せないポイントです。
総合すると、東京経済大学は公務員系や安定した民間企業を志望する学生が多く、結果として毎年一定のルートが形成されています。一方で文教大学は進路の方向性が多様で、一人ひとりの関心に合わせたキャリアを選びやすい環境が整っているため、画一的な傾向よりも個別性を重視した進路形成を望む学生に向いています。両校とも特徴がはっきりしているため、どのような働き方を望むかによって評価が分かれる項目です。
進学率
東京経済大学経済学部の進学率は 0.9 となっており、首都圏の経済系私立大学としては標準的な水準に位置しています。経済学部として基礎的な理論科目から応用的な専門領域まで学べるため、大学院で研究を深める学生も一定数存在しますが、全体としては就職志向が強い学部のため、進学率そのものが突出して高いわけではありません。進路の中心は民間企業や公務員であり、進学者は研究志向や専門性を深めたい学生に限られる傾向があります。
文教大学経営学部の進学率は 1.3 で、こちらも比較的落ち着いた数値となっています。文教大学は教育学部のイメージが強い大学ですが、経営学部においては実務科目が多く設定されていることで、大学院進学よりも実社会への早期参入を重視する学生が多く、進学者は必要な専門性を深めたい層に限られるケースが見られます。歴史が浅い学部ということもあり、大学院進学者の絶対数がまだ多くない点も特徴のひとつです。
総合すると、両大学の進学率で大きな差は見られず、0.9 と 1.3 の比較からも、進学より就職を選択する学生が多い点は共通しています。進学率自体は判断材料としてのインパクトが大きい項目ではなく、大学院へ進みたい学生にとっては各大学の研究領域や指導体制の相性のほうが重要であり、進路の幅を広げたい場合は、自身の志向性に合った学習環境を重視して選ぶのが適切です。
留学生

受け入れ状況
東京経済大学経済学部の留学生数は 100 名となっており、規模が大きすぎない学部としては比較的受け入れ体制が安定している点が特徴です。全体の人数は突出して多いわけではありませんが、経済学の国際性を踏まえ、アジア圏を中心に一定の留学生が在籍していることで、授業の一部やゼミ活動に適度な多様性が生まれています。生活面でのサポートが比較的手厚く、初学者でも学びやすい環境を整えていることから、「多国籍すぎてついていけない」という状況とは異なり、国内学生にとっても自然に国際的な視点に触れやすいバランスとなっています。
文教大学経営学部の留学生数は 89 名であり、こちらは大学全体の国際系学部に比べると受け入れ規模が小さめの水準に位置します。文教大学は教育・文学系のイメージが強い大学であるため、経営学部単体としての国際学生比率は控えめになりやすく、少人数の学びを志向する学生にとっては落ち着いた環境で学べることが利点となります。一方で「多国籍な学修環境で英語力を磨きたい」というニーズに対しては、他学部科目や海外研修制度と組み合わせることで補完するスタイルが求められる点が特徴です。
総合すると、東京経済大学は 100 名、文教大学は 89 名と、留学生数の違いがやや明確です。多様性が自然に生まれる規模感を重視するなら東京経済大学が向いており、一方で落ち着いた学習環境の中で国内学生中心のコミュニティで学びたい場合には文教大学のほうが相性が良いといえます。この項目は数値そのものよりも学習スタイルの好みに直結するため、どの程度国際色を求めるかが選択の鍵になります。
海外提携校数
東京経済大学経済学部の海外提携校数は 47 校となっており、学部規模を考えると必要十分な連携体制が整っている点が特徴です。特にアジア圏の大学との協定が多く、短期語学研修や交換留学プログラムなど、学生が海外に触れる機会を自然に確保できる環境があります。大規模大学ほど提携校が多いわけではありませんが、プログラムの実参加者数が学内のキャパシティと適切に釣り合っているため「選抜が厳しすぎて参加できない」という状況になりにくく、初めて海外経験を積む学生でも参加しやすい体制が整っている点がメリットです。また、授業内で海外大学と連携したオンライン型プログラムも導入されており、多様な国の学生と交流する機会が比較的確保されやすいことも特徴的です。
文教大学経営学部の海外提携校数は 48 校で、こちらは比較的控えめな数値となっています。文教大学は教育・文学系の国際連携が強い傾向があるため、大学全体としての提携校は一定数存在するものの、経営学部単体で利用できる提携校は対象がやや限定的になりやすい状況にあります。とはいえ、少ないから機会がないというわけではなく、人数枠に対して希望者が過度に集中しないため、実際には参加しやすい海外研修が多いことが特徴です。また、経営学部では実務科目が多いことから、海外インターンシップや短期語学研修を通じて実践的にスキルを磨く学生が一定数存在しており、提携校の数以上に活用度を高めやすい環境が整っています。
総合すると、東京経済大学は 47 校、文教大学は 48 校と、海外提携校数の規模には一定の差があります。より幅広い選択肢から海外プログラムを選びたい場合は東京経済大学が向いており、逆に落ち着いた環境で無理なく参加できるプログラムを求める学生にとっては文教大学が適した選択肢となります。提携校数そのものは国際経験の有無を決定づける絶対指標ではなく、各大学が提供するサポート体制やプログラムの活用しやすさが重要であり、自身の目的に合わせた選択が求められます。
結局東京経済大学経営学部と文教大学経営学部のどちらが良いか

東京経済大学は、就職率が可視化されている点や海外提携校の選択肢が適度に揃っている点が強みで、6.8 のように実データが明確に提示されている安心感と、留学生数 100 名という規模感が自然な国際交流を生みやすい環境が特徴です。加えて、公務員志向・安定志向の学生が一定数いることでキャリア形成の方向性が比較的読みやすく、堅実に進みたい学生との相性が良い大学といえます。
文教大学は、有名企業就職率が未公表であるため実数での比較は難しいものの、学部規模の小ささを活かした個別性の高い学習と、留学生数 89 名という落ち着いた国際環境が特徴で、自分のペースで学びたい学生に適した環境が整っています。また海外提携校数 48 校という数値からも、大きな競争なく研修機会を得やすい点が魅力で、少人数教育と実務的な科目構成がキャリアの幅を広げています。
総合すると、明確なデータと安定した支援体制を重視するなら東京経済大学が向いており、一方で個別最適な学びや落ち着いた国際環境を求めるなら文教大学が適した選択肢になります。数値の優劣だけでなく、大学ごとの学び方やキャリア志向との相性を踏まえた進路選びが重要であり、どちらも学生の志向性によって評価が自然に分かれるタイプの組み合わせだと言えます。