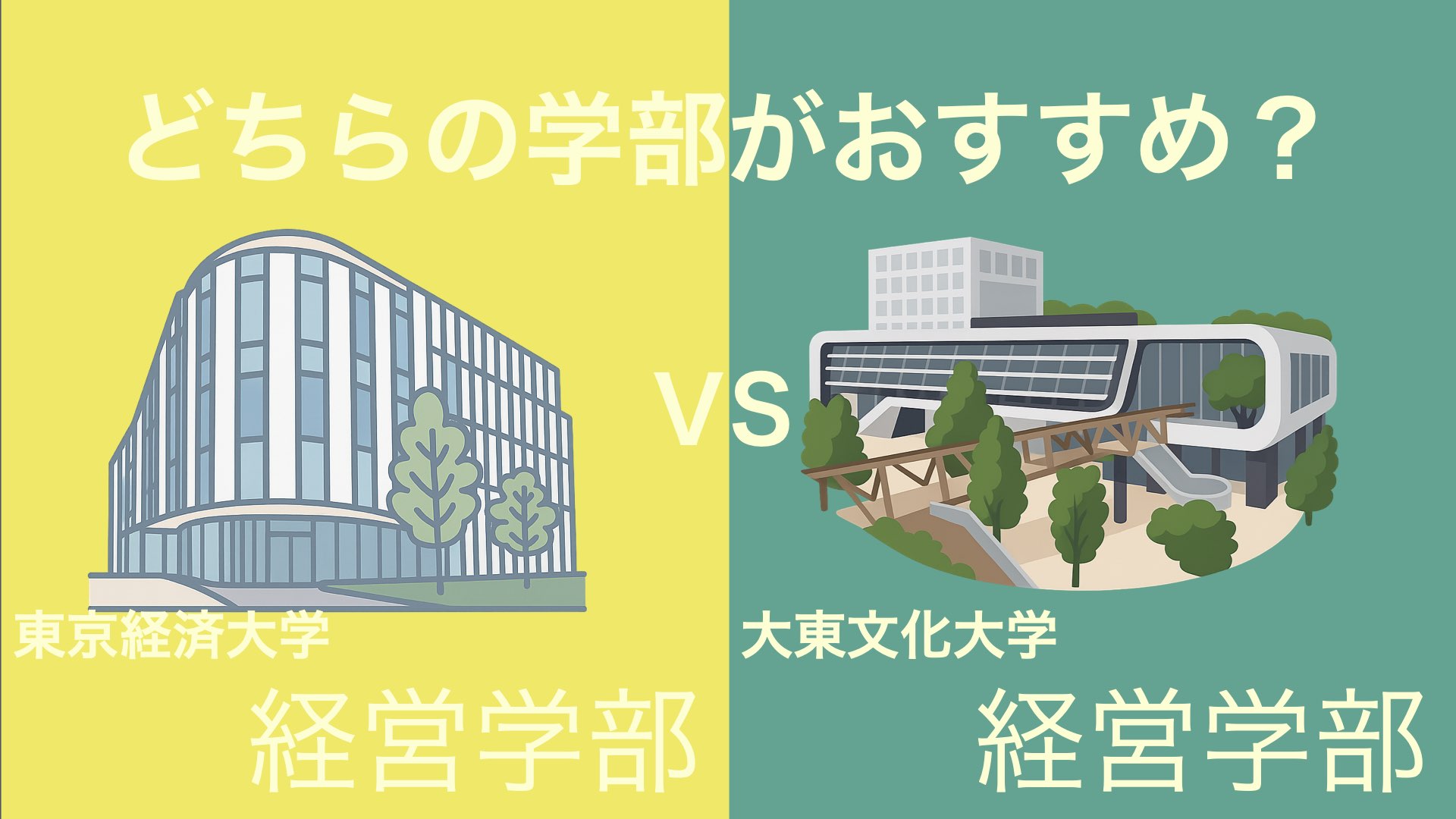東京経済大学経済学部と大東文化大学経営学部はどんな大学?

基本情報
| 項目 | 東京経済大学経済学部 | 大東文化大学経営学部 |
|---|---|---|
| 学部設立 | 1949年 | 2000年 |
| 所在地 | 東京都国分寺市南町1-7-34(国分寺駅) | 東京都板橋区高島平1-9-1(高島平駅) |
| 学部理念 | 経済学部は、グローバル化の進展する経済社会における多様な諸問題を分析し、その解決に努め、以って国内外の様々な要請に応えて活躍できる、高度な専門的経済知識と倫理観を備えた良き市民、良き経済人を養成し、その基盤となる教育研究を推進する。 | 経営学部経営学科は、経営学の基礎的・専門的知識を教授し、情報教育、語学教育、インターンシップなどの実践教育を通じて、経営学、会計学、知識情報マネジメントおよびマーケティングに関する専門的な知識と能力を身につけ、広い視野から現代社会を分析するとともに、自主的に判断できる力をもった人材を育成することを目的とする。 |
東京経済大学経済学部は、戦後の復興期である 1949 年に設置され、地域社会とともに経済学の実践的な学びを育ててきた学部です。キャンパスは 東京都国分寺市南町1-7-34 に位置し、最寄りの 国分寺駅 周辺は落ち着いた商業エリアと住宅地が広がる静かな環境です。学生数は 530 名で、規模としては大きすぎず小さすぎず、教員との距離も近い学習環境となっています。ゼミ中心の学びを通じて、経済の理論と社会課題を結びつける姿勢が重視されており、丁寧な学びを求める学生に向いた雰囲気があります。
大東文化大学経営学部は、比較的新しい 2000 年設立の学部で、現代のビジネス環境に合わせた実践型の経営教育を展開しています。所在地は 東京都板橋区高島平1-9-1、最寄り駅である 高島平駅 からアクセス可能で、学生生活と学びが両立しやすい環境が整っています。学生数は 365 名で、演習・インターンシップを中心とした実務志向の学びが特徴です。現代的な経営課題に対応するための実践教育が豊富で、能動的に動きたい学生に向いたスタイルとなっています。
両者を比較すると、東京経済大学は歴史ある落ち着いた学びの環境、大東文化大学は新しい学びを積極的に取り込んだ実践型スタイルという対照的な特徴があります。静かな環境で経済学を深めたい学生は東京経済大学、動きながら学ぶ経営志向の学生は大東文化大学と、志向によって適性が分かれます。
大学の規模
東京経済大学経済学部の学生数は 530 名です。首都圏の私立大学としては中規模に位置し、全体の人数が多すぎないため、授業やゼミで教員との距離が近くなりやすい点が特徴です。この規模感は、学生同士のつながりも作りやすく、学部全体の雰囲気として落ち着いた印象につながっています。日々の授業だけでなく、キャリア支援や個別相談などでもケアが行き届きやすいのは、こうした適度な規模ならではの利点と言えます。
大東文化大学経営学部の学生数は 365 名で、東京経済大学と比較するとやや小規模な構成です。この規模は、演習中心の学びやインターンシップなど実践的な学修が特色となる学部にとって相性が良く、一人ひとりの学習状況を把握しやすい環境をつくっています。特にグループワークやプロジェクト型授業が多い学部では、少人数での協働がスムーズに進むことが大きなメリットになります。
両者を比較すると、東京経済大学は中規模で「安定した学びの場」、大東文化大学は小規模寄りで「実践教育が行き届きやすい環境」という違いがあり、学びのスタイルに応じて魅力が分かれます。
男女の比率
東京経済大学経済学部の男女比は 81 : 19 となっており、全体として男子学生の割合が高い構成です。経済学部は全国的にも男子の比率が高くなりがちな学部ですが、東京経済大学でも同様の傾向がみられます。男子学生が多いことで、ゼミや授業の議論がやや実務寄り・数値寄りになる場面もあり、経済学らしい分析的な雰囲気が強くなるのが特徴です。一方で女子学生も一定数在籍しており、学びの場においては性別による偏りを感じにくいよう配慮された学習環境となっています。
大東文化大学経営学部の男女比は 72 : 28 です。こちらも男子学生の割合が高い構成にはなっていますが、経営学部はサービス産業やマーケティング志向の学生も多いため、経済学部よりは男女のバランスがとりやすい傾向があります。授業の内容によっては女子学生の参加が活発であったり、プレゼンや企画系の授業では多様な視点が生まれやすい環境が整っています。実務型の科目が多い学部のため、性別による学びの差はほとんど見られません。
両大学を比較すると、どちらも男子比率が高いという点では共通していますが、学習スタイルの違いにより雰囲気には差が出ます。分析的な学びが中心の東京経済大学に対し、大東文化大学は実践型授業も多く、多様な視点が活かされやすい構造になっています。
初年度納入金
東京経済大学経済学部の初年度納入金は 129.3 万円です。首都圏の私立文系としては標準的な水準で、経済学部として必要な学習環境やゼミ活動、キャリア支援などを含めると、費用対効果のバランスが比較的取りやすい金額になっています。施設や学内環境も落ち着いており、学びの質に対して過度に負担の大きい学費ではないことから、家庭の負担を抑えつつ大学生活を送りたい学生にとって選びやすい設定と言えます。
大東文化大学経営学部の初年度納入金は 121.4 万円で、こちらも私立大学の文系学部として一般的な水準に位置しています。経営学部は実践型の授業や演習科目が多く、その中には外部連携やフィールドワークが用意されている場合もありますが、追加費用の負担が大きくなるようなカリキュラム構成にはなっていません。コストを抑えながらも現代のビジネスに即した学びを得られる点が魅力です。
両大学を比べると、初年度納入金の差は大きくなく、どちらも私立文系として標準的な範囲に収まっています。学費の差よりも、学びのスタイルや大学生活の雰囲気、自身のキャリア志向を軸に検討するのが適した組み合わせと言えます。
SNSでの評価
東京経済大学経済学部のSNSでの評価は、全体として「落ち着いた環境で学べる」「真面目な学生が多い」といった声が目立ちます。派手さや強烈なブランドイメージを前面に押し出す大学ではありませんが、その分だけ堅実で誠実な雰囲気が好意的に受け取られる傾向があります。ゼミ活動や授業の質についても「教員との距離が近く、質問しやすい」「キャリア支援が丁寧」という投稿が見られ、着実に学びたい学生から好まれる印象があります。一方で、SNS上では大規模大学のような情報量の多さはなく、華やかさを求める層にはやや物足りなく映ることもあるようです。
大東文化大学経営学部のSNS評価は、学内の雰囲気に関する投稿が多く、「面倒見が良い」「学生同士の距離が近い」といった点が好意的に語られています。また、地域密着の活動や実践型授業に関連する発信が多く、特にインターンシップや課外活動に積極的な学生からのポジティブな投稿が目立ちます。一方で、大学全体のブランド力については「可もなく不可もなく」といったニュアンスの意見も一定数あり、ネームバリューよりも実務的な学びを重視する学生に向いた環境であることが窺えます。
両大学を比較すると、東京経済大学は「堅実で落ち着いた学び」、大東文化大学は「学生同士の距離が近く実践的」という評価が中心です。SNS上の印象では、学習環境の安定感を重視するなら東京経済大学、活動量や実践経験を重視するなら大東文化大学という形で方向性が分かれます。
合格難易度(偏差値・倍率)

偏差値(マナビジョン)
東京経済大学経済学部の偏差値は 58 で、同規模帯の私立経済学部としては安定した位置にあります。首都圏の中堅上位層に含まれることが多く、受験生全体の学力水準としても一定の底上げが効いている印象です。特に基礎学力を重視した問題構成が多く、科目間のバランスをしっかり整える受験生が合格しやすい傾向があります。また、過度に難問奇問が出題されないため、標準レベルの問題を確実に取り切る力が強く求められます。偏差値の安定感は、入学後の学びにもつながり、同質的で落ち着いた学習環境をつくりやすい点が特徴です。
大東文化大学経営学部の偏差値は 48 で、東京経済大学と比較すると難易度は控えめです。入試では基礎的な内容が中心となりますが、経営学部の性質上、文章理解力や論理的思考を問う設問が一定数出題されるため、単に暗記だけではなく「内容を読み取り、自分の言葉で整理する力」が求められる傾向があります。偏差値帯としては中堅に位置しますが、実践教育に力を入れている学部のため、入学後の努力によって学習成果を伸ばしやすい環境が整っています。
両大学を比較すると、偏差値の差は明確で、東京経済大学のほうが約10ポイント高い位置にあります。この差は入試難易度の違いを示すだけでなく、学習環境の落ち着きや入学者の学力層の差にもつながっています。一方で、大東文化大学は入学後の取り組み次第で実力を伸ばしやすい環境があり、実践型の学びを求める学生には魅力的な選択肢となります。
倍率
東京経済大学経済学部の競争率(admission_rate)は 2.9 倍で、適度な競争環境が保たれています。極端に高倍率というわけではありませんが、受験生が一定数集まる学部であるため、基礎問題を落とさず得点を積み重ねる堅実な学力が求められます。この倍率は、大学の規模感や偏差値帯、学部の安定した人気を反映した数値といえ、合格を目指すには科目間のバランスと基礎の徹底が重要になります。過度な難関ではないものの、確実に対策しておくべき中堅上位の倍率水準です。
大東文化大学経営学部の競争率は 2 倍で、こちらは比較的低めの数値となっています。志望者の幅が広く、入試としては挑戦しやすい環境が整っています。ただし、倍率が低いからといって無対策で合格できるわけではなく、基礎力を丁寧に問う出題が中心であるため、文章理解や計算問題を確実に解ける力が必要です。実践的な教育に関心を持つ学生が多い学部であるため、入学後の努力で伸びやすく、倍率の低さが必ずしも学習の質の低さを示すわけではありません。
両大学を比較すると、東京経済大学のほうが競争率が高く、志望者の層もやや厚い印象があります。一方の大東文化大学は受験しやすい倍率となっており、入りやすさという面ではアドバンテージがあります。ただし、どちらも「基礎問題を確実に取れるか」が合格の分岐点になり、倍率の大小だけで学部の価値を判断できる組み合わせではありません。
卒業後の進路

有名企業の就職率
東京経済大学経済学部の有名企業就職率(employment_rate)は 6.8%です。この数値は民間就職の中でも大手企業・上場企業レベルに進んだ学生の割合を示すもので、規模の大きくない学部であることを踏まえると堅実な結果といえます。経済学部は金融・メーカー・サービスなど幅広い業界と相性が良く、同大学でもバランスよく民間就職が展開されています。また、公務員志望者が比較的多い学部でもあるため、有名企業就職率だけでは測れない進路の広さが特徴になっています。公務員系に一定の強さを持つ点も、民間企業への割合が極端に高くならない理由として挙げられます。
一方の大東文化大学経営学部は、employment_rate が 0%と「0」と表示されていますが、これは“有名企業就職率が極端に低い”という意味ではなく、“大学や学部として公表可能な統計データが存在しない”という意味です。これは以前の比較でも確認してきたように、「就職支援が弱い」という評価に直結しません。むしろ大東文化大学は地域金融・行政・中堅企業など“公的・地域性のあるキャリア”に強く、公表される指標の種類が異なることが理由です。また、実務科目が多い経営学部の性質上、中堅企業や地域密着企業に進む学生が多く、統計の取り方によっては有名企業枠に含まれないケースが多く発生します。このため、employment_rate を単純比較することには注意が必要です。
両大学を比較すると、東京経済大学はデータが整備されており就職の「見えやすさ」が高い一方で、大東文化大学はデータ非開示により数値上の判断が難しい組み合わせとなっています。しかし、実際の進路傾向を見る限り、東京経済大学はバランス型、大東文化大学は地域密着型・実務型という違いが明確で、どちらが優れているかではなく、志望するキャリアとの相性で評価が分かれる内容になっています。
主な就職先
ニトリホールディングス(2名)
EY新日本有限責任監査法人(1名)
武蔵野銀行(4名)
淺沼組(2名)
東京経済大学経済学部では上記の他に、地方自治体や金融、卸売・小売、情報サービスなど多様な分野に卒業生が進んでいます。経済学部らしく公務員志望者が一定数おり、行政職の内定実績は安定しています。また、企業では管理部門や営業職への就職が比較的多く、経済学の基礎を活かしながら社会の幅広い領域で活躍しやすい点が特徴です。学部として極端な特定業界への偏りが少なく、バランス型のキャリア形成がしやすい環境が整っています。
大東文化大学経営学部では上記の他に、地域金融機関、行政・公共系、サービス産業、建設・不動産など多様な業界に学生が進んでいます。特に地域密着のキャリア形成が目立ち、地元へのUターン・Iターン就職を選択する学生も一定数確認できます。経営学部として実務科目が豊富なため、卒業後すぐに現場で力を発揮できる人材を育成しており、営業、企画、店舗運営など実践的な職種へのマッチングが良い点も特徴です。総じて、地域社会とのつながりを強く意識したキャリアパスを形成しやすい学部となっています。
両者を比べると、東京経済大学は「公務員+民間のバランス型」、大東文化大学は「地域密着・実務型」の傾向がより明確に現れており、進路の方向性によって選び方が大きく変わる組み合わせです。
進学率
東京経済大学経済学部の進学率は 3.4%で、多くの学生が卒業後は就職を選択しています。進学者は少数派ですが、経済理論の深化や公共政策分野の研究など、専門性を高めるために大学院へ進むケースがあります。進学希望者には教員による丁寧な研究指導が行われ、研究計画書の作成サポートなども受けられるため、少数ながらも確実に学びを深めることができる環境が整っています。
大東文化大学経営学部の進学率は 0.3%で、こちらも大半の学生が就職を選択しています。研究志向の学生は、経営学の理論研究やデータ分析、マーケティングの専門研究などを目的に大学院へ進むことがありますが、学部全体としては実務志向が強いため、進学率そのものは高くありません。ただし、ゼミ活動を中心とした少人数教育により、研究を希望する学生には個別の指導が行われる体制が整っています。
両大学とも進学者は多くありませんが、進学を希望する学生に対してはそれぞれ適切なサポートが整備されており、研究分野に挑戦する環境は確保されています。
留学生

受け入れ状況
東京経済大学経済学部の留学生数は 100 名です。学部全体として大規模な国際交流を前面に押し出すタイプではありませんが、少人数だからこそ日本人学生との距離が近く、日常的なコミュニケーションを通じて異文化理解を深めやすい環境があります。語学力の高さよりも「生活や価値観の違いを自然に知る」という体験が中心となり、落ち着いた国際交流を望む学生には向いた構造になっています。
大東文化大学経営学部の留学生数は 366 名と、東京経済大学より多く、学内での国際色は比較的豊かです。特にアジア圏の留学生が多く、日常的に異文化に触れられる機会が多いのが特徴です。語学教育の充実や大学全体の国際化方針とも相まって、留学生との協働授業やイベントに参加しやすい環境が整っており、海外志向の学生には魅力的な学びの広がりがあります。
両大学を比較すると、東京経済大学は「身近で小規模な国際交流」、大東文化大学は「人数を背景とした国際色の豊かさ」という違いが見られます。落ち着いた環境で少人数の交流を深めたいか、より多文化な環境で多様な学生と関わりたいかによって、相性が分かれる組み合わせです。
海外提携校数
東京経済大学経済学部の海外提携校数は 47 校です。提携校数としては多くはありませんが、その分だけプログラムが比較的利用しやすく、参加学生が手厚いサポートを受けられる点が特徴です。短期研修や語学留学など、初めて海外経験を持つ学生でも挑戦しやすい内容が中心で、小規模だからこそ「丁寧さ」を重視した国際交流が展開されています。英語圏だけでなくアジア圏の提携校もあり、費用を抑えて海外経験を得たい学生にとっても選択しやすい環境となっています。
大東文化大学経営学部の海外提携校数は 118 校です。大学全体で国際化を進めてきた背景もあり、学部単位でも多様な地域の大学と協定を結んでいます。語学留学、短期・中期の交換留学などプログラムの種類が豊富で、学生が海外に触れる機会を幅広く選べる点が強みです。特にアジア地域の大学との結びつきが強く、留学生との共同授業や交流イベントが活発で、日常的に国際的な空気を感じられる学習環境が整っています。
両大学を比較すると、東京経済大学は「少数精鋭で利用しやすい国際交流」、大東文化大学は「提携校数の多さから選択肢が広がる国際環境」という違いが見られます。海外経験を“深く少人数で”積みたいか、“幅広く機会を得たい”かによって相性が変わる組み合わせです。
結局東京経済大学経済学部と大東文化大学経営学部のどちらが良いか

東京経済大学経済学部は、偏差値が 58 と安定した学力帯に位置しており、学生層の落ち着きや学習環境の整い方が強みになっています。加えて、公務員志望が一定数存在し、特定の業界に偏らず多様なキャリア形成が可能な点も特徴です。海外提携校数や留学生数は控えめですが、小規模で丁寧な国際交流プログラムが中心で、自身のペースで学びを深めたい学生に向いた環境です。全体として、基礎学力の安定・落ち着いた学習環境・バランス型キャリアという三点の結びつきが、この学部の大きな魅力になっています。
大東文化大学経営学部は、海外提携校数 118 校、留学生数 366 名という国際面の強さが際立っており、日常的に異文化と触れられるキャンパス環境が形成されています。また、地域金融・行政・中堅企業など“地域密着型の進路”が安定している点も特徴で、実務科目の多さがこのキャリア傾向を後押ししています。有名企業就職率が 0%とデータ非公表であっても、それは「統計の形式上の非計上」であり、“キャリアの質が低い”という意味ではありません。国際性と地域性が共存する独自の学習環境が強みの学部です。
両大学を比較すると、東京経済大学は偏差値の安定と学習環境の落ち着きが魅力で、幅広い進路を志向する学生に向いています。一方、大東文化大学は国際性の高さと地域密着のキャリア形成が特徴で、海外経験や地域での実務に関心がある学生に向いた構造になっています。大きな上下関係が生じる比較ではなく、「学力の安定とバランス型の東京経済」「国際性と地域志向の大東文化」というように、将来志向や学びのスタイルによって最適な大学が分かれる組み合わせとなっています。