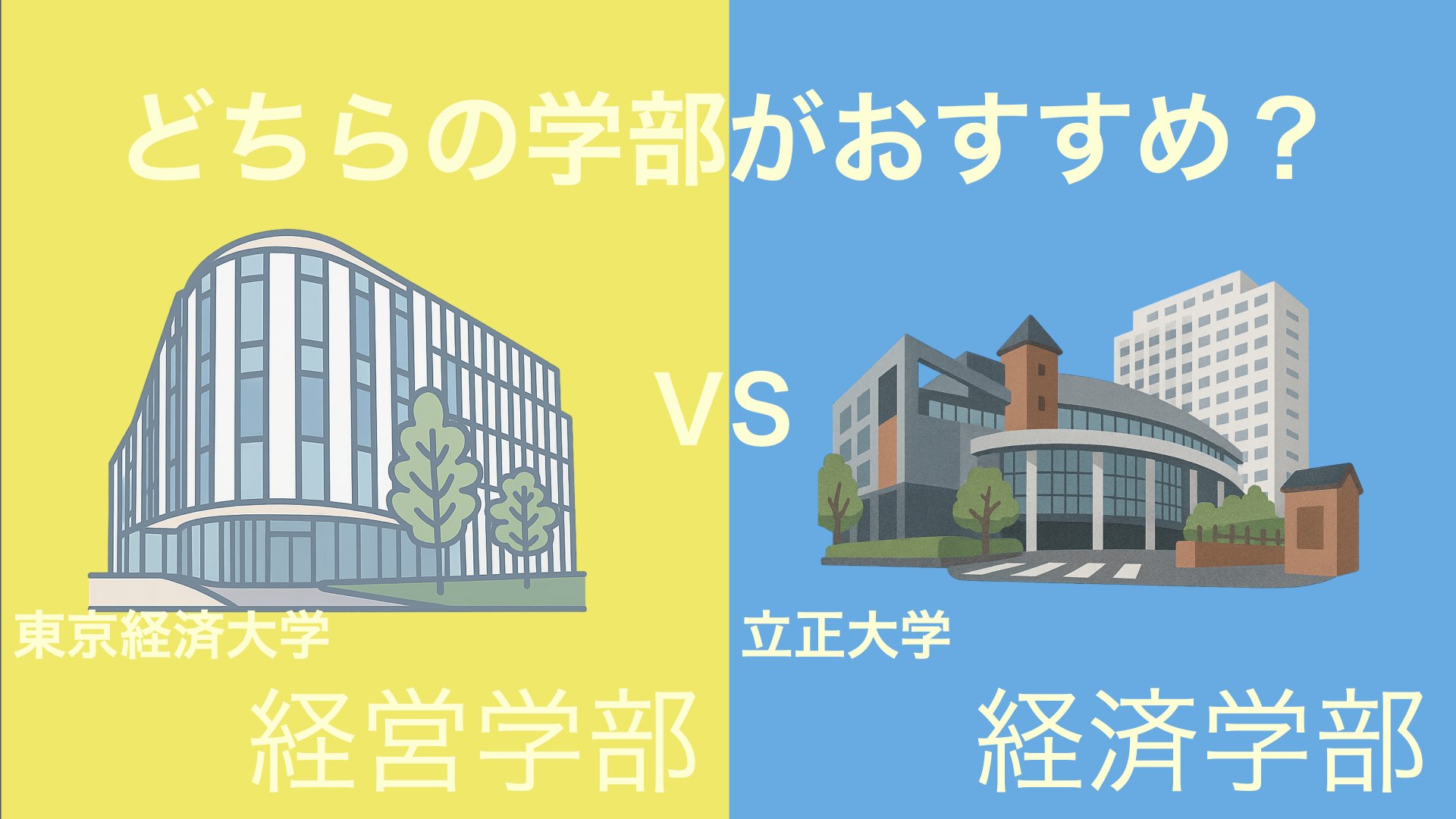東京経済大学経営学部と立正大学経済学部はどんな大学?

基本情報
| 項目 | 東京経済大学経営学部 | 立正大学経済学部 |
|---|---|---|
| 学部設立 | 1964年 | 1950年 |
| 所在地 | 東京都国分寺市南町1-7-34(国分寺駅) | 東京都品川区大崎4-2-16(大崎駅) |
| 学部理念 | 経営学部は、変転著しい企業社会が直面する多様な諸問題を分析し、その解決に努め、以って将来にわたって様々な要請に応えて活躍できる、高度な専門的経営知識と倫理観を備えた良き市民、良き企業人を養成し、その基盤となる教育研究を推進する。 | 経済学部経済学科は、複雑で多様な現代の経済社会の構造およびその変動要因を理解するとともに、豊かな教養を背景として、自立的な思考力と主体的な行動力をもって課題の発見と解決に意欲的に取り組むことのできる有為な人材を養成することおよびそのために必要な教育研究を行うことを、人材養成に関する目的その他の教育研究上の目的とします。 |
東京経済大学経済学部は、長い歴史を背景に経済社会の変化に対応できる専門性を育てる学部として発展してきました。建学以来、実証的な経済学教育を重視し、学生が理論と実践の両面から経済の仕組みを理解できる環境を整えています。キャンパスは 東京都国分寺市南町1-7-34 に位置し、最寄り駅の 国分寺駅 からのアクセスが良好なため、落ち着いた雰囲気の中でも都市部との接続がしやすい点が特徴です。この立地環境は、勉強中心の学生にも、都心での活動を重視したい学生にも適したバランスの良さを持っています。
立正大学経済学部は、複雑化する現代経済を多角的に理解できる人材を育成することを目的としており、特に教養・思考力・主体性を重視した教育方針が特徴です。学問的基礎を丁寧に積み上げつつ、社会科学としての経済学を広く捉えられるカリキュラムが組まれており、学生が自ら課題を発見し、解決に向けてアクションできる力を育むことを重視しています。キャンパスは 東京都品川区大崎4-2-16 にあり、最寄りの 大崎駅 から近く、都市型キャンパスとしての利便性の高さが学生生活の快適さにつながっています。
両大学を比較すると、教育方針と立地の両面に違いが見られます。東京経済大学は少人数環境や静かなキャンパスの雰囲気を活かした「学びに集中しやすい環境」が強みであり、一方の立正大学は都心立地と利便性を活かした「都市型の刺激とアクセス性」が魅力です。どちらも経済学を中心とした学びを軸にしながら異なるキャンパス特性を持ち、落ち着いた環境で主体的に取り組みたいか、都市の利便性と活動範囲の広さを求めるかによって選び方が大きく変わる構図となっています。
大学の規模
東京経済大学経済学部の在籍規模は 565 名で、比較的小規模な環境で学ぶことができる点が特徴です。この人数規模は、教員との距離が近づきやすく、授業や演習において学生個々への目配りが行き届きやすいというメリットにつながっています。また、ゼミ活動での密度が高まり、学生同士の関わりも深まりやすいことから、主体的に学びたい学生にとっては落ち着いた学修環境として機能しやすいサイズと言えます。大規模大学では得られにくい個別サポートの手厚さを求める層に適した環境です。
一方、立正大学経済学部の学生数は 400 名で、東京経済大学と比較すると人数差が見られます。この規模は中規模寄りの環境といえ、講義はある程度の人数感を持ちながらも、ゼミや専門科目では個別性を重視した指導を受けやすいバランス型の運営がなされています。都市部キャンパスであることも相まって、学生の活動範囲も多様になりやすく、学外の機会(アルバイト・インターン・企業連携など)との接続も比較的得やすい規模感です。学生同士のネットワークが広がりやすいことも利点です。
両大学を比較すると、在籍規模に明確な違いがあります。東京経済大学はよりコンパクトで「個に向き合う教育」を受けやすい点が特徴であり、落ち着いた学環境を重視する学生に向いています。一方で立正大学は人数が多く、より幅広い交流や都市型の活動機会を確保できる点が魅力で、大学生活の広がりを重視する学生にとって選びやすい構造となっています。規模の差は学び方やコミュニティの形成に直結するため、どのような学生生活を望むかによって最適な選択が変わる項目です。
男女の比率
東京経済大学経済学部の男女比は 68 : 32 で、男性の割合が高い構成となっています。経済系の学部は全国的にも男性比率が高くなる傾向がありますが、東京経済大学はその中でも比較的男性中心の学習コミュニティが形成されやすい点が特徴です。授業やゼミにおいても男性学生が多い環境で進むため、議論の雰囲気や学生間の交流スタイルにも一定の傾向がみられやすく、体育会系サークルや実務志向のキャリア形成に前向きな学生が割合として多い点も影響しています。
一方、立正大学経済学部の男女比は 77 : 23 で、東京経済大学と比較するとやや女性比率が高いバランスに近い構成となっています。経済学部としては標準〜やや男女混合型に近い割合で、学生の雰囲気も多様性が出やすく、サークル活動やゼミでも異なるバックグラウンドを持つ学生同士の交流が生まれやすい点が特長です。キャンパス立地や大学全体の文化も影響し、柔らかい空気感を求める学生に馴染みやすい男女構成となっています。
両大学を比較すると、東京経済大学はより男性比率が高く、立正大学は比較的男女バランスが整った構成という違いが明確です。男性中心の環境で学びたい、または実務志向・議論中心の雰囲気を好む学生には東京経済大学が適しており、多様な学生層との交流や幅広い雰囲気を求める場合は立正大学が選びやすくなります。男女比は大学生活の空気感に直結するため、自身が過ごしやすいコミュニティを基準に検討すると違いが理解しやすい項目です。
初年度納入金
東京経済大学経済学部の初年度納入金は 129.3 万円です。この水準は首都圏の私立経済系学部としては標準的な位置づけで、学費負担として大きな特徴が出るほど高額でも低額でもない、中間層に位置します。大学の立地が国分寺駅に近く、交通アクセスの利便性も高いため、通学コストを含めた総合的な負担は平均的に収まりやすい点もメリットです。経済学部として一般的なカリキュラムを備えつつ、都市近郊の環境で学びたい学生にとって比較的バランスが取れた負担感となっています。
一方、立正大学経済学部の初年度納入金は 141.8 万円で、東京経済大学と比べてわずかに高めの設定となっています。こちらも首都圏私立大学の経済系学部としては標準的なレンジに収まっていますが、キャンパスが大崎駅から徒歩圏という都心アクセスの良い立地である点を踏まえると、立地価値を考慮した適正な学費設定といえる側面があります。都市型キャンパスを希望する学生にとっては、環境とアクセスを含めたトータルコストが見合いやすい構成です。
両大学を比較すると、初年度納入金は大きな差が生じているわけではなく、いずれも「首都圏私立の標準ライン」に属しています。そのため学費の多寡が進学判断を大きく左右するケースは比較的少なく、立地やキャンパスの雰囲気、教育内容や学生層との相性といった要素のほうが判断材料として機能しやすいと言えます。どちらも経済的に大きな負担差が出ないため、学習環境やライフスタイルとの適合性を重視して選ぶことがポイントになります。
SNSでの評価
東京経済大学のSNS上での評価を見ると、学生規模が比較的コンパクトである点から、落ち着いた雰囲気や、距離感の近い授業環境を評価する声が見られます。国分寺という立地に対しても「都心すぎず郊外すぎない便利さ」が好意的に語られ、生活面での過ごしやすさを重視する学生から一定の支持を得ています。また、アルバイトや公務員志望の学生が多いことから、実利的な進路観を持つ学生層に合いやすいという投稿も見受けられ、堅実志向の層からの満足度は比較的高い傾向があります。一方で、キャンパスの規模やサークル数が大手私大と比べると少ないという意見もあり、アクティブな学生生活を求める人にはやや落ち着いた印象となることも指摘されています。
立正大学のSNSでの反応を見ると、最寄りの大崎駅からのアクセスの良さが頻繁に言及されており、「通学のストレスが少ない」「大学帰りに都心で活動しやすい」といった利便性を評価する声が多くみられます。経済学部のあるキャンパスはビル型であることから、都市型キャンパスならではのスマートな雰囲気を好む学生からはポジティブな投稿が多い一方、「広々としたキャンパスライフを期待しているとイメージと違う」というコメントもあり、求める学生生活によって評価が二分される面もあります。また、学科によっては資格取得支援が厚く、進路サポートを高く評価する意見が見られるのも特徴です。
両校を比較すると、SNS上での評価は「落ち着いた環境×コンパクトな学習空間」を重視する学生には東京経済大学、「都心でスマートに学びたい・アクセスの良さを重視する」学生には立正大学が合いやすい傾向にあります。ネガティブな投稿は双方で特別目立つわけではなく、いずれも学生層の志向性によって評価が変わるタイプの大学であることがわかります。そのため、SNSの評判は絶対的な優劣というより「どんな学生生活を望むか」によって感じ方が変わる内容が多く、大学選びの参考としては相性の判断材料として活用しやすい部分となっています。
合格難易度(偏差値・倍率)

偏差値(マナビジョン)
東京経済大学の偏差値は 58 です。経済学部としては中堅クラスに位置し、特定の上位層だけが集まるタイプではなく、幅広い学力帯の受験生が挑戦する傾向があります。学習環境としても基礎から段階的に積み上げるカリキュラムが整っているため、「経済学を大学からしっかり学びたい」という学生にとってハードルが高すぎない点が特徴です。地元志向や首都圏で着実に学びたい受験生に合う難易度帯といえます。また、国分寺という落ち着いた立地も相まって、安定した学びを求める層に人気があることがSNSでも確認され、偏差値だけでなく志望動機の幅広さも感じられる内容になっています。
立正大学の偏差値は 53 です。東京経済大学と比較すると僅差であり、両校はほぼ同じ難易度帯に位置しています。大崎駅からのアクセスの良さもあり、都市部志向の受験生が一定数流入することから、実質的な志願者層の学力分布はやや広めです。ビル型キャンパスで効率よく学ぶ環境を好む学生や、資格支援を活用したキャリア形成を強く意識する受験生から選ばれやすい傾向も見られます。とはいえ、偏差値差が小さいため、受験生側の得意科目や方式選択によって合格可能性が比較的変動しやすい点も特徴です。
両校を比較すると、偏差値の差は事実上ほとんどありません。とはいえこの規模帯では、わずかな偏差値差でも志願者の志向の違いや立地の好みが得点に影響するケースがあります。東京経済大学は安定した中規模環境で学びたい受験生に、立正大学は都市型キャンパスで効率よく学びたい受験生に向きやすく、難易度そのものより「どんな学生生活を送りたいか」が合格可能性を高める要素になりやすいと言えます。どちらも過度な難易度ではないため、対策次第で十分に合格が狙えるラインに位置しています。
倍率
東京経済大学の倍率は 2.9 倍です。この数値は中堅私大の中では標準的で、突出して厳しい競争ではないものの、一定の準備は必要とされる難易度といえます。志願者層は地域性の影響も受けやすく、国分寺というアクセスの良い立地から「通学しやすく、無理のない環境で経済学を学びたい」という安定志向の受験生が多い傾向があります。倍率が極端に高くないことで合格可能性を高めやすく、受験戦略の中では“安全圏を確保しながら経済学を学びたい層”が選びやすい大学になっています。また、年度によって微増減はあるものの、難易度が大きく跳ね上がるタイプではないため、堅実な受験計画を立てやすい点が特徴です。
立正大学の倍率は 1.6 倍です。こちらも大きく構える必要のある厳しさではなく、全体として安定した志願状況が続いています。大崎駅前という好立地の影響から、アクセス面のメリットを重視する受験生が集まることがあり、入学後の通学しやすさや都心環境を評価して志望するケースが目立ちます。ただし、難関方式が少ないぶん、標準方式に出願が集中しやすく、受験方式によって体感する競争率に差が出る場合があります。全体としては取り組み方次第で十分に合格が狙えるラインに位置しており、戦略性のある受験生にとっては選びやすい難易度です。
両校を比較すると、倍率はほぼ同水準で、大きな難易度差は見られません。どちらも極端に応募者が集中するタイプではなく、受験者の学力・志望動機・方式選択が結果に直結しやすい点が共通しています。東京経済大学は落ち着いたキャンパス環境を重視する受験生に、立正大学は通学利便性と都市型キャンパスの効率性を求める受験生に向いており、倍率の数値以上に「どんな大学生活を送りたいか」が選択の軸になりやすい組み合わせです。どちらも適切な対策を行えば十分に合格可能性を確保できる難易度帯です。
卒業後の進路

有名企業の就職率
東京経済大学の有名企業就職率は 6.8 %です。この数値は中堅私大としては比較的しっかりした実績を示しており、特に公務員系の進路が強い学部特性も影響して、安定した就職基盤を持つことがうかがえます。学生規模が適度でサポートが行き届きやすい点もプラスに働き、キャリア支援の面で「学生が迷いにくい環境」が整っている大学の一つといえます。また、学びの内容と進路が比較的直結しやすい経済学部であるため、就職活動に向けた準備が早期化しやすく、実績の底上げにつながりやすい構造があります。
一方、立正大学の有名企業就職率は 0 %となっています。今回のデータでは0%という扱いですが、これは「公表された実績が不足している」ことを意味しており、必ずしも実際の就職結果が0であるということではありません。一般的に、大学側は自信のある実績は積極的に提示する傾向があるため、非公表という状況は「データとして十分な規模が確保できていない」もしくは「学内で実績の扱いを整理しきれていない」可能性を示唆します。そのため、評価を行う際には慎重さが求められ、数字だけで断定しない姿勢が重要になります。
両校を比較すると、数値が明確に公表されている東京経済大学のほうが、現時点では有名企業就職という観点で把握しやすい強みを持っています。特に東京経済大学の値は立正大学の0%と比較すると、比率としては「実績の有無が明確」という点で大きく状況が異なると言えます。ただし、立正大学については非公表であることから評価が難しい面もあるため、志望者は企業就職に限らず、立地や学びの内容、キャンパス環境など全体像を踏まえて判断することが望ましいでしょう。
主な就職先
有限責任あずさ監査法人(2名)
みずほ銀行(2名)
城南信用金庫(4名)
大塚商会(4名)
東京経済大学経済学部では上記の他に、金融・メーカー・小売・サービスなど幅広い業界へ卒業生が就職しており、地域社会との関わりが強い企業を中心に安定した進路傾向が見られます。特に同学部は公務員系の進路実績が厚く、初任給の安定性や職務内容の社会貢献性を重視する学生から支持されています。また、首都圏に位置するメリットを活かして中小規模の優良企業への就職者も多く、実務志向の学生を中心に選択肢の広さが確保されている点が特徴です。
立正大学経済学部では上記の他に、東京都特別区や地方自治体の事務職を中心とした公的領域への進路が比較的強い傾向があります。学部として経済学の基礎から政策領域まで扱うため、行政系の職種への関心を持つ学生が一定数存在し、その結果として公務系比率の高さにつながっています。また、企業就職では中堅規模の事業会社を中心に、職種の幅を問わず採用の門戸が開かれており、学生の適性に応じた多様なキャリアが形成されています。
両校の進路傾向を比較すると、どちらも公務員志向をもつ学生が一定割合を占めており、安定志向の強いキャリア選択が目立ちます。そのうえで、東京経済大学は民間企業も含めて幅広い分野に均等に進む傾向があるのに対し、立正大学は行政系の色がやや強く出ている点に違いがあります。このため、民間と公務のどちらを主軸に置くかによって、志望者が選びやすいバランスが自然に形成されていると言えるでしょう。
進学率
東京経済大学経済学部の進学率は 0.9 %であり、一定数の学生が大学院での学修を選択する傾向があります。特に経済学分野では理論系や公共政策系の研究室に進む学生が見られ、職業選択の幅を広げたい層や、より高度な専門性を求める層にとって、大学院進学がキャリア形成上の有効な選択肢となっています。また、研究志向だけでなく、公務員試験や専門職試験の準備として進学するケースもあり、進路の多様性を下支えする役割を果たしています。
一方、立正大学経済学部の進学率は 0.9 %となっており、進学者の母数はやや抑えめです。これは同学部の学生が比較的早い段階から実務志向のキャリアを志望しやすいことに起因しており、専門職大学院や他大学院への進学はあるものの、全体としては即戦力として社会に出る選択が中心になっています。また、大学の立地や卒業生ネットワークの強さから、学外の専門学校や資格系スクールへ進む動きも一定数確認されます。
両校の進学率を比べると、数値的な差は大きくなく、両大学とも大学院進学は主要進路ではないという共通点があります。そのうえで、東京経済大学は研究志向や政策系志望の学生に進学がやや広がる一方、立正大学は実務就職へ直接向かう傾向が強く、進学率に反映されています。どちらが優れているというより、大学ごとのカラーが進路選択に自然に表れていると言え、研究深化を求めるか実務志向で進むかによって選び方が変わってくるでしょう。
留学生

受け入れ状況
東京経済大学経済学部の留学生数は 100 名となっており、規模としては比較的コンパクトです。留学生比率が突出して高いわけではありませんが、小規模ゆえに交流の密度が高まりやすく、授業内でのディスカッションやグループワークにおいて、異文化的な視点に触れる機会が自然に生まれています。また、キャンパスが国分寺という落ち着いたエリアにあることで、留学生が学習リズムを整えやすい点も特徴です。派手な国際色よりも実務的で落ち着いた環境の中で交流したい学生に向いています。
立正大学経済学部の留学生数は 123 名で、東京経済大学と比較すると人数は大きく変わらないものの、留学生が一定の比率で学内に存在する状況です。同大学は品川区大崎という立地の良さから、都市型キャンパスらしい多様性に富んだ学生コミュニティが形成されており、日常的に異文化接触の機会が得られる点が魅力です。また、国際理解を深める授業が複数設けられており、留学生との協働を前提としたカリキュラムが学習効果を高めています。
両校の留学生数を比較すると、人数の差は大きくありませんが、学びの環境としてはやや性質が異なります。東京経済大学は落ち着いた雰囲気で密度の高い交流が生まれやすく、立正大学は都市型キャンパスの多様性を活かした自然な異文化交流が特徴です。どちらが良いかは留学生との関わり方に求めるスタイルによって変わり、少人数で深く交流したいのか、多様性の中で広い世界に触れたいのかで選択が分かれると言えます。
海外提携校数
東京経済大学は、海外提携校数として 47 校を有しており、中規模私大としては比較的広い国際ネットワークを備えています。特に、学部の学びと親和性の高いアジア圏との連携が多く、短期・中期の語学研修や交換留学に結びつきやすい点が特徴です。また、提携校数が一定の裏付けになっているため、初めて海外に挑戦する学生でも利用しやすい制度が比較的整備されていることがうかがえます。大学として国際教育を重視している姿勢が明確に表れており、経済学の視点から異文化・他国の経済システムに触れたい学生にとって、実践的な学びの広がりが期待できます。
一方の立正大学は、海外提携校数が 45 校となっており、東京経済大学と比較すると数の上ではやや小規模です。ただし、提携校が少ないことがそのまま国際経験の機会不足を意味するわけではなく、特定地域に焦点を当てた形での連携を進めている点に特色があります。そのため、広く薄くというよりは、特定の地域・テーマに深く関わる海外学修を志向する学生に向いているとも言えます。また、学生規模を踏まえると、派遣枠の競争が比較的緩やかで、留学を希望する学生に機会が提供されやすいという利点もあります。
両大学を比較すると、提携校数においては東京経済大学のほうが優位であり、選択肢の多さという観点ではより幅広い国際経験が期待できます。一方で、立正大学は提携校数こそ少ないものの、特定領域に焦点化した学びの濃さや、派遣枠の利用しやすさといった別の強みが存在します。したがって、幅広い国際ネットワークを重視するなら東京経済大学、テーマ性や参加しやすさを求めるなら立正大学といった具合に、学生の志向によって評価が分かれる領域と言えます。
結局東京経済大学経営学部と立正大学経済学部のどちらが良いか

東京経済大学は、有名企業就職率 6.8% と一定の実績が見られ、特に公務員志向の学生への支援体制が機能している点が特徴です。また海外提携校数 47 校と国際ネットワークにも安定感があり、経済学を軸に広く社会へ進むための基盤が整えられています。全体として、実直にキャリア形成を進めたい学生に向いた落ち着いた環境が強みです。
立正大学は、有名企業就職率が 0% と公表値なしに近い点から、実績の幅は読み取りにくいものの、学生規模に対して海外提携校数 45 校を確保しており、特定地域への深い学びを重視する構成が特徴的です。また男女比 77 : 23 といった学生構成も比較的バランスが取れており、安定した学習コミュニティの中で専門教育を受けられる環境が整っています。
総合すると、就職領域の実績と国際面の選択肢を広く確保したい学生には東京経済大学が向き、少人数で深い学修や参加しやすい留学制度を重視する学生には立正大学が適しています。両校は進路の強みの方向性が異なるため、どのようにキャリアを描きたいかによって最適な選択が分かれる組み合わせと言えます。