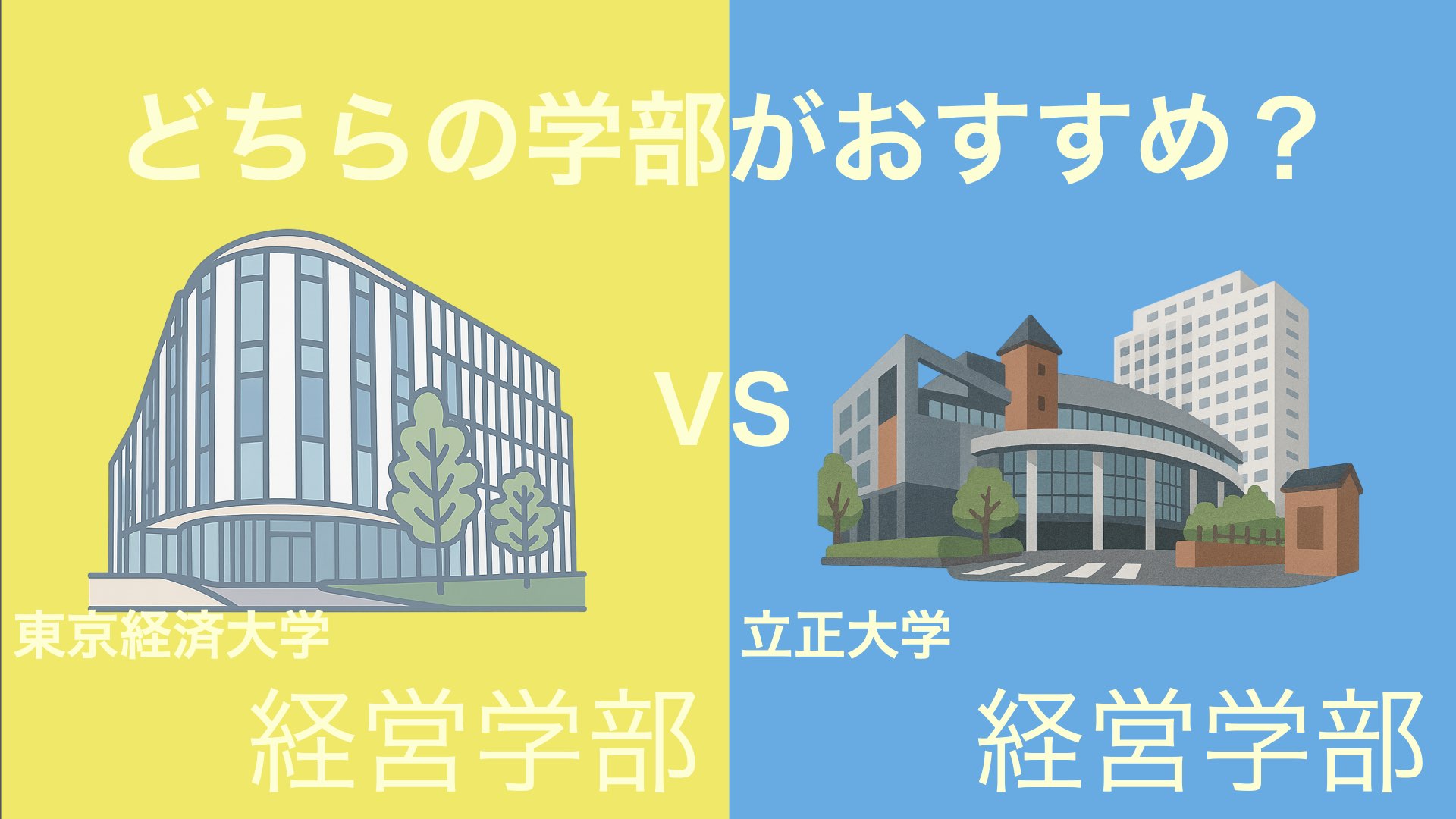東京経済大学経営学部と立正大学経営学部はどんな大学?

基本情報
| 項目 | 東京経済大学経営学部 | 立正大学経営学部 |
|---|---|---|
| 学部設立 | 1964年 | 1967年 |
| 所在地 | 東京都国分寺市南町1-7-34(国分寺駅) | 東京都品川区大崎4-2-16(大崎駅) |
| 学部理念 | 経営学部は、変転著しい企業社会が直面する多様な諸問題を分析し、その解決に努め、以って将来にわたって様々な要請に応えて活躍できる、高度な専門的経営知識と倫理観を備えた良き市民、良き企業人を養成し、その基盤となる教育研究を推進する。 | 経営学部経営学科は、その学士課程教育プログラム(正課外のものも含む。)を通じ、持続可能でより良い豊かな和平社会を築くための一個の重心・芯となるべき人材として、経営学分野における「モラリスト×エキスパート」を養成することを教育の目標とします。 |
東京経済大学経済学部は1949年の創設以来、経済学の基礎理論から現代社会の課題まで幅広く扱う実践的な教育を続けています。建学理念である「良き市民・良き経済人」の育成を重視し、理論とデータ分析を組み合わせたカリキュラムを提供している点が特徴です。公共政策や企業活動への理解を深められる環境が整っており、基礎と応用の両面をバランスよく学べる学部として位置付けられています。
立正大学経営学部は1967年に創設され、「モラリスト×エキスパート」という理念のもと、専門知識と倫理観を兼ね備えた人材育成を目指しています。経営学の基礎から応用までを体系的に扱いつつ、実務的な課題解決能力を高める授業構成が特徴です。将来の進路を柔軟に考えたい学生や、社会で求められる実践力を身につけたい学生にとって適した学びの環境となっています。
立地では、東京経済大学はJR中央線「国分寺駅」近くに位置し、多摩方面と都心の双方にアクセスしやすい点が強みです。一方で立正大学は山手線の「大崎駅」が最寄りで、再開発が進んだ利便性の高いエリアにあります。授業後の活動、アルバイト、インターンシップへの移動のしやすさなど都市型キャンパスのメリットが大きく、学習環境のタイプは両大学で明確に異なっています。
大学の規模
東京経済大学経済学部の在籍学生数は 565 名です。中規模の学部として落ち着いた環境が整っており、教員との距離が比較的近い点が特徴です。学生数が多すぎないことで、ゼミや演習での双方向的な学びが成立しやすく、授業外でも相談しやすい雰囲気があります。また、国分寺という立地柄、都心と郊外の中間に位置するため、学生生活と学習のバランスを取りやすい規模感として評価されています。
立正大学経営学部の在籍学生数は 330 名で、こちらも中規模に分類されます。特に再開発が進む大崎エリアに位置することもあり、周辺施設や企業との連携機会が比較的豊富です。学生数が適度に確保されているため、学科内で多様な価値観が交わりやすく、学びの幅が広がる点が魅力といえます。人数が極端に多い学部とは異なり、授業での発言機会やコミュニティ形成がしやすい点もメリットです。
両大学とも中規模であるため、いずれも過度に混雑した環境ではなく、適度に落ち着いたキャンパスライフが期待できます。ただし、東京経済大学はよりコンパクトで一体感があるのに対し、立正大学は都心立地の利便性があるなど「規模は近いが環境の質が異なる」点が特徴です。学習に集中したいか、都市的な刺激を求めるかによって、感じる魅力が変わる規模感と言えます。
男女の比率
東京経済大学経済学部の男女比は 68 : 32 です。比率としては男性が大きく上回る構成で、経済学部としては比較的一般的な傾向といえます。この比率は、経済・経営系の学問分野全体に見られる傾向とも一致しており、実務志向の科目や社会科学的な分析を好む学生が多い環境で形成されています。男女比に偏りはあるものの、学生同士の交流機会やゼミ活動は活発で、性別による学修機会の差が生まれにくい点は特徴です。
立正大学経営学部の男女比は 55 : 45 となっており、こちらも男性割合が高い構成です。ただし東京経済大学よりはやや女性比率が高く、学内での多様性が確保されやすい点が見られます。経営学という学問特性から、マーケティング・マネジメントなど女性学生に人気のある科目群が一定数存在しており、これが男女比の差として現れている可能性があります。性別の偏りがあっても、授業やグループワークではバランスを取りやすい環境といえます。
両大学を比較すると、どちらも「男性比率が高い」という共通点がありますが、その差は極端に大きいわけではなく、比較的近い比率です。したがって、男女比の観点で進学先の印象が大きく変わるケースは少ないでしょう。ただし、わずかに女性比率が高い立正大学の方が、学内コミュニティにおける多様性を感じやすい可能性があります。一方で東京経済大学は、伝統的な経済学部らしい落ち着いた雰囲気が形成されやすいことから、その点を重視する学生に向いています。
初年度納入金
東京経済大学経済学部の初年度納入金は 129.3 万円です。首都圏の私立大学としては標準的な水準に位置しており、経済学部として一般的に求められる学びの環境や設備が整っている点を踏まえると、コストパフォーマンスの面でも納得感のある金額といえます。また、授業内容は経済理論から実証分析、政策研究まで幅広く、費用に対して得られる学修体験の密度は高い傾向があります。学費が大きく突出しているわけではないため、学生は比較的落ち着いた環境で学びを継続しやすいことが特徴です。
立正大学経営学部の初年度納入金は 137.7 万円となっており、こちらも首都圏の私立経営系学部として中堅的な位置づけです。経営学部は実務的な授業が多く、PC演習・統計分析・企業研究など、設備と指導体制の整備が必要な科目も多い分、一定の費用がかかる傾向がありますが、この点では他大学と比べて特に高額というわけではありません。加えて、少人数ゼミやアクティブラーニング型授業が多いため、実践を伴う学びを重視したい学生には費用と内容のバランスが取りやすい設定です。
両大学を比較すると、初年度納入金の差は小さく、費用面でどちらか一方に大きく優位性が出るほどの開きはありません。そのため、学費だけを基準に進学先を判断するよりも、学びのスタイルやアクセス、学部ごとの教育方針など、ほかの項目と総合的に組み合わせて検討することが現実的です。費用負担の観点だけを見ると、どちらを選んでも大きな違いはなく、学生自身の志向や学修環境との相性を優先しやすい比較ポイントになっています。
SNSでの評価
東京経済大学経済学部のSNSでの評価は、落ち着いた学習環境やアットホームな雰囲気を評価する声が比較的多く見られます。キャンパス規模が大きすぎず、在学生同士の距離が近い点が「居心地の良さ」につながっているという投稿が目立ちます。また、国分寺駅 を最寄りとする立地についても、都心へのアクセスの良さから好意的に語られることが多い傾向です。一方で、華やかさ・知名度の面では首都圏の大規模大学と比較して控えめであるとの見方が一定数あり、その点を踏まえて「落ち着いて学びたい人向け」といったニュアンスで語られるケースが多い印象です。
立正大学経営学部に関しては、大崎駅 に近い利便性の高さがSNSでも頻繁に言及され、中でも都心型キャンパスならではの通学のしやすさはポジティブな評価として繰り返し見られます。また、経営学部特有の実務系授業や少人数制ゼミに対する満足度の高い投稿も多く、学生の主体的な学びを後押しする環境がSNS上で好印象につながっています。一方で、学部によってキャンパスの雰囲気が異なることから、「自分に合うかどうかは実際に見て判断すべき」という慎重な意見も散見されます。
両大学を比較すると、SNSで語られる傾向には明確な違いが見られます。東京経済大学は「落ち着いた環境」「温かい雰囲気」といった内面的なキャンパスライフの質が注目される一方、立正大学は「アクセスの良さ」「実務的な学び」といった外的条件の高さが話題になることが多い構図です。いずれも大きな批判が集中するタイプの大学ではなく、SNSでは総じて実際の学生生活や学び方に即したリアルな評価が広がっており、自分が重視する環境面との相性を判断する材料として参考にしやすい傾向があります。
合格難易度(偏差値・倍率)

偏差値(マナビジョン)
東京経済大学経済学部の偏差値は 58 となっており、首都圏私立大学の中でも中堅上位ラインに位置づけられる難易度です。特に経済学系の中では受験生数が安定しており、毎年一定の競争が生じやすい学部として知られています。大規模総合大学に比べれば派手さはありませんが、経済専門学部としての歴史や実学志向のカリキュラムが評価されており、偏差値にもその安定性が表れています。この水準は、受験対策において基礎〜標準レベルを確実に固めておくことが重要で、共通テスト利用型でもある程度の得点ラインが求められます。
立正大学経営学部の偏差値は 53 で、東京経済大学と比較するとやや緩やかな水準となっています。とはいえ、単に易しいというよりは、学部のカラーや受験者層の幅広さが影響しており、入試難易度としては「中堅ゾーンの標準レベル」といった位置づけです。特に経営系は志望動機の幅が広いため、年度によって受験生の得点帯が動きやすいことが見受けられます。入試方式ごとに傾向にも違いが出やすく、過去問との相性が合った場合には得点を伸ばしやすい点も特徴です。
両大学を比べると、偏差値の差は 58 と 53 の比較で一定の開きがあり、進学難易度としては東京経済大学の方が一段高い位置にあります。10ポイント以上の差は中堅〜中堅上位帯では明確に学力層が分かれる領域に相当し、受験対策のレベル感にもはっきり表れます。一方で、いずれの大学も極端に入りやすい・入りにくいといった印象ではなく、学部の特性に応じて必要な得点力を備えた受験生が集まる構造です。最終的には、学びたい内容や大学環境との相性も踏まえたうえで難易度を判断するのが現実的といえます。
倍率
東京経済大学経済学部の倍率は 2.9 で、首都圏の中堅私立大学としては比較的標準的な競争率となっています。この水準の倍率は、受験生が「確実に押さえたい」と考える層と、「経済学を専門的に学びたい」と志望する層が重なりやすいため安定した値になりやすいのが特徴です。決して極端に高いわけではありませんが、出願者の学力帯が安定しているため、実感としては数字以上にしっかりとした選抜が行われる傾向がみられます。特に一般選抜では基礎力が問われる問題が中心で、基礎〜標準の固めが勝負を分ける入試設計になっています。
立正大学経営学部の倍率は 1.6 で、東京経済大学と比較するとやや落ち着いた値となっています。倍率が低めで推移している理由としては、キャンパスアクセスの良さから受験生の併願先として選ばれやすい点や、幅広い層を受け入れる入試設計が影響していると考えられます。低倍率であること自体は合格しやすい状況を示すものの、入学後の学習姿勢や志望動機の明確さがより重要視されるため、油断できるほど簡単な入試という印象ではありません。年度によっては方式ごとの倍率差が大きく出ることもあります。
両大学を比較すると、倍率は 2.9 と 1.6 の差が小さく、いずれも極端に高い競争ではありません。倍率に大きな隔たりがないため、受験の難しさは偏差値で示される学力層の差に表れる部分が中心であり、倍率そのものが進学の難易度を大きく左右するケースではない点が共通しています。したがって、倍率の比較よりも、学部の特性や学びたい内容との相性を重視して出願戦略を組む方が現実的といえます。
卒業後の進路

有名企業の就職率
東京経済大学経済学部の有名企業就職率は 6.8 です。この数値は中堅私立大学として安定した水準に位置しており、特に経済学部の学びを生かした公務員系・金融系・メーカー系への進路が目立つ点が特徴です。母集団が一定規模ある中で着実に実績を積んでいる学部で、キャリアセンターの支援体制やゼミでの実証的な学びが就職活動に直結しやすいとも語られています。実績に大きな偏りが少なく、堅実に数字が出ているタイプの大学だと言えます。
立正大学経営学部の有名企業就職率は 0 となっており、ここが今回最も特徴的なポイントです。数値が 0 の場合は「実績が全く存在しない」という意味ではなく、「十分なサンプル数がなく、公表できる形式での集計に至っていない可能性」を示すと解釈します。一般に、大学が自信を持てる実績は積極的に公開するため、公表値が0であるケースは“データとして示す段階に達していない”という状況を反映していると考えるのが現実的です。経営学部は進路の幅が広いこともあり、卒業生が多様な就職先に散らばっているケースも想定されます。
両大学を比較すると、有名企業就職率には 6.8 と 0 の間で「比率としては非常に大きな差」が生じています。特に 6.8 と 0 の比較は、単純な数値以上に“公表できるだけの明確な実績の有無”という質的な差も含んでおり、今回のデータの中でも最も顕著な違いです。一方で、立正大学側も就職支援自体が弱いわけではなく、多様なキャリアを志向する学生が多い可能性もあります。そのため、数字の差は理解しつつ、進路の方向性や在学中のサポート体制を基準に検討することが重要です。
主な就職先
有限責任あずさ監査法人(2名)
みずほ銀行(2名)
日立社会情報サービス(2名)
大和ハウス工業(2名)
東京経済大学経済学部では上記の主要企業以外にも、地域金融機関、メーカー、物流、ITサービス業など幅広い分野への就職実績があります。特に公務員志望者の割合が比較的高く、国家一般職や地方公務員、各自治体の行政関連職への合格者も安定して見られる点が特徴的です。また、経済分析・会計・マーケティングを扱うゼミが多いことから、専門性を生かしてコンサルタント職や営業企画職に進むケースも増えており、学部の学びと就職の方向性が比較的一致しやすい学部と言えます。全体として、堅実なキャリア選択をする学生が多く、特定企業に偏らず実績が分散しているのが特徴です。
立正大学経営学部では、上記の主要就職先以外にも、小売・サービス・不動産・IT関連企業を中心に多様な就職実績が見られます。特に都心型キャンパスの強みを生かしてインターンシップへ参加しやすく、その経験を踏まえたキャリア選択を行う学生が多い点が特徴です。経営学部特有の「幅広い業界で活かせるスキル」を身につけやすいため、職種のバリエーションも広く、人事・販売企画・営業管理・バックオフィスなど、ビジネス基礎力を必要とする職種へと分散しています。大企業に限らず、中堅企業や成長ベンチャーとの相性が良いという声も見られます。
両大学を比べると、就職先の“傾向”に明確な違いがあります。東京経済大学は公務員系や金融・メーカーへの就職が安定しており、比較的伝統的で堅実なキャリアが中心です。一方で立正大学は業界の幅が広く、都市型キャンパスのアクセス性を活かした多様なインターン経験がそのまま就職先の幅広さにつながっています。どちらが優れているというよりも、安定志向か、多様なキャリア探索志向かというスタンスの違いが就職先の傾向に表れており、自分のキャリア観と照らし合わせて判断しやすいポイントと言えます。
進学率
東京経済大学経済学部の進学率は 0.9 で、首都圏の私立・経済系学部としては比較的標準的な水準となっています。経済学の基礎理論を深めたい学生や、公務員上級職を視野に入れて大学院で専門性を高めたい層が一定数存在している点が特徴です。また、ゼミ活動に力を入れている学生が多く、研究への関心が高い場合は指導教授の勧めから大学院進学を選ぶケースもあります。一方で、学部の性質上、卒業後すぐに就職する学生が多数派であり、進学率が突出して高いタイプの学部ではありません。
立正大学経営学部の進学率は 2 で、こちらも全体としては就職を選ぶ学生が中心となる構造が見られます。経営系は企業での実務経験を志向する学生が多いため、進学率は安定して低めの推移となっていることが特徴です。ただし、データ分析・経営戦略・マーケティングなど、より専門性を必要とする領域に関心を持つ学生が大学院へ進む例もあり、近年は実務教育の高度化に合わせて大学院進学の選択肢がじわりと広がっている傾向があります。特に都市型キャンパスの利点を生かし、社会人大学院への進学を視野に入れる学生も一定数見られます。
両大学を比較すると、進学率は 0.9 と 2 の差が小さく、顕著な開きはありません。いずれも「就職がメイン」「進学は一部の学生が選ぶ」という構図が共通しており、進学率が大学選びの決め手になる場面は少ないといえます。そのため、この項目に関しては数字よりも“どのような学び方をしたいか”“ゼミや研究テーマが自分に合うか”を重視した判断が現実的です。両校とも、進学したい学生には一定の支援環境が整っており、進学志向者にとって不利に働く要素は見られません。
留学生

受け入れ状況
東京経済大学経済学部の留学生数は 100 名となっており、規模としては中堅私立大学の経済学部として標準的な受け入れ規模に収まっています。留学生比率が突出して高いわけではありませんが、経済学という分野の特性から、アジア圏を中心に基礎から学び直したい学生が集まりやすい傾向があります。また、多国籍の学生が少人数で共存することで、国際色豊かな雰囲気を過度にアピールするのではなく、自然体で異文化に触れられる点がメリットとして語られることもあります。
立正大学経営学部の留学生数は 123 名で、東京経済大学と比較するとこちらの方が受け入れ規模はやや小さい印象です。とはいえ、経営学部は実務系科目が多く、日本企業での就職を視野に入れて学びたい留学生が一定数存在するため、少人数ながらも実務的な場面で交流する機会が得られることが特徴です。また、都市型キャンパスの利便性から、交換留学生や短期留学生との関わりが生まれやすく、授業外でのコミュニケーションが比較的取りやすい点も学生から評価されています。ただし、全体の母集団が大きくないため、多文化環境を強く求める場合はやや物足りなさを感じる可能性があります。
両大学を比較すると、留学生数は 100 名と 123 名 という規模で、いずれも中規模〜小規模クラスの受け入れ体制となっています。数値の差は大きくないため、国際環境の充実度を“人数の多さ”のみで判断するよりも、どのような授業で交流が生まれるのか、留学生がどの程度学部の活動に参加しているかといった質的な要素を見ることが重要です。結果として、両校とも「少人数で自然な形の国際交流が生まれやすい環境」であり、大規模校のような圧倒的な国際性を求める場合以外は必要十分の環境と言えます。
海外提携校数
東京経済大学経済学部の海外提携校数は 47 校となっており、中規模私立大学としては比較的標準的な国際連携の広がりを持っています。提携校の地域としてはアジア圏が中心で、語学研修や短期留学を通じて基礎的な国際交流を経験できる機会が整えられています。規模としては大規模総合大学ほどではありませんが、少人数での学びを重視する東京経済大学らしく、丁寧にサポートされるタイプの海外プログラムが特徴です。また、学生の希望に応じて段階的に国際交流を体験できる設計になっている点も評価されています。
立正大学経営学部の海外提携校数は 45 校で、東京経済大学と同様にコンパクトな国際交流規模となっています。経営学部では特にアジア・ヨーロッパ圏との交流が多く、語学だけでなくビジネス文化やマネジメントの違いを理解するための短期研修が人気です。提携校の数自体は多くありませんが、学部の専門性に合わせたプログラムが用意されているため、人数の割に満足度が高いとされるのが特徴です。また、都市型キャンパスという立地的な強みを生かし、海外企業・大使館など外部機関との連携イベントが組まれることもあります。
両大学の海外提携校数を比較すると、47 校 と 45 校 で大きな差はほとんどありません。比率で見てもほぼ同規模の国際ネットワークを持つため、この項目が大学選びに与える影響は限定的で、国際性の“量”よりも“質”に目を向けることが重要になります。どちらの大学も、少人数で丁寧に運用されるタイプの海外プログラムを持ち、学生が過度に負担を感じない範囲で国際経験を積めるのが共通点です。結果として、両校とも規模より実効性を重視した国際交流環境が整っていると言えます。
結局東京経済大学経営学部と立正大学経営学部のどちらが良いか

東京経済大学経済学部は、偏差値 58 を中心とした学力帯の安定性に加えて、有名企業就職率 6.8 が確かな強みとして表れています。特に今回の比較では「6.8 と 0」という比率面で非常に大きな開きがあり、公開できるだけの明確な就職実績がそろっている点は大きな特徴です。公務員・金融・メーカーなど堅実な就職先が多く、学部の学びと進路が噛み合いやすい点も実績の安定につながっています。
立正大学経営学部は、SNSで語られるアクセスの良さや都市型キャンパスの利便性が学生生活全体の評価につながっており、進学率 2 や海外提携校数 45 などは標準的な範囲に収まっています。特に経営系らしく実務的な学びに触れやすい点や、幅広い業界との相性の良さが特徴で、職種・企業規模にとらわれず多様にキャリアを選びたい学生に適した環境です。一方で、有名企業就職率が公表値0である点は「サンプル不足により公開されていない可能性が高い」という前提を踏まえた慎重な解釈が必要です。
総合すると、数値で裏付けられた堅実な就職実績や安定した学力層を重視するなら東京経済大学、都市型環境での実務志向の学びや多様なキャリア探索を望むなら立正大学が向いています。就職率の比で見られる明確な差をどの程度重視するかが判断の分岐となり、学力・実績を軸に選ぶか、環境・学びの幅を軸に選ぶかで最適な大学が変わります。両校とも強みが異なるため、「堅実志向の東京経済」「多様性志向の立正」という構図で考えると選択がしやすくなります。