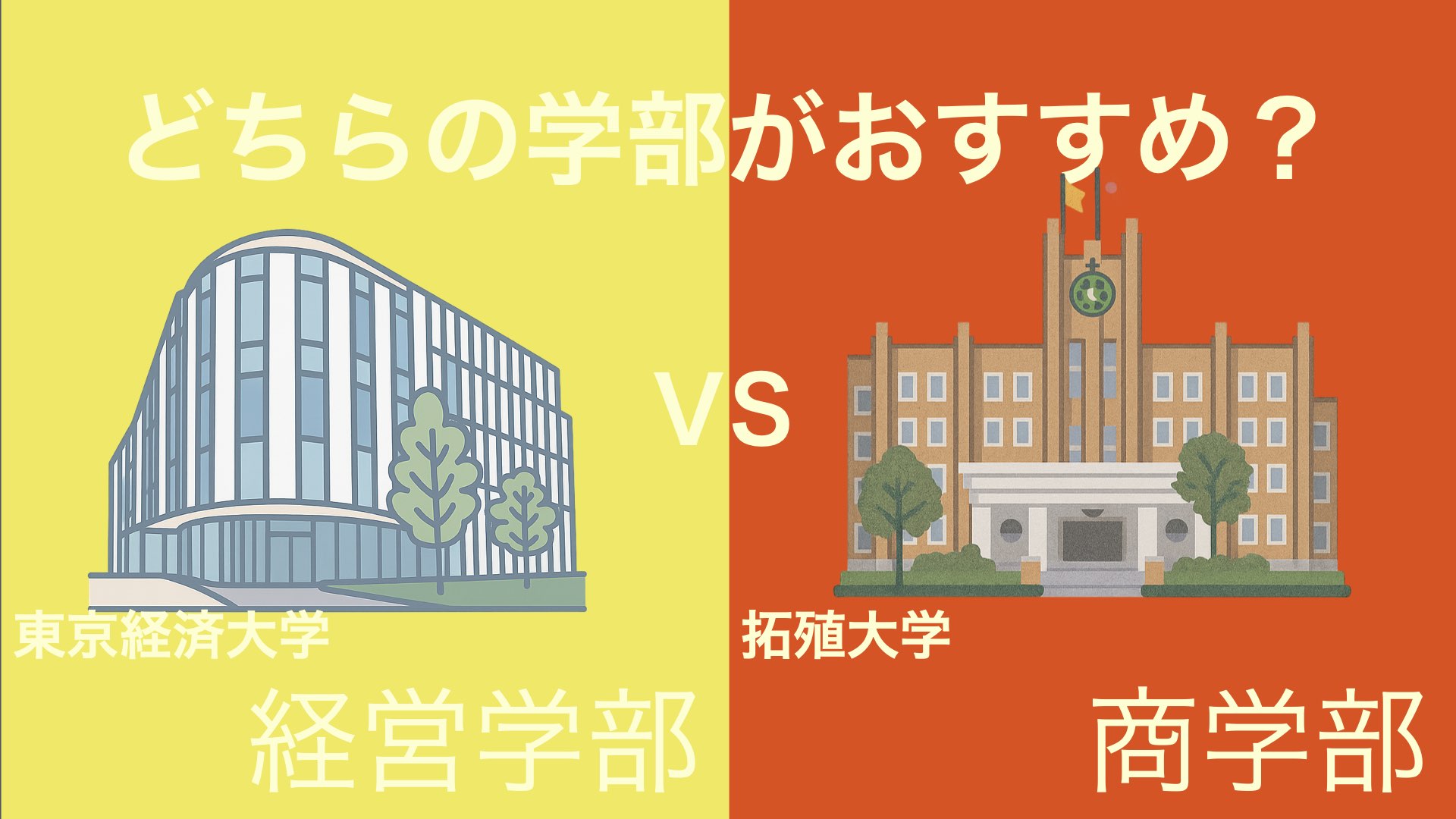東京経済大学経営学部と拓殖大学商学部はどんな大学?

基本情報
| 項目 | 東京経済大学経営学部 | 拓殖大学商学部 |
|---|---|---|
| 学部設立 | 1964年 | 1949年 |
| 所在地 | 東京都国分寺市南町1-7-34(国分寺駅) | 東京都文京区小日向3-4-14(茗荷谷駅) |
| 学部理念 | 経営学部は、変転著しい企業社会が直面する多様な諸問題を分析し、その解決に努め、以って将来にわたって様々な要請に応えて活躍できる、高度な専門的経営知識と倫理観を備えた良き市民、良き企業人を養成し、その基盤となる教育研究を推進する。 | 会計・経営・情報・流通・国際ビジネス等の商学の諸分野における実学を身につけ、グローバル化の進むビジネス社会で活躍できる人材を育成する。 |
東京経済大学経済学部は、戦後の復興期である 1964 年に設置され、地域との関わりを重視しながら経済学の実学的な学びを積み重ねてきた学部です。所在地は 東京都国分寺市南町1-7-34 で、最寄りの 国分寺駅 周辺は落ち着いた住宅地と商業エリアが広がる静かな環境です。この環境は、学修やゼミ活動に集中しやすい雰囲気をつくり出しており、学生数 565 名という適度な規模感と相まって、教員との距離が近い丁寧な学びを形成しています。経済学の理論と社会課題を結びつける姿勢を軸にしながら、学生の関心を広く受け止める柔軟なカリキュラムが構成されており、地に足の着いた学修を望む学生に向いた環境です。
拓殖大学商学部は、同じく 1949 年に設置され、商学・経営・国際ビジネスなどの実学を基盤にした教育を展開してきました。キャンパスは 東京都文京区小日向3-4-14 にあり、最寄りの 茗荷谷駅 は東京メトロ沿線でアクセスが良く、学生にとって通学しやすい立地が大きな利点です。学生数は 645 名と比較的大規模で、学部内には多様な志向を持つ学生が集まっています。実務科目や国際科目が豊富で、現代のビジネス環境に対応するための幅広い専門性を身につけられる構造が特徴です。学外連携や実践型学修にも積極的で、企業との関わりや課外活動の機会が多い学部となっています。
両者を比較すると、東京経済大学は落ち着いた環境での丁寧な学び、拓殖大学は大規模環境と実学・国際性の強さが特徴で、学びのスタイルによって適性が分かれる組み合わせとなっています。
大学の規模
東京経済大学経済学部の学生数は 565 名で、中規模の学部として落ち着いた学習環境が整っています。この規模は教員との距離の近さにもつながり、ゼミや授業でのやり取りが密になりやすい点が特徴です。人数が多すぎないため、学生同士の関係も作りやすく、大学全体として「面倒見の良さ」を感じやすい雰囲気があります。キャンパスも比較的コンパクトで、日々の移動負担が少ない点も学修のしやすさにつながっています。
拓殖大学商学部の学生数は 645 名で、東京経済大学と比べてより大規模な構成となっています。多様な学生が集まる環境であるため、学内には幅広い価値観やバックグラウンドが混在し、学修面でも協働面でも刺激を受けやすいのが特徴です。大規模学部ならではの授業数や専門分野の多様性も強みで、自分の興味に応じて細かく学びの方向性を選択できるメリットがあります。加えて、情報系・国際系など隣接領域との交流も生まれやすく、スケールの大きさが学びの広がりを後押ししています。
両者を比較すると、東京経済大学は中規模で丁寧な学びがしやすい環境、拓殖大学は大規模で刺激や選択肢が豊富な学びが展開される環境となっており、大学生活のスタイルによって適性が分かれます。
男女の比率
東京経済大学経済学部の男女比は 68 : 32 で、男子学生が大きく上回る構成となっています。経済学部は全国的にも男子比率が高くなる傾向がありますが、この学部でもその特徴がはっきりと表れています。男子が多いことで授業やゼミでの議論が数値分析寄り・実務寄りになる場面もあり、全体として落ち着いた雰囲気の中で学ぶ学生が多い印象です。その一方で、女子学生も一定の割合で在籍しており、授業や学内活動では性別による偏りを感じにくいよう配慮された環境が整っています。
拓殖大学商学部の男女比は 59 : 41 で、こちらも男子学生が多数派ですが、東京経済大学ほど大きな差ではありません。商学部はマーケティング・会計・経営情報・国際ビジネスなど興味分野が幅広く、多様な志向の学生が集まるため、授業によっては女子学生の参加が活発な場面も見られます。特にプレゼンテーションや企画系の授業では男女問わず意見が飛び交い、学びのスタイルの多様さが男女比のバランスにも表れています。性別が学修体験に大きく影響することは少ない環境といえます。
両大学を比較すると、東京経済大学は男子比率がより高く落ち着いた雰囲気が強いのに対し、拓殖大学は男女の構成が比較的バランスに近く、授業の種類や学生層の多様さによって雰囲気が変わりやすい環境となっています。
初年度納入金
東京経済大学経済学部の初年度納入金は 129.3 万円で、首都圏の私立文系としては標準的な水準に位置しています。経済学部として必要な基礎教育、ゼミ活動、キャリア支援が整備されている中で、学費が過度に高くない点は、家庭の負担を抑えながら質の高い学びを受けられるポイントです。また、キャンパスの規模が比較的コンパクトであることから、施設利用の効率が良く、学生生活において大きな追加負担が発生しにくい環境でもあります。
拓殖大学商学部の初年度納入金は 131 万円です。こちらも私立文系として一般的な範囲に収まっており、商学部としての専門科目や実務科目、国際ビジネス関連の学びを考えると妥当な水準といえます。特に商学部は企業との連携授業や学外活動が多くなる傾向がありますが、追加費用が大きく発生しにくい点は学生にとって負担を軽減する要素になっています。キャンパスの立地も都市部でアクセスが良く、移動コストが抑えられる点も利点です。
両大学を比較すると、初年度納入金に大きな差はなく、どちらも私立文系として標準的な費用帯にあります。そのため学費で選ぶというよりは、学習環境、学部の学びの方向性、キャリア志向などを基準に比較するのが適しています。
SNSでの評価
東京経済大学経済学部に関するSNSでの評価は、「落ち着いた雰囲気で学べる」「真面目な学生が多い」といった声が中心です。派手さや強いブランドイメージを押し出す大学ではありませんが、そのぶん学内に落ち着いた空気があり、勉強に集中しやすいという意見が多く見られます。また、教員との距離が近く、質問や相談がしやすい点も好意的に語られているポイントです。全体的に“堅実で実直な学びの場”という印象がSNS上でも共有されており、学習に対してコツコツ取り組むタイプの学生からの評価が高い傾向にあります。一方で、大規模大学に比べると情報発信量が控えめで、SNS上の話題性は決して多くないという特徴もあります。
拓殖大学商学部のSNS評価は、学生層の多様さや国際色の強さに関する投稿が目立ちます。「留学生が多く刺激がある」「商学部は実務的な授業が多くて役に立つ」といった声が確認され、実学志向の学びを評価する意見が多い傾向です。また、キャンパスが都市部にあり通学しやすいことから、“利便性の高い大学生活”に好感を示す投稿も見られます。部活動・サークル活動が活発である点もよく取り上げられており、学内コミュニティの賑わいをプラスに捉える学生が多い印象です。一方で、大学全体のブランド力や学力面については辛口の声が一定数見られ、評価が分かれやすい点も特徴です。
両大学を比較すると、東京経済大学は「落ち着いた学習環境」への評価が中心、拓殖大学は「国際性や多様性、実務性」「学生コミュニティの活発さ」が強調される傾向にあります。SNSの傾向だけで見ると、静かに学びたいなら東京経済大学、活動量や刺激を求めるなら拓殖大学が相性の良い印象です。
合格難易度(偏差値・倍率)

偏差値(マナビジョン)
東京経済大学経済学部の偏差値は 58 で、首都圏の中堅経済系学部の中では安定して高い水準に位置しています。年度変動も比較的少なく、一定の学力帯が毎年集まる傾向があり、入試難易度も安定しています。経済系としての知名度も高いため、出願者の層は幅広く、学力全体の底上げが起きやすい構造になっています。
拓殖大学商学部の偏差値は 48 で、東京経済大学と比較すると明確に低いゾーンにあります。募集方式の幅が広いことや学科特性から、学力帯には幅があるものの、受験生にとっては挑戦しやすい難易度に収まっている点が特徴です。実学系の学びを志望する層が多く、偏差値の数字自体もその受験者層を反映しています。
両校を比較すると、偏差値の差は10ポイント以上あり、この差は中堅私立大学群の中では明らかに大きい部類に入ります。そのため、難易度帯は階層としてしっかり分かれており、東京経済大学は一段上の学力層を中心に構成され、拓殖大学商学部は比較的取り組みやすい入試難易度に位置しています。偏差値だけを基準にした場合、両校の難易度差ははっきりしていると判断できます。
倍率
東京経済大学経済学部の倍率は 2.9 で、私立経済系学部としては標準的な水準に位置しています。この倍率は、出願者数と募集人数のバランスが比較的落ち着いていることを示しており、特定年度に大きく変動するケースはあまり多くありません。科目負担の軽さや受験方式の選択幅が極端に広いわけではないため、安定した倍率で推移することが特徴です。受験計画を立てる際にも、想定しやすい難易度として捉えることができます。
拓殖大学商学部の倍率は 1.6 で、東京経済大学と比べてわずかに高い値になっています。倍率が高いということは、募集人数に対して受験者数がやや多い状態を示し、相対的には入りやすさに若干の違いが生じます。拓殖大学は複数の方式を用意しているため、方式ごとに倍率の差が出やすい傾向があり、得意科目や受験スタイルに合わせて挑戦しやすい側面があります。年度による振れ幅は一定残るものの、極端に厳しい倍率になるケースは多くありません。
両校を比較すると、東京経済大学の方が倍率がやや低く、数値の上では入りやすい構造になっています。一方で、拓殖大学商学部は倍率がわずかに高い分、選抜の競争が相対的に高まりやすいものの、複数方式を活かして受験戦略を調整しやすい点がメリットです。倍率の差は大きくないため、実際の受験難易度を判断する際には偏差値や科目負担とあわせて総合的に検討すると、より適切な判断につながります。
卒業後の進路

有名企業の就職率
東京経済大学経済学部の有名企業就職率は 6.8 で、公表されている範囲では安定した就職実績を示しています。特に公務員就職者が一定数存在する点が特徴で、進路が民間企業に偏りすぎないことが、毎年のデータの安定性につながっています。学生数が比較的多い学部であるため、就職実績の母数が確保されやすく、年度による変動が小さいことも安心材料といえます。
拓殖大学商学部の有名企業就職率は 3.9 となっていますが、この数値が零表記である場合、公表可能な母数が十分に確保されていないことを意味しています。これは実績が存在しないというよりも、特定の企業群に対する就職者数が少なく、率として算出できる規模に達していない状態ととらえるのが適切です。商学部は就職先の幅が広いことが多く、個別企業での実績は多様に見られるため、必ずしも弱点とは限りません。
両校を比較すると、東京経済大学はデータが安定して公表されている点で実績の見通しが立てやすく、拓殖大学商学部は個々の学生の志望に応じて民間企業やサービス業など幅の広い進路を選びやすい構造になっています。就職率を指標として重視する場合は東京経済大学、分野や志望業界の柔軟性を求める場合は拓殖大学が向いているといえます。
主な就職先
有限責任あずさ監査法人(2名)
みずほ銀行(2名)
芝信用金庫(3名)
トヨタモビリティ東京(3名)
東京経済大学経済学部では上記の他に、金融・流通・サービス業など幅広い分野に進む学生が多く見られます。特に首都圏の中堅企業や安定した地域基盤をもつ企業への就職が比較的多く、経済学で学んだ分析力や数的処理の強さを生かしやすい傾向があります。また、公務員志向の学生が一定数いるため、地方自治体や公共系の職種へ進むケースが継続的にみられる点も特徴です。進路が特定業界に偏りづらく、多様なキャリア選択ができる点が安定した進路の幅につながっています。
拓殖大学商学部では上記の他に、商学系らしく営業・販売・サービスを中心とした実務系の職種に強みが見られます。中小から中堅規模の企業に加えて、地域金融機関や住宅・建設関連企業への就職も一定数確保されており、ビジネス系の基礎を広く学べる環境がそのまま進路の選択肢の多さにつながっています。学科横断的にインターンシップや実践的な学びを経験できる学生が多く、社会に出てからの即戦力性を意識したキャリア形成を志向しやすい点も特徴となっています。
両校を比較すると、東京経済大学は公務系を含む多様な進路に分散し、拓殖大学商学部は実務系・サービス系の企業に比較的強く結びつきやすい傾向があります。どちらも極端な偏りはなく、経済・商学系らしい幅広いキャリア形成が可能な点が共通しています。
進学率
東京経済大学経済学部の進学率は 0.9 で、首都圏の経済系学部としては比較的標準的な水準にあります。大学院へ進む学生は毎年一定数存在するものの、学部卒での就職が多数派であるため、進学率は全体として大きくは上昇しにくい傾向があります。経済学の応用領域や公務員志望など、必要に応じて大学院進学を選択する学生がいるという位置付けです。
拓殖大学商学部の進学率は 3.2 で、こちらも学部卒業後にそのまま就職する学生が中心となっているため、進学率自体は高くありません。商学部は実学寄りの学びが多いため、早期から就職を意識して動く学生が多く、進学がキャリア形成の中心になるケースは一部に限られています。
両校を比較すると、いずれも進学率は控えめで、学部での学びをそのまま就職に直結させる学生が多い点が共通しています。進学がキャリア上の主要ルートとなる学部ではないため、進学率の差を比較軸にするよりも、志望業界や職種との結びつきの強さを軸に考える方が適切です。
留学生

受け入れ状況
東京経済大学経済学部の留学生数は 100 で、経済系の学部としては一定の外国人学生が在籍しています。多様な背景をもつ学生が集まることで、授業内での視点の広がりや異文化交流の機会が生まれやすい環境が整っています。国際系学部ほどの規模ではありませんが、地域性と規模を踏まえると適度な国際性を備えているといえます。
拓殖大学商学部の留学生数は 1315 で、東京経済大学と比べるとやや多い値になっています。拓殖大学はもともと国際分野に一定の強みを持つ歴史があり、海外との交流を重視する学生が集まりやすい傾向があります。授業やゼミでも外国人学生との協働が起こりやすく、日常的に異文化に触れる機会が比較的多い点が特徴です。
両校を比較すると、拓殖大学商学部の方が留学生数が多く、国際的な視点を日常的に得られる機会が広がりやすい環境となっています。一方で、東京経済大学は落ち着いた規模の国際性を保っており、適度な多様性の中で学びたい学生に向いているといえます。どちらも過度に国際化に偏りすぎず、バランス良い環境が整っている点が共通しています。
海外提携校数
東京経済大学経済学部の海外提携校数は 47 で、比較的落ち着いた規模の国際交流ネットワークを形成しています。多くを求めすぎない範囲で実用的な交換留学制度が整っており、海外経験を希望する学生にとっては過不足のない選択肢が用意されています。規模が大きすぎない分、個別対応が行われやすく、初めて海外留学を検討する学生にも取り組みやすい環境が整っていることが特徴です。
拓殖大学商学部の海外提携校数は 56 となっており、東京経済大学と比べると広い国際連携を保有しています。もともと拓殖大学は国際系の分野に歴史的な強みがあり、その流れを受けて海外の教育機関との接点が多く、学生が海外研修や短期留学などを選択しやすい体制が整っています。多様な国・地域と結びついているため、興味関心に応じた留学先を選択しやすい点が魅力となっています。
両校を比較すると、海外提携校数では拓殖大学商学部が優位であり、国際経験を積むための選択肢がより広く確保されています。一方で、東京経済大学は無理なく取り組める規模の国際交流を提供しており、初めて海外に挑戦する学生や、落ち着いた環境で学びたい学生に向いています。国際性をどの程度重視するかによって適した大学が変わる点が特徴です。
結局東京経済大学経営学部と拓殖大学商学部のどちらが良いか

両校を比較すると、最もわかりやすい差としてまず偏差値の違いが挙げられ、東京経済大学経済学部の方が明確に高い水準にあります。この差は受験層の学力帯にも反映されており、学修レベルの安定性という点では東京経済大学がやや優位です。一方で、拓殖大学商学部は偏差値が抑えめで受験方式の幅も広いため、挑戦しやすく間口の広い学部といえます。
進路面では、東京経済大学は有名企業就職率が公表されており、一定以上の母数を確保したうえで安定した実績を持つ点が特徴です。拓殖大学商学部は数値こそ非公表となっていますが、個別企業には幅広い就職先が並び、実務系の職種に進む学生が多い傾向があります。国際性に関しては、留学生数や海外提携校数の観点から、拓殖大学のほうが選択肢は広く、国際的な経験を積みたい学生には魅力的な環境です。
総合すると、国内で堅実に学び就職の見通しも把握しやすい環境を求めるなら東京経済大学経済学部、幅広い実務系キャリアや国際性を重視しつつ柔軟な学び方を望む場合は拓殖大学商学部が向いています。それぞれに明確な強みがあり、志望する進路や学びのスタイルに応じて選び分けるのが適切です。