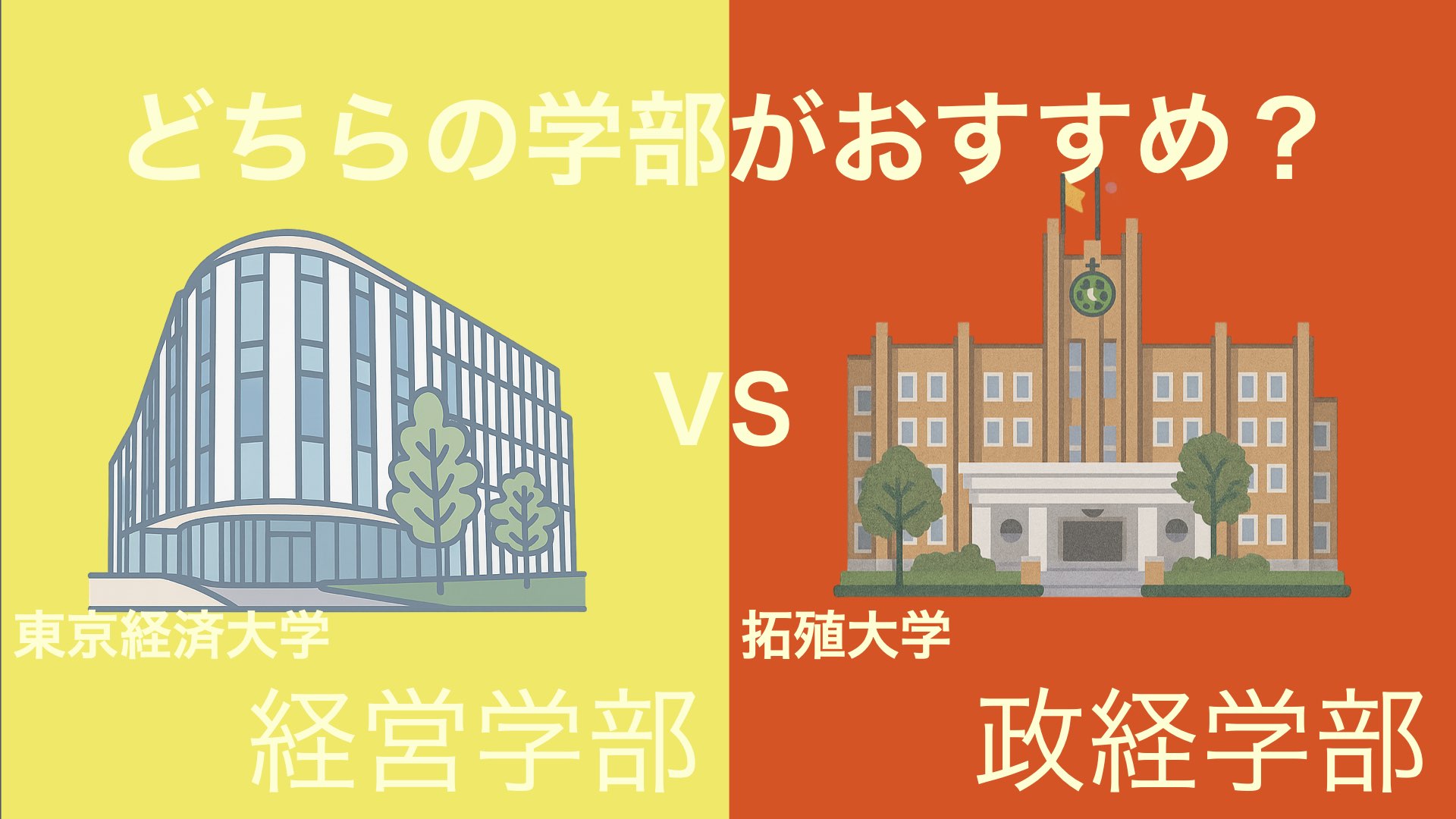東京経済大学経営学部と拓殖大学政経学部はどんな大学?

基本情報
| 項目 | 東京経済大学経営学部 | 拓殖大学政経学部 |
|---|---|---|
| 学部設立 | 1964年 | 1949年 |
| 所在地 | 東京都国分寺市南町1-7-34(国分寺駅) | 東京都文京区小日向3-4-14(茗荷谷駅) |
| 学部理念 | 経営学部は、変転著しい企業社会が直面する多様な諸問題を分析し、その解決に努め、以って将来にわたって様々な要請に応えて活躍できる、高度な専門的経営知識と倫理観を備えた良き市民、良き企業人を養成し、その基盤となる教育研究を推進する。 | 法律学・政治学分野における理論的・実践的知識を身につけ、グローバル化時代の実社会の諸問題を的確に指摘し、解決できる能力と意欲を持った人材を育成する。 |
東京経済大学経済学部は、経済学の基礎から応用領域までを幅広く学べるカリキュラムを備えており、理論を土台としつつ現代の経済社会で求められる分析力や課題解決力を養うことができます。キャンパスは 東京都国分寺市南町1-7-34 に位置し、最寄りの 国分寺駅 から通学しやすい環境にあります。歴史的にも1949年の設置以来、地域社会との結びつきを保ちながら実務的かつ堅実な経済教育を展開してきた点が特徴です。学生規模は 565 名で、適度な規模感のもとで学びやすい環境が整っています。
拓殖大学政経学部は、政治学と経済学を横断的に学べる学部として特徴があり、理論だけでなく現実社会の課題を読み解く力を強化する教育方針を掲げています。所在地は 東京都文京区小日向3-4-14 で、最寄りの 茗荷谷駅 から徒歩圏内にあり、都心で学べる利便性の高さが魅力です。1949年創設と長い歴史を持ち、国際性にも強みを持つ大学として幅広いテーマに触れられる環境が整っています。学生数は 853 名で、学部規模は比較的大きく、多様な学生層と関わりながら学修を進められる点が特徴です。
両校を比較すると、東京経済大学はコンパクトな規模と落ち着いた学修環境が魅力で、経済学に的を絞った学びを深めやすい構造になっています。一方、拓殖大学政経学部は政治と経済を横断して学べる点や都心立地によるアクセスの良さが強みで、多様な学生が集まるダイナミックな環境が特徴です。学びのスタイルやキャンパスの雰囲気の違いが明確で、自分の志向や生活スタイルに合わせて選びやすい比較となっています。
大学の規模
東京経済大学経済学部の在籍学生数は 565 名で、経済系学部としては中規模に位置する落ち着いた人数構成となっています。この規模感は、教員との距離が比較的近く、ゼミ活動や専門科目での双方向的な学びを重視したい学生にとって適した環境といえます。キャンパス全体もコンパクトで移動がしやすく、日常的に同じ学生同士が顔を合わせることで、学修面でも生活面でも安定したコミュニティが形成されやすい点が特徴です。
拓殖大学政経学部の学生数は 853 名となっており、東京経済大学と比較して大規模な学部構成を持っています。規模が大きいことで科目の選択肢が広がり、政治学と経済学を横断的に学びたい学生や、幅広いバックグラウンドを持つ学生と交流したい場合には魅力的な環境となります。学生数の多さは多様な視点が集まることにつながり、授業やゼミでの議論にも広がりが生まれやすい点が強みです。
両校を比較すると、東京経済大学は中規模で落ち着いた学習環境が整っているのに対し、拓殖大学政経学部は大規模で多様性の高い学生コミュニティを形成している点が大きな違いとなっています。静かな環境で腰を据えて学びたい場合は東京経済大学、幅広い価値観に触れながら学びを進めたい場合は拓殖大学が向いているといえます。
男女の比率
東京経済大学経済学部の男女比は 68 : 32 で、男性学生の割合が高い構成となっています。経済学部は全国的に見ても男性比率が高くなる傾向がありますが、東京経済大学でもその傾向がはっきり表れており、授業・ゼミ・サークル活動においても男性中心の構成になりやすい点が特徴です。ただし、女性学生も一定数在籍しており、少人数科目やゼミでは性別に関係なく交流が生まれる環境が整っています。
拓殖大学政経学部の男女比は 78 : 22 で、こちらも男性が多い学部構成となっています。政治学や経済学といった社会科学系の分野では男性比率が高くなりやすい中で、拓殖大学も同様の傾向を示しています。規模が大きい学部であるため、女性学生の絶対数は確保されていますが、全体の比率では男性が優勢となっている構成です。学科ごとに多少の偏りはありますが、日常的な授業やゼミでは幅広い学生との交流が可能です。
両校を比較すると、どちらも男性比率が高い点は共通していますが、割合としては東京経済大学のほうがやや男性寄りの構成となっています。男女比の違いが学修環境に大きく影響するほどではありませんが、キャンパスの雰囲気やコミュニティの形成に若干の差が出る可能性があります。落ち着いた小規模コミュニティを重視する場合は東京経済大学、より大規模で多様な学生層の中で学びたい場合は拓殖大学政経学部が向いています。
初年度納入金
東京経済大学経済学部の初年度納入金は 129.3 となっており、首都圏の私立経済系学部としては標準的な水準に位置しています。学費設定は大きく突出するほど高額ではなく、施設利用や実務科目などを含めた内容とのバランスが取れている点が特徴です。学びの範囲も経済学に特化しており、特別な追加費用が求められるケースも少ないため、費用面での見通しを立てやすい環境といえます。
拓殖大学政経学部の初年度納入金は 131 で、東京経済大学と比較してわずかに高いものの、大きな差ではありません。都心に位置する大学として標準的な設定であり、政治・経済の両分野を学べるカリキュラムの幅を考えると妥当な費用感といえます。こちらも追加の専門設備費などは限定的で、全体として大きく負担が増えるタイプの学部ではありません。
両校を比較すると、初年度納入金の差はごくわずかで、費用面における優劣はほぼないと言えます。学費を大きな判断要素にする必要はあまりなく、学びたい内容やキャンパス環境、卒業後の進路イメージなどを中心に選択する方が適切です。費用面での負担差が小さいため、他の要素を重視して志望校を検討しやすい組み合わせとなっています。
SNSでの評価
東京経済大学経済学部に関するSNSでの評価は、落ち着いたキャンパス環境や学びやすい規模感に好意的な声が多く見られます。特に、こぢんまりとした雰囲気で教員との距離が近い点や、学生生活が安定して送りやすいといった意見が比較的多く投稿されています。一方で、華やかさや派手さを求める学生からは控えめな印象を持たれることもあり、全体として堅実で実直な大学というイメージが形成されています。
拓殖大学政経学部のSNSでの評価は、都心立地の利便性と学生数の多さによる活気のある雰囲気に関するコメントが多く見られます。特にキャンパスが駅に近い点や、学生コミュニティの幅広さが肯定的に受け止められやすく、学内の活動やイベントに関する投稿も比較的多い傾向があります。一方で、学生数が多いことによるにぎやかさや、忙しさを感じるという声も一定数あり、賑やかな環境を好むかどうかで評価が分かれる面もあります。
両校を比較すると、東京経済大学は落ち着いた学修環境を高く評価する投稿が多く、拓殖大学政経学部は都心の利便性やキャンパスの活気に対する肯定的な意見が目立ちます。求める大学生活のスタイルによってSNS上の印象が異なるため、自分の生活イメージと照らし合わせて判断することが適切です。
合格難易度(偏差値・倍率)

偏差値(マナビジョン)
東京経済大学経済学部の偏差値は 58 で、首都圏の私立経済系としては堅実に中堅上位に位置する数値です。毎年の変動も比較的安定しており、受験生の学力層が一定して集まる傾向があります。経済学一本で学ぶ専門志向の層が多いこともあり、偏差値は学部の性質を反映した落ち着いた水準に維持されています。バランス型の受験生にとっては、しっかりと対策すれば射程に入りやすい偏差値帯といえます。
拓殖大学政経学部の偏差値は 47 で、東京経済大学と比較すると明確に低い帯に位置しています。政経学部は政治・経済を横断的に扱うことから受験層に幅があり、入試方式の多さもあって学力のボリュームゾーンが広めになりやすい特徴があります。そのため、偏差値はやや下がり気味の位置にあるものの、受験方式によっては得意科目を生かす戦略も取りやすく、挑戦しやすいレンジとして受験生から選ばれるケースも少なくありません。
両校を比較すると、偏差値の差は十ポイント以上あり、この差は私立中堅大学群の中では大きい部類に入ります。東京経済大学はより高い学力層が集まりやすく、学修水準も相対的に引き締まった環境です。一方で拓殖大学政経学部は入りやすい難易度に位置しており、政治・経済を幅広く学びたい学生にとって柔軟にアプローチできる偏差値帯といえます。偏差値だけで難易度を判断する場合、両校の階層差は明確です。
倍率
東京経済大学経済学部の倍率は 2.9 で、首都圏の経済系学部としては比較的標準的な水準にあります。倍率が低いほど入りやすいという一般的な見方に照らすと、東京経済大学は募集人数と受験者数のバランスが落ち着いており、特定年度に急激に難化する傾向はあまり見られません。受験方式も極端に広いわけではないため、倍率の振れ幅も小さく、安定した取り組みやすさが特徴です。
拓殖大学政経学部の倍率は 1.6 で、東京経済大学よりもやや低い数値になっています。これは行動科学・政治学・経済学と複数の領域を扱う政経学部ならではの受験層の広さや、方式ごとの出願の分散が影響していると考えられます。倍率が低いことは、東京経済大学よりもさらに入りやすい構造にあることを示し、受験生にとっては確実性を取りにいきやすい選択肢となっています。
両校を比較すると、倍率だけを指標とした場合には拓殖大学政経学部のほうが入りやすく、東京経済大学のほうがやや競争がある構造です。ただし差は大きくないため、学部選びでは倍率そのものよりも、学びたい領域や将来の進路、偏差値帯との相性を含めて総合的に判断するほうが適切です。倍率はあくまで参考値として活用するのが良いバランスといえます。
卒業後の進路

有名企業の就職率
東京経済大学経済学部の有名企業就職率は 6.8 で、学部規模を踏まえると安定した実績を示しています。特に公務員就職者が一定数いることも特徴で、進路が民間企業だけに偏らない点が、データの安定性や毎年の実績のぶれの小ささにつながっています。経済学で培う分析力や数的処理能力を活かしやすく、金融・流通・公務など多方面に進む学生が一定割合存在することも、この数値の背景にあります。
拓殖大学政経学部の有名企業就職率は 3.9 となっています。これは必ずしも実績不足を意味するものではなく、学部が大規模で進路が多方面に広がりやすいことから、特定カテゴリーの企業群に集中しにくいことが要因として考えられます。政経学部は政治・行政・経済分野の広い出口を持っており、警察・地方自治体・国家公務員を含む公的機関への進路が一定数存在するため、データが分散しやすい構造になっています。
両校を比較すると、東京経済大学の方が有名企業就職率の面では安定的に把握しやすく、数値そのものも比較的見えやすい形で公表されています。一方、拓殖大学政経学部は進路が広がりやすく、公務系の就職割合も一定して見られるため、特定の企業群に偏らないキャリア形成が可能です。指標としての見やすさを重視するなら東京経済大学、多様な公的機関や民間企業に幅広く進める柔軟性を重視するなら拓殖大学政経学部が適しています。
主な就職先
有限責任あずさ監査法人(2名)
みずほ銀行(2名)
東京特別区(3名)
東京国税局(1名)
東京経済大学経済学部では上記の他に、金融、流通、サービス、情報関連など多様な業種へ進む学生が見られます。特に、首都圏の中堅企業や安定した地域基盤を持つ企業との親和性が高く、経済学で培った数的処理力や課題分析力を強みに、営業、企画、総合職など幅広い職種に挑戦する学生が多い点が特徴です。また、公務員試験に向けたサポートもあり、行政系へ進む学生が一定数存在するため、進路全体が偏りにくくバランスの良いキャリア選択が可能になっています。
拓殖大学政経学部では上記の他に、地方自治体や国家公務員などの行政系職種、警察、消防といった公共安全分野への進路が特徴的に見られます。また民間企業ではサービス業、金融、専門商社など実務に直結しやすい業界への就職が比較的多く、ビジネス系の基礎を幅広く学べる学部の特性が進路に反映されています。学部規模が大きいため、学生の興味関心も多様であり、個人の強みを生かした形で幅広い業界に進む傾向があります。
両校を比較すると、東京経済大学はバランスの取れた民間就職と公務系進路が共存する点が特徴で、拓殖大学政経学部は公務系への進路がしっかりと見られる点と民間企業への進出の幅広さが魅力です。進路の方向性に大きな偏りはありませんが、行政分野や公共系を希望する学生にとっては拓殖大学政経学部がやや親和性が高い傾向があります。
進学率
東京経済大学経済学部の進学率は 0.9 で、学部卒業後はそのまま就職に向かう学生が中心となっています。経済学部はもともと実社会との接点が強く、金融や公務員などの職種に進むケースが多いため、大学院進学は必要に応じて選択される程度にとどまります。とはいえ、経済理論の探究を深めたい学生を対象とした進学ルートも一定数確保されており、必要に応じて大学院へ進める環境が整っています。
拓殖大学政経学部の進学率は 3.8 で、こちらも東京経済大学と同様に学部卒での就職が主流です。政治・経済の専門性を生かした公務系や民間企業への進路が幅広く、大学院進学は全体の一部に限られています。政経学部の場合、進路の多様性が大きいことから、学生が自身のキャリアの方向性に応じて進学の必要性を判断する傾向が強い点が特徴です。
両校を比較すると、どちらも進学率は控えめで、学部で得た知識をそのまま社会で活かす形が一般的です。進学率の差は小さく、進学を主要な判断軸とするよりも、就職先の傾向や学部の専門領域との相性を基準に学校選びを行う方が現実的です。進学を前提にした学部ではないため、両校とも就職を軸としたキャリア設計と親和性が高い点が共通しています。
留学生

受け入れ状況
東京経済大学経済学部の留学生数は 100 で、比較的落ち着いた規模の国際性を備えています。経済学という学問分野上、海外の経済情勢や国際関係に触れる機会は多いものの、学生構成としては過度に国際比率が高いわけではなく、授業やゼミで適度に異文化に触れられる環境が整っています。初めて国際的な学びに触れる学生でも馴染みやすく、日常的な学修の中で自然に多様性を体験できる点が特徴です。
拓殖大学政経学部の留学生数は 1315 で、東京経済大学と比較すると明らかに多い水準となっています。拓殖大学はもともと国際系分野に強みを持つ大学として知られており、その影響から政経学部でも海外出身の学生が多く在籍しています。授業・ゼミ・課外活動において留学生と接する機会が豊富で、日常的に多文化に触れられる点が大きな魅力となっています。国際的な価値観に触れながら学びたい学生にとっては好適な環境です。
両校を比較すると、国際性という点では拓殖大学政経学部が大きく優位であり、留学生比率の高さが学修環境の多様性を強めています。一方で、東京経済大学は落ち着いた国際環境で、適度な多文化交流を求める学生に向いている構造です。どちらも国際性は持っていますが、日常で触れられる密度には明確な差があり、求める国際経験の度合いに応じて選びやすい比較となっています。
海外提携校数
東京経済大学経済学部の海外提携校数は 47 で、交換留学や短期研修に利用しやすい適度な数の提携先を持っています。規模が大きすぎないため、留学相談やサポートが個別に行われやすく、初めて海外に挑戦する学生でも取り組みやすい点が特徴です。実用的な提携校とのネットワークが中心となっており、英語圏を含む主要な地域とつながりを持ちながら落ち着いた国際交流が可能です。
拓殖大学政経学部の海外提携校数は 56 で、東京経済大学に比べて明確に多い数となっています。拓殖大学は国際分野に強い伝統を持っていることから、長年にわたって多くの海外機関とのネットワークを形成してきました。アジア圏を中心に、さまざまな地域との交流を展開しており、留学制度の選択肢が幅広い点が大きな魅力です。短期・長期を問わず自分に合った留学プランを立てやすいのも特徴です。
両校を比較すると、海外提携校数では拓殖大学政経学部が大きく優勢で、国際経験を積むための選択肢の幅が広がっています。一方、東京経済大学は無理なく活用できる規模の提携校ネットワークを持っており、初めて留学に挑戦する学生や、限定的に国際経験を積みたい場合に向いています。国際性に対する重視度によって適した環境が分かれる項目です。
結局東京経済大学経営学部と拓殖大学政経学部のどちらが良いか

両校を比較すると、最も明確な違いは偏差値と国際性の二つに現れており、東京経済大学経済学部は偏差値 58 と比較的高い水準に位置する一方で、拓殖大学政経学部は 47 と、学びの入り口として挑戦しやすいレンジにあります。学力層の違いは学修環境にも反映されやすく、東京経済大学は落ち着いた雰囲気で学びやすい点が特徴です。
一方、国際性に関しては拓殖大学政経学部が明確に優位で、留学生数 1315 や海外提携校数 56 の規模から、多文化環境の中で政治と経済の双方を学びやすい構造になっています。東京経済大学は留学生数 100 と海外提携校数 47 が抑えめで、必要な国際性をコンパクトに確保するタイプです。
総合すると、偏差値と学びの安定感を重視し落ち着いた環境で経済学を深めたい学生には東京経済大学経済学部が向いています。一方で、国際的な視点や多文化との交流を重視しながら政治と経済を横断的に学びたい場合は拓殖大学政経学部が適しています。それぞれの特徴が明確に分かれる組み合わせであり、自身の志向に合わせて選択しやすい比較といえます。